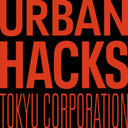こんにちは、東急株式会社「URBAN HACKS」採用担当です。
URBAN HACKSは、交通事業を軸に不動産、生活サービス、ホテル等多彩な事業を展開している東急株式会社が、街づくりにおけるDXを目的に、2021年7月より生まれた新組織です。現在、新たなイノベーションを生み出すべく、積極採用を進めています。
今回は、入社4年を迎えた社員の野口さん・石神さん・松田さんに、URBAN HACKSでのキャリアや成長の変遷をお伺いしました。URBAN HACKSのこれまでの歩みと特徴、まだまだ成長可能な無限の未来が見えてきました。
「挑戦できる大企業」に惹かれ、URBAN HACKSへ
―当初、皆さんがURBAN HACKSへの転職を決めた理由を教えてください。
野口:私はソフトウェアの受託会社に所属した後、医療系のスタートアップ企業を経て東急にジョインしました。開発領域はフロントエンドからバックエンドまで幅広く手掛けてきましたが、現在のメインはバックエンドです。東急を選んだ理由は、しっかり開発にコミットしたい思いがあったからです。東急は大企業でありながら、URBAN HACKS自体はスタートアップの要素が強いという環境が魅力でした。
松田:東急にジョインした理由は、少人数精鋭の組織で、スピーディな価値提供がしたかったからです。経歴としては美術大学を卒業後、テレビ制作会社やアプリ制作の会社、デーティングサービスを提供している企業を経て、東急に転職しました。私は現在プロダクトのUIUXデザインや利用促進施策クリエイティブのアートディレクションなどを担当しています。
石神:前職は大手小売企業で、プロジェクトマネジメントや事業開発を経験しました。やりがいはありましたが、次第に一つの事業領域に縛られず、更に多くの人に使われるサービスを作りたいという気持ちが強まってきました。その点、東急グループは、交通・不動産・リテールなど幅広い事業領域を持ち、人々の生活のあらゆる場面に関わるコングロマリットです。そのため、人々の生活を横断するサービスに携わることが出来ると思い入社しました。現在は「プロダクトオーナー」として、開発チーム、マーケティング、BizDevと共に事業成長を推進する役割を担っています。
―入社前と入社後で、イメージとのギャップはありましたか。
松田:入社後のギャップは特にありませんでした。というのも、VPoEの宮澤が転職前のカジュアル面談で「DXを推進していく組織としての課題」を説明してくれたからです。組織課題を明確にとらえ、誠実かつ現実的に話してくださるところに共感しましたし、それが入社を決めた理由にもなりました。
ギャップがあるとすれば、やはり東急グループの事業の幅広さです。入社前は東急線や東急ハンズぐらいがすぐ想起できる事業のイメージだったので、入社後に少しずつ自社事業を学んでいきました。
石神:良い意味でのギャップはありました。入社前は、大企業特有の縦割り組織をイメージしていました。実際には、プロジェクト単位で部署や企業を越え、連携する機会が多くあります。例えば、私が立ち上げたデジタル乗車券サービス「Q SKIP」は、交通事業者、改札機メーカー、商業施設などグループ外企業を含めた10社以上を巻き込みながら進めています。その分、私のようなマネジメント系の職種は、強い巻き込み力や調整力が求められます。
―入社後の3年間で、組織的にはどのような変化がありましたか。
野口:組織の拡大に伴い、雰囲気はだいぶ変わりました。入社当時はメンバーが20名ほどでしたが、今は100名ほどになっています。また、URBAN HACKSがグループ内にも浸透してきた印象がありますね。重要なシステム開発も依頼されるようになってきたので、責任が増え期待値が上がってきた反面、今までのようにアクセルベタ踏みではなくブレーキも調整しながらの動きになってきたかもしれません。「まずやってみよう」という挑戦のマインドを保ちつつ、慎重さも必要になってきたのが4年目の印象です。
松田:関わる部署や企業が増えてきたので、各組織の文化や雰囲気を学ぶことが増えてきました。それぞれの文化やコンテキストを理解して、適切な接し方を模索していく。接し方の違いも少しずつ学んでいます。

「東急のDNA」は、今も息づいている
―働いてきて感じたURBAN HACKSの企業文化や、風土はありますか?
野口:私は「昔の東急」を調べるのが好きで、入社前から「大東急(陸上交通事業調整法の趣旨に則って大同団結した当時の東急の呼称)」をなどを調べては「歴史ある会社だな」と思っていました。東急株式会社の源流を作った渋沢栄一や、東急グループの実質的な創業者・五島慶太の時代から流れる「東急のDNA」は、今もたまに感じます。
例えば、昔の東急が道を切り開いてきたように、石神さんが立ち上げた「Q SKIP」も関東圏初のサービスでした。普通だったらなかなか挑戦できそうにない「業界初」に、「自分たちがやっていかねば」という強いパワーで切り込んでいますよね。東急のDNAが受け継がれているからこそ、「Q SKIP」も出来たのだろうし、今の東急にも攻めの姿勢があると感じています。
石神:「東急のDNA」については、私も共感しています。東急グループ全体として、交通インフラや不動産など単一サービスの提供がゴールではなく、「その先の暮らしをどう豊かにするか」という企業文化が根付いていると感じます。
松田:東急のブランディングについては、いい意味でおごそかな雰囲気を感じます。単に派手なことや身の丈に合わないことはしないというか。だからこそ、競合他社との差別化が図れないことが課題だったりもするので、今後はブランディングを見直すフェーズなのかもしれません。過去記事にも「老舗からの脱却」とありましたが、お客様にどういうイメージでとらえていただくのか、そういう体験設計から考え直すのではと、デザイナーとして感じています。
目指すは「老舗からの脱却」|URBAN HACKS初の単独開催イベント「Designer Night」の裏側
各自の専門性が進化し、個から組織へと視野が広がる
―この3年間で、業務内容や役割の変化はありましたか?
野口:業務内容はほぼ変わっていませんが、役割は少し変わってきているかもしれません。上司部下などがないフラットな組織なので、役割自体少ないのですが、社員増に伴って評価制度を作ったり、評価する側の役割が出てきたりしています。「全員がフラットで」とは言いつつも、皆経験値も年齢も違うので、そういう意味での変化は少しありました。あとは、単純に開発の量や種類が増えました。私は3年間で5件ほどのプロジェクトに関わりましたね。

松田:私は正直、プロジェクトも役割もほぼ変わっていません。東急カードアプリ「東急カードプラス」のリニューアルプロジェクトに参画しています。サービスの対象者や機能も変わっているので、開発フェーズが「0→1」から「1→100」へと変わりました。とはいえ、まだまだUIをアップデートしたり、世界観を一から見直したりと、気持ちとしてはずっと「0→1」なので、それがやりがいや楽しさでもあります。ステークホルダーもかなり増えているので、それを踏まえた立ち回りを考えていく必要があります。

石神:私は入社後、「東急カードプラス」のリニューアルプロジェクトでプロダクトマネージャーを経験しました。その後、グループ各社と連携し「Q SKIP」の立ち上げを主導。現在はプロダクトオーナーとして、より戦略的な視点で事業全体の設計にも関与しています。
特に「Q SKIP」は、従来は紙の乗車券やICカードが主流だった公共交通機関に、QRコードやクレジットカードタッチによる新たな乗車手段を導入するということで、一番の挑戦でしたね。
大変だったのは、やはりステークホルダーを巻き込みながら事業を進めることです。その際意識したのは、データやファクトで語ることと、少しずつすり合わせを進めることです。それぞれのバックグラウンドや利害が異なるので、同じ目線で語れるようデータを意識したり、データ分析に力を入れたりしました。
とはいえ、新規性の高いサービスはデータやファクトが整っていないことも少なくありません。そうした拠り所がない状態で、色々な思惑がある関係者の意識を統一することは非常に困難でした。そうした時こそ「小さく」巻き込むことを意識しました。そうすることによって、「少数でも認識が擦りあっていくこと」と「自分の考えが少しずつブラッシュアップされること」が両輪で回り、最終的にチーム力になることを、この3年間で学ばせてもらいましたね。

フェーズ2の今、点と点をつなぎ “面” にしていく
―今後のキャリアの展望や、これから挑戦したいことを教えてください。
松田:さまざまなステークホルダーと同じ目線でプロジェクトを進めるために、デザイナーとして出来ることを、より突き詰めていきたいです。また、グラフィックやアニメーションなどの表層的な表現方法を、さらに追求し続けたいと思っています。普段は、その上段の要件定義やサービスデザインに時間を割いてしまい、表層的なデザインにかける時間が減りがちなので。しっかりとデザインに時間をとり、クオリティの高いものを引き続き追及したいです。
野口:2030年には渋谷が大きく変わった状態になるので、その中で東急が、いろいろなサービスをうまく展開できていたらいいなと思います。現在ある東棟の他にも渋谷スクランブルスクエア 中央棟・西棟が2027年度に開業予定だったり、東京メトロ銀座線の路線上に「ヒカリエデッキ」も整備され、東急百貨店 東横店の跡地あたりにも遊歩道ができたりして渋谷の東西南北が回遊しやすくなると思います。きっとこれからも海外からたくさんの人が来るでしょうし、オフィスワーカーが働きに来たり、移動で渋谷を通る人もいたりする中で、「便利で楽しく、ワクワクする何かが作れていれば」という希望があります。
石神:今後注力したいのは、グループやプロダクトの垣根を越えた連携を更に加速させることです。私たちが入社した当時、URBAN HACKSは発足間もない時期で、まずは社内での認知獲得と信頼の構築から始まりました。足元の課題に向き合いながら、顕在化しているニーズに一つひとつ丁寧に応えていくことに取り組んできた結果、多くのユーザー接点を持つプロダクトが複数生まれました。ただ、都市のDXを本質的に進めていくには、個別最適の積み上げだけでなく、チームやプロダクトを越えた連携による全体最適が不可欠です。その実現に向けて、「点」から「面」への展開を見据えた新たな挑戦を始めていきたいと考えています。
野口:そんな中で、フェーズ1でデジタル化を行い、フェーズ2でその「点」を増やして、フェーズ3でその点を「面」にしていくことを目指しています。今はまさにフェーズ2の佳境に入っていて、事業部からの信頼を泥臭く積み上げていく必要があります。良い信頼関係が出来ているので、URBAN HACKSを介して、つながりのメッシュが加速していくのではないでしょうか。例えば最近は、組織活性化委員会の試みで、「ゆうべの会」という懇親会を始めました。月に1回、事業部の方をお呼びしてお食事を囲む会で、割と好評です。そうやって少しずつメッシュを広げていけば、実を結んでいくだろうという期待があります。
―最後に、応募を検討する方へ一言お願いします。
野口:4年経った今でも東急で働き続けている私の情熱を支えてくれる言葉があります。 それが、URBAN HACKS のウェブサイトに掲げたこのフレーズです。 「テクノロジーによる街づくりは、まだまだ可能性に満ちている。」 この言葉を、今、改めて強く実感しています。 東急には、まだまだ伸びしろがある。だからこそ、挑戦しがいがあるんです。 もし「テクノロジーで街をもっと面白くしたい」と思ったなら、きっとここはあなたの心がワクワクするフィールドになると思います。
石神:私たちはこの3年間で、組織だけでなく人の変遷も間近で見てきました。そうした中で実感したのは、URBAN HACKSに向いているのは、「自分の考えを語るだけでなく、多様な価値観や制約条件を受け入れながら、泥臭く行動し、変化を具体的な形にできる人」だということです。URBAN HACKSは東急グループの一員である以上、「リアルとの融合」に挑み続けることが求められます。そのためには、技術力だけではなく、現場を支える関係者の声を聞き、共に歩む力、相手に応じた交渉や伝え方の工夫が欠かせません。「こうあるべき」と理屈を押しつけるのではなく、相手への敬意を持ちながら、粘り強く関係を築いていけること。それこそが、URBAN HACKSらしさを体現できる人だと感じています。
松田:3年間働いてきて、率直に「この会社、とても働きやすい」と感じています。パンデミックがひと段落した今でも、フルリモートに近い形で働けて自分らしい選択が可能です。そのおかげで仕事の成果も出しやすいと思いますし、長く働き続けられるポイントかなと思います。職人気質の方も、割とマイペースな働き方がしやすいので、向いているかもしれません。
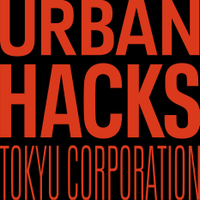

/assets/images/7179385/original/575840e0-04e1-4ae9-82c9-7b849b0a54f5?1626072058)
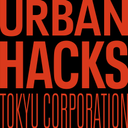
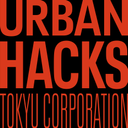
/assets/images/7179385/original/575840e0-04e1-4ae9-82c9-7b849b0a54f5?1626072058)


/assets/images/7179385/original/575840e0-04e1-4ae9-82c9-7b849b0a54f5?1626072058)