研究者起業家の、クラファン大敗戦記と3つの教訓。
「91%の成功確率」と言われたクラファンが、なぜ失敗したのか?
研究者として、そして起業家として信じたロジックが通じなかった現実。
今回は、昨年2024年に挑戦したクラファンの全記録を率直に綴ります。
私、古谷優貴はもともと大学で研究者として、数多くの論文執筆に取り組んできました。その後、研究の知見を社会に還元すべく起業。過去には株式投資型クラウドファンディングサービスであるファンディーノを通じて3,000万円の資金調達にも成功しています。
当時は多くの方々から「これは絶対に成功する」「次世代のインフラになる」といった期待の声をいただき、自分自身もその声に背中を押される形で、ある種の自信とともに歩んでいました。
しかし今回挑戦したクラウドファンディングは、これまでの成功とは異なる、厳しい結果となりました。社内ではX(旧Twitter)での発信やメルマガ配信、知人への直接の声かけなど、様々な広報施策を展開しましたが、期待していたほどの効果は得られませんでした。
結果的に、私個人の声がけに応じてくださった方々の支援が中心となり、組織としての広報力に課題があったことを痛感しました。
また、最大の反省点としては、支援を期待すべきターゲット層に対する理解が不十分であったことが挙げられます。いわゆる「あしながおじさん」的な支援者層を想定していたにもかかわらず、そのニーズに応えるようなリターン設計やアプローチが欠けていました。
さらに、初動のデータが非常に良好だったことで、過信が生まれ、リターン内容の改善や施策の修正が後手に回ってしまったことも大きな要因でした。
AIの予測では「500万円達成の確率91%以上」「1,500万円も77%以上」とされていたことが、判断の甘さに拍車をかけた部分も否めません。
年末に近づくにつれて支援の伸びは鈍化し、「このままでは目標に届かないかもしれない」という空気が社内に漂い始めました。それでも多くのメンバーは「最低でも300万円は達成できるだろう」と考えており、危機感の共有が遅れてしまったのも事実です。
最終週に入り、ようやく本格的なラストスパートをかけましたが、結果として支援総額は1,186,000円。目標の36%という結果に終わりました。
All or Nothing形式であったため、資金は受け取れず、支援者の皆様に対してもリターンをお届けすることができませんでした。
結果として、応援してくださった方々の期待を裏切る形となってしまったことを、深く反省しております。
この失敗を経て、私は3つの重要な教訓を得ました。
過去の成功体験にとらわれず、常に「今回の挑戦に適した手法」をゼロベースで考えること。想定する支援者層の理解を深め、ニーズに応じた施策を迅速に実行すること。
そして、いかにデータが好材料であっても、それに依存することなく現場感覚を持ち続けること。
いずれも基本的なことではありますが、今回それがいかに重要かを改めて思い知らされました。
現在はこの反省を踏まえ、過信を排し、データと実情の双方を冷静に見つめながら、次なる挑戦に向けた準備を進めております。たとえば、中古機器の売買領域では既に一定の成果が出始めており、より持続可能な資金調達の在り方についても再構築を進めています。
今回の失敗は、確かに厳しいものでした。しかしながら、これを糧として、より堅実かつ確度の高い事業展開へとつなげてまいりたいと考えております。

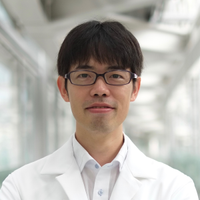
/assets/images/9988596/original/189ed614-eb94-400b-b3e0-c7ad8c876360?1658812601)


/assets/images/9988596/original/189ed614-eb94-400b-b3e0-c7ad8c876360?1658812601)
/assets/images/9988596/original/189ed614-eb94-400b-b3e0-c7ad8c876360?1658812601)

