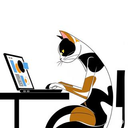SIerから飲食店長を経て、再びITへ――独学1年半でフルスタック×インフラ自動化を形にするまで
Photo by Tanya Barrow on Unsplash
キャリアの分岐点:なぜ一度ITを離れたのか
2006年、SIerに就職して大手メーカーグループの医療システム電子化プロジェクトに参加しました。設計補助・テスト・インフラ構築を担当し、システム運用の基礎を学びました。その後、BPO企業で給与計算システムの運用・保守を経験し、安定したシステム運用の重要性を実感しました。
しかし、正直に言えば当時の私にはインフラの面白さが全く理解できていませんでした。2006年当時、サーバーやネットワークの設定は全てGUIでポチポチと手作業で行うしかありませんでした。同じような設定を何度も何度も繰り返す日々――ただただ**「つまらない」**と感じていました。
「もっと面白い仕事がしたい」「人と直接関わって成果を実感したい」という想いから、飲食業界へ転身しました。
店長、バーテンダー、料理人として2年半、スタッフの採用・育成、売上管理、顧客満足度向上といった店舗運営の全てを統括しました。カウンターに立ち、キッチンで料理を作り、同時に経営管理も担う――お客様の笑顔やスタッフの成長を直接見られることにやりがいを感じました。
しかし2010年、店が閉店。再びIT業界へ戻り、教員向けシステム開発を行う企業でACCESSを使ったデータベース開発を2年間担当しました。
2012年以降は体調面の理由で一時キャリアを中断しましたが、2017年から体調が回復し、Webライターとして活動を再開しました。IT技術への興味は完全には消えておらず、2024年春頃、本格的にプログラミング学習を開始しました。学習を進める中で、Terraformというツールの存在を知ったのです。
「インフラをコードで管理できる」――その瞬間、あの当時の「つまらなさ」の正体が分かりました。手作業でポチポチやっていた作業は、今ではコードで自動化できるものになっていたのです。
「これなら面白い。これならやりたい」――そう確信し、クラウドエンジニアとして再挑戦することを決意しました。
独学で挑んだフルスタック開発
2024年春から独学でプログラミングを学び始め、最初はHTMLやCSSから始め、徐々にJavaScript、TypeScript、Reactへと学習範囲を広げていきました。
2025年1月、それまでの学びを形にするため「ハンニバルのアルプス越えルートアプリケーション」という個人プロジェクトをスタートしました。歴史が好きで、古代の戦略や地理に興味があったため、このテーマを選びました。
要件定義から設計、フロントエンド・バックエンド開発、インフラ構築まで一貫して担当し、React、TypeScript、Mapbox GL JSでインタラクティブな地図UIを実装しました。バックエンドはNestJSとGraphQLでAPI設計を行い、データベースにはPostgreSQLを採用しました。
インフラ自動化への挑戦
このプロジェクトで最も力を入れたのが、TerraformとGitHub Actionsによる完全自動化のCI/CDパイプライン構築です。過去のインフラ運用経験から、手作業による運用は属人化とミスの温床になると痛感していました。
この構成を手作業でデプロイすると、VPC、ALB、NAT Gateway、ECS Fargate(Blue/Green環境)、RDS、DynamoDB、S3、CloudFront、各種セキュリティ設定など、全て合わせて約3-4時間かかります。しかしTerraformとGitHub Actionsによる自動化により、コードをpushしてから本番環境へのデプロイ完了まで約10分に短縮できました。
さらに、ブルー/グリーンデプロイメントとカナリアリリースを実装することで、無停止リリースと自動ロールバックを実現しました。問題が検知された場合、手作業なら15-20分かかるロールバック作業が、自動で数分以内に完了します。
また、CloudWatchでのログ監視やCloudTrail、GuardDutyを活用したセキュリティ監査も行い、運用の安定性とセキュリティを両立させました。
技術とマネジメント、両方の視点
飲食店長として学んだ**「目標を共有し、チームで達成する」**経験は、クラウドエンジニアの仕事と本質的に同じだと考えています。
店舗運営では、単に日々のオペレーションをこなすだけでなく、積極的に外部との協業も行っていました。近隣の魅力的なバーを自分で訪れ、そこのバーテンダーと関係を築き、ゲストバーテンダーとしてイベントを企画・実施していました。自店舗にはない魅力を持つ人材を見つけ、交渉し、協力して新しい価値を生み出す――この経験から、外部リソースを活用してより大きな成果を生み出すことの重要性を学びました。
クラウドエンジニアも同様です。社内のアプリケーション開発者、事業部門と協力するだけでなく、AWSサポート、外部SIer、技術コミュニティのエンジニアなど、外部の知見を積極的に取り入れながらプロジェクトを成功させる必要があります。
個人プロジェクトでも、エンジニアコミュニティで積極的にコードレビューを依頼し、設計・パフォーマンス・セキュリティに至るまで厳しいフィードバックを受けながら品質を向上させました。この「自分だけで完結させず、より良い知見を持つ人と協力する」姿勢は、飲食店長時代に培ったものです。
次のステップ
約1年半の集中学習で、フロントエンドからバックエンド、インフラ自動化まで一貫して構築できるスキルを身につけました。しかし、個人プロジェクトはあくまでスタート地点です。実際のビジネス現場で、チームと協力しながら価値を生み出すことが次の目標です。
クラウドエンジニアとして、以下のような貢献ができると考えています:
- インフラのコード化と自動化:手作業による運用を削減し、チーム全体の生産性を向上
- CI/CDパイプラインの構築・改善:デプロイ頻度を上げ、リリースリスクを低減
- セキュリティとコスト最適化:CloudWatch、CloudTrail、GuardDutyを活用した監視体制の構築と、無駄なリソースの削減
- 技術と非技術者の橋渡し:飲食店長として培ったコミュニケーション能力を活かし、事業部門とエンジニアチームをつなぐ
GitHub: https://github.com/kmryst/terraform-hannibal
私のGitHubリポジトリでは、実際のコードやインフラ構成をご覧いただけます。もし興味を持っていただけましたら、ぜひお話しさせてください。