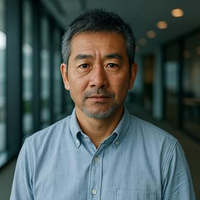朝、自分の机に置いたはずのメモの位置が少しだけずれていた。誰かが触れた形跡があるわけでもないのに、何かが移動したような確かな違和感があった。そのわずかなズレを見つめていると、頭の奥に柔らかいざわめきが生まれ、今日がこれまでと同じでは終わらない予感だけが先に歩き出していった。こういう直感は大抵当たる。だからこそ、そのズレを放置せず、むしろ自分から近づいていくことにした。
メモを手に取ると、書いた覚えのない行がひとつ増えていた。自分の字にしか見えないのに、まったく思い出せない。未来の自分が今の自分に何か残していったような、そんな錯覚を抱かせるほど自然にそこにあった。奇妙なのに怖くないのは、内容が曖昧な問いだったからだ。その問いは、これから迎える選択の分岐に対して、自分がどんな視点を持てるのかを試すような響きを持っていた。
その問いに導かれるように外へ出ると、普段歩く道の輪郭がわずかに変わって見えた。いつも通りの景色なのに、奥行きがひとつ増えたような感覚があって、まるで背景のレイヤーが一枚めくれたような違和感が心地よかった。人の表情や会話の端々から、普段なら意識しない意図の温度まで伝わってくる。世界が急に丁寧に話しかけてくる日は、自分の内側に未整理の余白が生まれている証拠なのかもしれない。
歩きながら、さっきのメモの謎の一行がじわじわ意味を帯びていくのを感じた。未来の自分が書いたという仮説を置いた途端、その一行は助言でも予言でもなく、ただの「可能性」そのものに変わった。これから選ぶ道の先に、今の自分では見えない風景があることを示すサイン。人は変わることを恐れているように見えて、実際は変わらずにいることをもっと恐れているのかもしれない。その恐れは静かで、誰にも見えなくて、気づいたときには心の奥に根を張っている。
そんなことを考えていると、ふと立ち止まってしまった。ここに立つ理由もないのに、足が止まったことだけが確かだった。そこで周囲を見渡すと、いつもは通り過ぎていた場所に新しい意味が浮かび上がってくるように思えた。自分の行動が変わらない限り、景色は永遠に同じ顔をし続ける。けれど、視点が変わり始めると、今まで背景だと思っていた場所が急に主役のように存在感を持つ。未来の自分からの下書きは、それに気づけと言っているようだった。
会社や仕事を選ぶときも、たぶん同じ構造がある。見えている情報だけで判断しようとすると、選択肢は狭くて息苦しい。けれど、見えていない層に気づいた瞬間、選べる道が静かに増えていく。挑戦の原型は、壮大な覚悟ではなく、ただ一歩だけ視線の角度を変えることなのかもしれない。その角度の差が、数ヶ月後にはまったく違う未来へ続いていく。
夕方、再び机に戻ると、例のメモは朝よりもしっくり馴染んで見えた。謎が解けたわけではないのに、そこにあるべきだと自然に感じる。未来の自分から届いた下書きという仮説は現実味を帯び、まだ見ぬ自分と今の自分がひそかに連携しているかのようだった。今は意味が曖昧でも、いつか点が線になる日が来る。その線は、誰かに合わせた直線ではなく、自分だけが引ける少し奇妙で柔らかな軌道だ。
今日の小さなズレが、未来の自分につながる最初の証拠だとしたら、この違和感こそ歓迎すべきシグナルだ。まだ言葉にならない未来の声を、これからも拾い集めていきたいと思う。