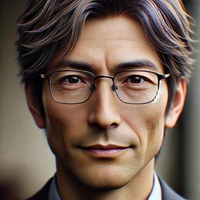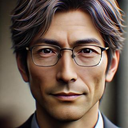【本田教之】消されたホワイトボードの跡に、チームの未来が見えた
Photo by Paul Hanaoka on Unsplash
ある日、オフィスに入った瞬間、ホワイトボードが真っ白になっているのに気づいた。
昨日までびっしりと書かれていた設計メモも、タスクも、誰かの落書きも、きれいさっぱり消されていた。
その白さを見たとき、なぜか少しだけ胸がざわついた。
「きれいになってよかったですね」と隣のメンバーが言った。
たしかに見た目はすっきりした。だけど、僕にはそこに“何かの終わり”を感じた。
あのボードに書かれていた線や文字は、単なる情報ではなかった。
議論の熱、迷い、ひらめき、すれ違い。
チームが「どうすれば良くなるか」を探していた、その痕跡だった。
エンジニアとして20年、僕は数多くのシステムを設計してきた。
どんなプロジェクトでも、最初にホワイトボードを使う。
要件を整理し、データ構造を描き、矢印で関係をつなぐ。
その過程で、アイデアは何度も消され、書き直される。
でも、いつも思う。
本当に価値があるのは、完成した図よりも「消した跡」なのではないかと。
システムもチームも、きれいすぎると息苦しくなる。
完璧なドキュメント、整理されたコード、整然とした会議議事録。
それらは美しいが、どこか人間味が薄れていく。
現場では、失敗の跡や迷いの線の中にこそ、学びや成長が詰まっている。
それを残す文化が、チームの“厚み”をつくるのだと思う。
独立して会社を立ち上げてから、この「跡」をどう扱うかが僕のテーマになった。
効率化やDXが進む時代に、どこまで“消さない勇気”を持てるか。
Slackの履歴をすぐ消すより、あえて残しておく。
コードレビューの指摘も、正すだけでなく、その背景を共有する。
組織の中に「人の軌跡」を残すことが、今の時代にはいっそう重要になっている。
ホワイトボードが消された日、僕は何も書き足さず、そのままの白さを少し眺めた。
そして思った。
これは「終わり」ではなく、「次の余白」かもしれない。
跡が消えたからこそ、次に何を書くかが問われている。
システムの設計も、チームの未来も、同じことだ。
人はしばしば、きれいな成果を残そうとする。
でも実際に人を動かすのは、“汚れた跡”の方だ。
消すことと、残すこと。
この小さな選択の積み重ねが、チームの文化を形づくっていく。
僕は今日も、ホワイトボードの前に立つ。
そして新しい線を引くたびに、昨日の跡を思い出す。
あの消された線の向こうに、僕たちが描くべき未来がある気がしてならない。