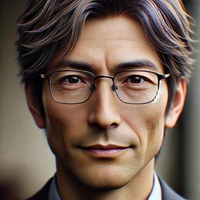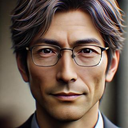【本田教之】光を当てられるより、“影をつくる側”でいたいと思った日
Photo by Monica Valls on Unsplash
ある日、同僚に「もっと目立った方がいいよ」と言われた。彼の言葉は悪気のないものだったし、確かにその方がキャリア的には得をする場面も多い。でも、なぜかその言葉が胸に引っかかった。僕は本当に光を当てられたいのだろうか。
仕事をしていて一番ワクワクする瞬間は、誰かが輝き始める時だ。新しいメンバーが自分のアイデアを実現して笑顔になる時、チーム全体が一つの方向に動き出す時。その中心に自分がいなくてもいい。むしろ、その瞬間を生み出す“背景”でいられることが嬉しい。
光は目立つけれど、影をつくるものがなければ存在できない。スポットライトの下に立つ人を支えているのは、見えないところで試行錯誤している人たちだ。僕はいつの間にか、そういう存在になりたいと思うようになっていた。
以前、プロジェクトでトラブルが起きたことがある。誰もが焦り、誰もが責任を感じていた。僕は目立たないところで一つずつ問題を整理し、必要な情報を集め、少しずつ空気を整えていった。結局、解決の瞬間に拍手を受けたのはリーダーだったけれど、それを見て「これでいい」と思った。光が当たる場所に、自分の影が静かに伸びている感覚があった。
「影をつくる側」でいることは、決して地味ではない。目立たないからこそ、自由がある。誰かのアイデアを後押ししたり、メンバーの弱点をカバーしたり。気づかれなくても、確かに流れを変えられる。大きな成果の裏に、たくさんの静かな努力が重なっている。それが見えるようになると、仕事の景色が変わる。
最近、若いメンバーに「目立たない仕事って、どうモチベーションを保つんですか」と聞かれた。僕は少し考えてから答えた。「光は誰かが見てる。でも、影は自分だけが知ってる。だから面白いんだよ」。その瞬間、彼がふっと笑った。多分、少しだけ伝わったのだと思う。
チームというのは、不思議な生き物だ。光が強すぎても、影が濃くなりすぎても、うまく進めない。大事なのは、バランスを保つ人の存在だと思う。僕はその“光と影の間”を調整する仕事が好きだ。目立たなくても、チームが動き出す瞬間の空気の震えを感じるとき、そこに確かに自分の仕事がある。
光の下に立つ人がいるからこそ、影をつくる側にも意味がある。どちらが正しいわけでも、どちらが偉いわけでもない。ただ、僕はこれからも影をつくる側として、誰かの輝きを見守りながら働いていきたい。
それが、僕にとっての“仕事の理想形”だと思っている。