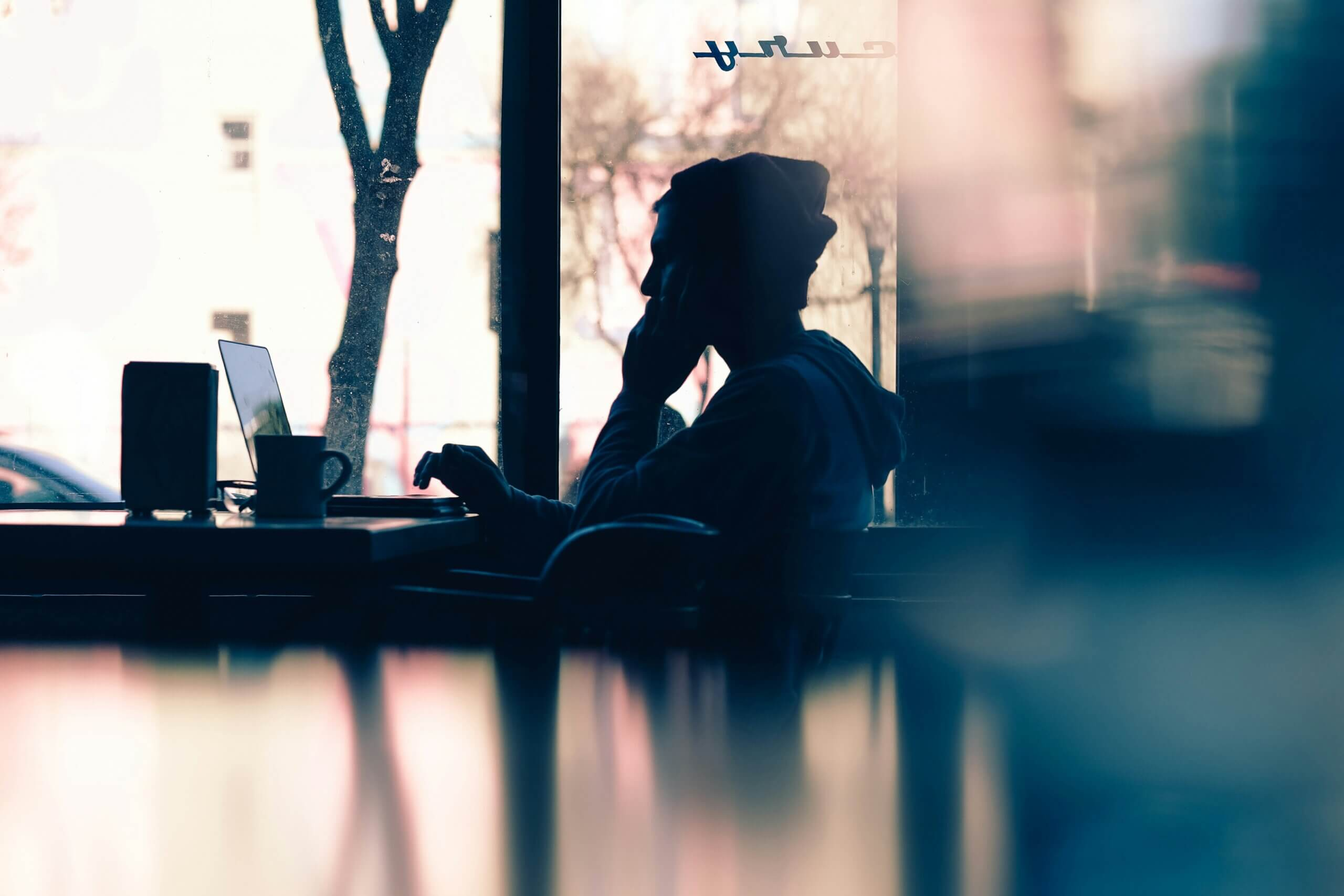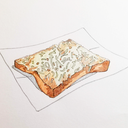Business social network with 4M professionals
Tomonori Shimatsu
株式会社アイトーン / マーケ/EC/コーワーキングスペース運営
Self Introduction
Available to logged-in users only
Ambition
複数の業界にて顧客対応をしてきたことから、お客様とサービスの間に立ち、双方に本質的価値を届けてきた経験をより活かせる職務に携わることを望みます。
マーケター(事業/営業/Webサイト連携)
税務SaaSのスタートアップ初期のフェーズにて、ビジネスサイドに広範囲に携わる。 ・会社のミッション・ビジョン・バリューの言語化 ・4つのWebサイト制作:各4事業の内容整理、サイト構成案の作成、デザイナー/コーダーへの業務デ
株式会社オールウィン5 years
WEBコンテンツマーケター
バックオフィス企業のWeb事業部にて、お客様の課題感のヒアリング・BtoBサイトの長期施策の提案と運用を担当。 ・マンションリノベーション事業のマーケティング:数千万円単価のBtoC領域にて、集客から成約するまでの仕組みをゼロから構築。クライアントと協力関係を築きながら、月3件成約する
翻訳(Side)
100句の百人一首を英語に翻訳。2018年に参加していたライティングゼミで知り合ったデザイナーさんが私の文章を読んで、声をかけてくれたことから生まれたプロジェクト。
株式会社清水坂ジュエリー3 years
実店舗店長
販売力と販売プロセスの言語化と共有を評価いただき、20名の販売スタッフのリーダーとしてチーム販売力を高める接客スタイルを促進。毎年の売上昨年比の更新、2016年度上半期には過去4年で最高の売上を記録。店舗動線の改善、販売プロセスのマニュアル化を行い、離職率の低下、売上分析と向上に貢献。
- 書籍の挿絵制作-
そうげんカフェ4 years
店長
全ての業務を担当した後、 お客様対応と業務再現性を評価いただき、 店長に昇進。 全レシピを言語化/数値化。引き継ぎ作業の改善と、味の再現性を向上させる。 オリジナルメニューとして自家焙煎コーヒーの開発を行い、 仕入れから焙煎、ドリップ、 保存方法、テイクアウトまで全工程の改善を一人で行い、店舗のブランディングに貢献。
ロマンス語学習3 years
スペイン語・フランス語・ポルトガル語・英語
アルゼンチンのコルドバ市に滞在。複数の外国語専門学校に通う。スペイン語で英語・フランス語・イタリア語・ポルトガル語の授業を受ける。最後の半年は、コルドバ大学に入学し、スペイン語でスペイン語を学ぶ。
英知大学4 years
スペイン語スペイン文学科
スペイン語、スペイン文学、ラテンアメリカ文学の学習。 個人的にロマンス語(フランス語、イタリア語、ポルトガル語)も学習を進める。
愛農学園農業高等学校3 years
稲作部
全寮制の農業高校で稲作を専攻。当時は日本で唯一の「有機農業」を学べる少人数の高校。実践重視の教育(1日の大半が農作業)のもと、農業を学ぶ。