Skyland Ventures(以下、SV)の挑戦と成長は、誰が支えているのか。
数多くのスタートアップに出資し、“攻め”の姿勢で成長を続けるSV。
その裏側には、日々の業務を着実に、そして柔軟に支えるコーポレートチームの存在があります。
今回お話を伺ったのは、SVのコーポレートマネージャー・佐々木さん。
もともと上場企業や上場子会社などで事務職を中心としてキャリアを歩み、一見普通の人が見れば地味で退屈そうに見えるような業務に喜びを見出してきた彼は、VC業界に気がついたらどっぷりとハマり
今では「挑戦する組織の裏方を支える」存在として活躍しています。
そんな佐々木さんへ
・なぜSVで働くことになったのか。
・どんな価値観を大切にし、どこへ向かっているのか。
その背景にあるストーリーに迫りました。
インタビューを担当するのは、SVで採用広報を担当している山本です。
目次
入社のきっかけと、初めての仕事
-きっかけは「木下さんを手伝ってあげて」という一言
-最初は試行錯誤しながらのスタート
新しい環境への適応と成長
-徐々に業務の幅を広げた成長”
-コロナ禍で訪れた“学習の時間”
新しい挑戦とスピード感
-一度経験したことから「応用」することの重要性
-スピードと精度のせめぎ合い
木下さんとの連携と”少ない言葉”の仕事術
-「余白をもって伝える」
SVの組織成長と、これから
-10人の才能ある個人が集まった組織へ
-ルールの整備と成長痛
SVに必要なコーポレート人材とは
-「誰も拾っていないボールを拾える人」
<プロフィール>
名前
Skyland Ventures コーポレートマネージャー 佐々木優(Masaru Sasaki)
経歴
・上場企業の管理部で総務法務など幅広く経験
・独立系投資会社にて日本と中国のスタートアップ投資の関連業務に従事
・2019年 11月 Skyland Venturesに入社
入社のきっかけと、初めての仕事
-きっかけは「木下さんを手伝ってあげて」という一言
山本:
まずはSVに入社されたきっかけを教えてください。
佐々木:
当時、SVの関係者(現在はSVのGeneral Partner(GP)の一人である袁小航氏)の個人会社のスタッフだった自分が「木下さんが大変そうだから、ちょっと手伝ってあげて」と声をかけられたのが始まりでした。
軽い気持ちでオフィスのあったコワーキングスペース(旧ハイブシブヤ)に行ってみると、整理されていないように見える荷物や本が山積みで、「引っ越しの手伝いかな?」と思っていたくらいです。
ところが木下さんに「まず打ち合わせしましょう」と言われて。掃除をするのに打ち合わせが必要なんだと思っていたら、話がどんどん実務の内容になっていきました。
「これは引っ越しじゃないぞ」と気づいたときには、もう本格的なコーポレート業務の話が進んでいました。
私にとっては、ひょうんなことからSVとの関係がはじまりましたが、今思うと滅多とない機会だったので、ご縁をいただいた袁さんには本当に感謝しています。
-最初は試行錯誤しながらのスタート
佐々木:
私は過去に上場企業の管理部門にいましたが、VCファンドやスタートアップで働いた経験はほぼありませんでした。
投資の契約書は管理部門において見慣れているものとは違いますし、投資の業務に登場する用語も初見では分からないといった中でのスタートでした。
最初は調べながら、試行錯誤しながらのスタートで、管理業務の経験はあったもののほぼ未経験というくらいのレベルでした。
新しい環境への適応と成長
-徐々に業務の幅を広げた成長”
山本:
入社して最初に取り組んだのはどんな仕事でしたか。
佐々木:
ファンドの会計や、運営会社の管理業務から着手しました。
外部の会計士や税理士と連携の上、さまざまな取引の内容や背景を理解しながら、会計処理の状況を確認するような仕事でした。慣れないことも多かったので、ひとつひとつ丁寧に整理しながら進めることを意識しましたね。
その後は、決算や報告資料の準備にも携わるようになり、徐々に全体像をつかみながら業務の幅を広げながら、着実に知識を積み重ねていくことができたと思います。
その後はファンドの決算対応も任されるようになりましたが、まだ入社して数ヶ月しか経っていない時期で、情報の波に溺れるくらいドタバタしていましたね。
-コロナ禍で訪れた“学習の時間”
山本:
それは大変なスタートでしたね。
佐々木:
そんなスタートでしたが、2020年になると、コロナ禍に入り、スタートアップ界隈全体の先行きが怪しくなる期間があり、SV全体の活動が一時的に落ち着きました。
その頃は落ち着いて知識を深めたり、業務の型を整えるにはちょうどよいタイミングでした。
新しい挑戦とスピード感
-一度経験したことから「応用」することの重要性
山本:
SVでは新しい取り組みも多いと思います。そうした“初めての取り組み”はコーポレートチームにもあると思うのですが、どのように向き合ってきたんですか?
佐々木:
たしかに、例えばターゲットファンドを組成したり、2022年にはWeb3投資を始めてみたり、投資先に対する取り組みであったり、これまでにない新しい動きはSVでは次々に生まれますね。
入社して2-3年くらいは、なんだかんだで代表の木下さんと一緒に動いていたような気がします。
その頃はまだ木下さんにスケジュールを引いてもらったり、タスクの抜け漏れを都度確認したりしてもらっていました。
今となっては、私のほうで主体的に進めています。
業務に対する慣れはもちろんありますが、長らく一緒に仕事をさせていただいているおかげで木下さんの思考回路が理解できたこと。
加えて自分の思考回路の中でも応用できるようになったことが任せていただけるようになった要因かと思っています。
-スピードと精度のせめぎ合い
山本:
特に「ごうぎんSkylandファンド」(下記PR TIMES参照)の設立は特にスピードが求められたと聞いています。
佐々木:
はい。投資事業有限責任組合によるファンドの設立の手順自体は把握していたのですが、リリースタイミングを考慮した結果、短い期間でファンドのセットアップを実施しました。
その中で、「どうすれば最短で進められるか」を常に考えていました。
そのプレッシャーは大きかったですね。
もちろん、相手があって確認しながら進めなければならない案件ですので、当時の先方ご担当者には色々と無理を申し上げましたが、
ご理解いただき、無事に期限に間に合わすことができたことは、今でもとても感謝しています。
木下さんとの連携と”少ない言葉”の仕事術
-「余白をもって伝える」
山本:
代表の木下さんとのコミュニケーションで意識していることはありますか?
佐々木:
できるだけ少ないやり取りで、必要なことが伝わるように意識しています。
というのも、代表の木下さんは多忙で時間も限られているので、本質的ではない部分までも1つひとつ丁寧に確認を取っていては、SV全体のスピードが落ちてしまうからです。
もちろん、最初からそれができたわけではありません。
何年かかけて木下さんとの最適な仕事の進め方をつかんでいった結果、今のやり方が成り立っていると思います。
SVの組織成長と、これから
-10人の才能ある個人が集まった組織へ
山本:
佐々木さんから見て入社した頃とSVはどんな風に変化しましたか。
佐々木:
2022年からここ3年間、SVにはフルタイムメンバーが10人ほど在籍していますが、今振り返ると2-3年前はその10人の強みを活かしきれていないような印象でした。
それが今は、それぞれが自分の持ち場を持ち、自分の役割を自覚して働いている。
ようやく組織として“機能する”フェーズに入ってきた実感があります。
-ルールの整備と成長痛
佐々木:
一方で、成長痛のようなものでルールの整備がまだ十分とは言えません。
ルールを作りすぎても、メンバーの自由度や裁量を狭めてしまう。
とはいえ、明文化されていないと統一感が出ない。
このバランスをどう取っていくかは、コーポレートとして大きな課題だと感じています。
SVに必要なコーポレート人材とは
-「誰も拾っていないボールを拾える人」
山本:
今後、SVに必要なコーポレート人材はどんな人だと思いますか?
佐々木:
「経験があるかどうか」よりも、「誰も拾っていないボールを自ら拾いにいけるか」が大事だと思っています。
スタートアップやVCにおけるコーポレートチームは、ルーティン業務が中心のようにも見えますが、実際には“初めてのこと”も頻発しています。
経験者だったとしても、必ずどこかで未経験の課題にぶつかります。
もちろん私が経験してきたことをチームのメンバーに教えることはできますが、それだけで新しいことには対応できません。
新しいことに対応するためには可能な限り自分で調べて、自分の頭で考え、ぼんやりとでもゴールをイメージできることが必要です。
最終的には「専門家に聞く」「周囲を巻き込む」などにいたることも多々ありますが、基本的には自分で「できる方法を探す」ということに、前向きな姿勢が大切だと考えています。
そして、このような姿勢で取り組める人が結果的にもっとも成長するし、会社への貢献度も高くなると思います。
最近ではAIの発達により様々な答えが簡単に導きやすくなっていますが、でも本当に自分の目の前で発生した困難に立ち向かうとき、実は答えは簡単には落ちていません。
答えを探し回るだけで心が折れそうになることがあります。
そういうことに臆することのないコーポレートチームに成長していきたいですね。
私の好きな本に、「ガルシアの手紙」という本があり、困難な課題に立ち向かう際の心構えを説いたもので、これをSVのメンバーにも薦めてるときがあります。
専門性を持ちながらも柔軟であること。そして自ら考え、動き、支えること。
SVの“挑戦”を下支えする役割は、決して目立つものではありません。
けれど地道な積み重ねがあってこそ、大胆な挑戦が現実のものとなっているのだと佐々木さんの話を聞いていて実感しました。
スタートアップの挑戦を裏で支えるのは、時に派手さのない、けれど確かな視点と行動力を持つ人であると感じたインタビューでした。


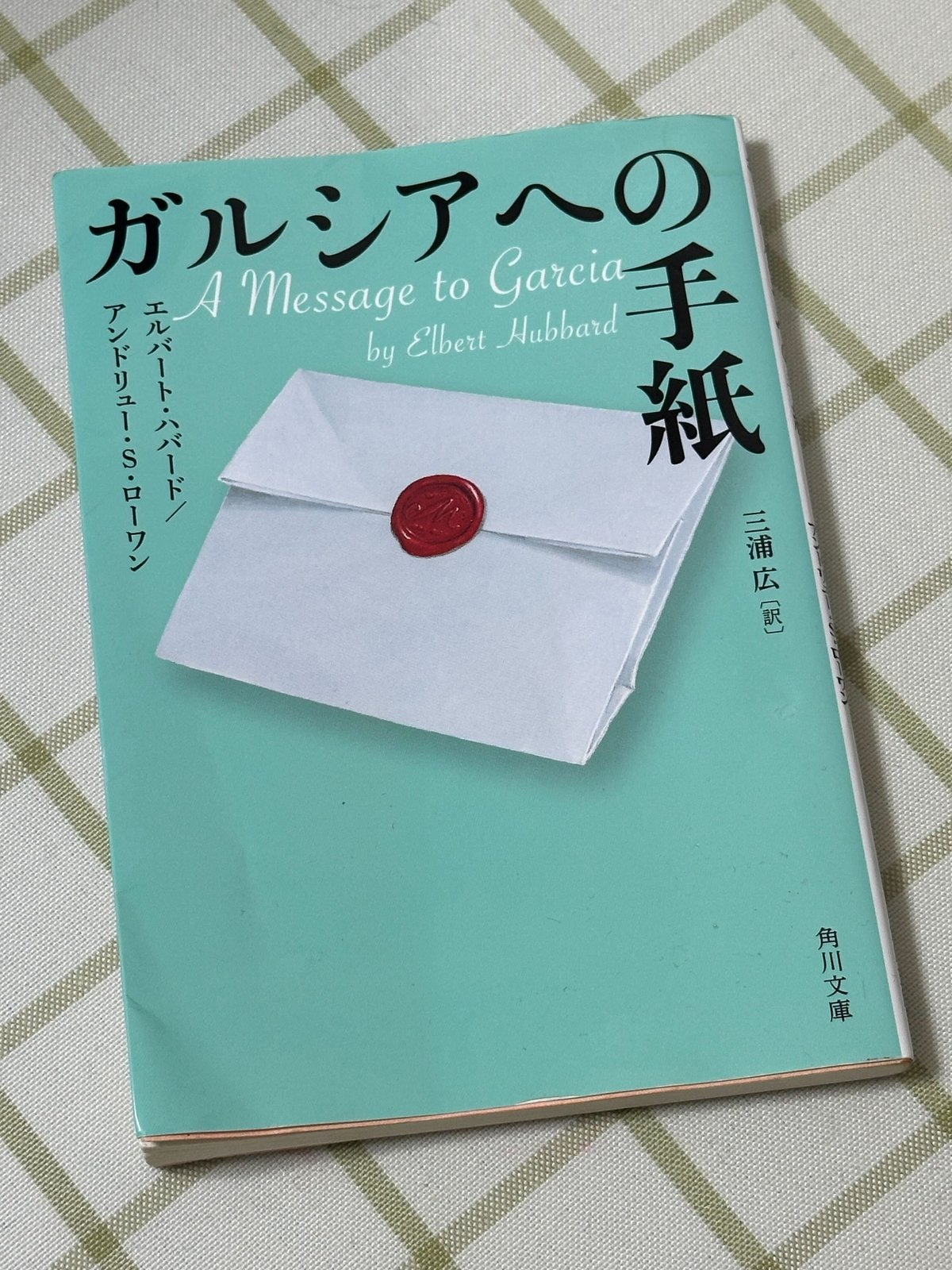

/assets/images/6816/original/366e6a41-275b-4cf3-931e-3b6b0fc57875.png?1392712899)
/assets/images/6816/original/366e6a41-275b-4cf3-931e-3b6b0fc57875.png?1392712899)

