クリエイティブなWeb制作の現場では、アイデアの方向性がひとつに定まらないことが多くあります。
そんな中、OVERAの現場で生まれたのが「読了感メソッド」という独自の視点です。このメソッドは、「サイトを閲覧した後にどんな感情が残るか」という“感想”を共通言語とすることで、チーム全体の視点を揃え、クリエイティブの質を劇的に向上させました。
この記事を書いた人
こんにちは!OVERA Webディレクターの白﨑明人です。
ロジックは成立しているはずだけど何かが足りてない、デザインに対し思ってることがあるけどうまく言語化できない、もっと出来るはずとモヤモヤしていた時にUNIT9がゲストの勉強会があり「読了感」を大事にしているということを聞き、それだ!と思って編み出したのが「読了感メソッド」です。
本記事が同じような悩みを持つ方々の参考になればと思っております。
読了感メソッドとは
一言で言うと、ブランドの課題とwebサイトで達成することをユーザー目線でシンプルにまとめた体型図です。
読了感メソッドでは、具体的なターゲットとブランドを伝える上でのコミュニケーションペインポイントで課題を整理し、どんな「読了感」を感じてもらえば課題解決の寄与できるかを目標にします。
さらに閲覧者が他社にブランドを紹介する際にどんな伝え方をするかの「伝言内容」を設定します。
ちなみに読了感は読後感と意味合いは一緒です。語呂が良いので、弊社では読了感と呼んでいます。
課題と目標を明確化することで、クライアント含め全員の意識統一を図ります。
例えば、そのアイディアや入れたい内容は、読了感に沿っているのか、読了感のためにもっと工夫が必要なのではないか、とブレない話し合いができます。
ただ正直に言うと、読了感メソッドのおかげでクリエイティブのアイディアが生まれるかと言うと違います。
あくまでも共通の指針を作ることが目的のフレームワークになります。
項目の解説
・ターゲット
ここで設定するのは属性やライフスタイルなどで設計するペルソナとは違い、よりWebサイトで狙うべきターゲットの情報を記載します。
Webサイトで認知〜CVまで行う場合もあれば、他のタッチポイントで認知され流入するケースなど、コミュニケーション戦略上のタッチポイントとしてのWebサイトの用途と目的は様々です。
今回のPJにおいて、webサイトはどの立ち位置なのか、その上でどんな人がターゲットになるのかを設定します。
・コミュニケーションペインポイント
上記で設定したターゲットがブランドに対して感じる課題において、コミュニケーションに関して不満に感じる点を課題とし列挙していきます。
例えば、、
・説明内容が複雑で結局どんなベネフィットがあるのかわからない。
・簡潔すぎて具体的な内容がわからない。
・他ブランドと比べて何が優れているのかピンとこない。
・抽象的すぎて、意味が理解できない。
など前段を抜きとして、1閲覧者として不満に感じる点を列挙していきます。
・読了感
読了感では、「サイトを閲覧した後にどんな感情が残るか」という“感想”を記載します。
比較している際は機能的にも情緒的にも色々考える。でも結局、これいいなと思うかどうか。その時の感想はごくシンプルになるはず。
なるべくシンプルな感想を記載することが重要です。
コミュニケーションペインポイントを解消し、設定した読了感に到達するための具体的な方法は構成やデザインなどになります。
ここで注意するべきは、「ブランドらしさ」を読了感に含めないことです。
個人的な意見でもありますが、「ブランドらしさ」って閲覧者の感想としてでないと思っています。
「ブランドらしさ」を通して、これ良いな、憧れるな、自分に合ってるな。
などが閲覧者の感想だと思っており、「ブランドらしさ」で逃げないことが重要だと思っています。
・伝言内容
友人知人におすすめする際の説明や、口コミサイトでどう紹介してくれたら良いなということを記載します。
読了感は個人の感想であって、抽象的な中に色々な要素が加わってる。
すげーの中にもかっこいいとか、すごくこれ使い勝手がいいとか、そういう含めてすげーってなると思うんですけど、人に紹介するとなった場合は、もっと具現化して良いと感じたことや、なぜあなたにこれがおすすめしてるか話します。
なので伝言内容を設定すると、より具現的なポイントが抽出できると考えました。
読了感メソッド誕生の背景
制作現場ではプロデューサー、デザイナー、エンジニア、それぞれが異なる軸で意見を交わし、議論がまとまらないことが多くありました。クライアント寄り、スケジュール優先、自分の美意識…。どれも間違ってはいないものの、同じゴールを共有できていない状態では、生産的な会話になりづらかったのです。
カスタマジャーニー・エクスペリエンスマップ・デザイン思考・バリュープロポジションキャンバス・リーンキャンバスなどなど、考えを統一させるために色々な手法を試してみました。
ただどうしても、全員でのフレームワークの理解度の必要や、アウトプットに直接寄与しないなど、制作コストが嵩むばかりで効果が実感できないなどの悩みがありました。
そうした中で私が提案したのが、「読了感」という視点でした。「このWebサイトを見終えたとき、ユーザーにどんな感情が残ってほしいか?」を設計の中心に据える。UXのフレームワークのようにロジカルすぎず、でも誰もが感覚的に共有できる。その“感想”という主観を、クリエイティブ全体の判断軸とすることで、議論の軸が一本化されていったのです。
メソッドがもたらした現場の変化
読了感を導入したことで、まずチーム内の対話が劇的に変わりました。以前は、個々の意見がぶつかり合い、なかなか収束しませんでした。しかし、「このデザインで、ユーザーは本当に“使ってみたい”と思うだろうか?」「この文章で“信頼感”は伝わるだろうか?」と、全員が“感想”という共通軸で考えることで、ブレがなくなり、議論も前向きになりました。
例えば「アイオニック」のWebサイト制作では、実際に担当したプロデューサーが電動歯ブラシ派から手磨き派に変わったほどのインパクトがありました。
このプロジェクトでは、ペインポイントとして「電動じゃないと汚れが落ちないのでは?」という不安を設定し、読了感には「手磨きでも、イオンの力でしっかり落ちるんだ」という安心感を掲げました。
構成やビジュアルでは、“イオンで歯垢を緩めて落とす”という独自性と、“毎日の手磨きがちょっと誇らしくなる感覚”を丁寧に設計。
結果、まるで自分が使っているかのような“疑似体験”が生まれ、読了感がユーザーの行動変容を後押しする好例となりました。
チームワークとクリエイティビティへの影響
このメソッドは、単にクリエイティブのクオリティを高めるだけでなく、チーム全体の心理的安全性にも寄与しました。以前は「誰の案が通るか」というコンペのような空気が漂い、ギスギスすることもありましたが、今では「この案は、あの読了感に近づけるにはどうしたらいいか?」という問いにみんなで取り組むようになりました。
結果、アイデアを否定するのではなく、ブラッシュアップの方向での議論が増え、建設的なミーティングが可能になっています。この空気がチームに良循環を生み、結果として作品のクオリティやクライアントからの信頼向上にもつながっていると感じています。
誰もが使える「共感の軸」として
読了感メソッドは、決してOVERAの専売特許ではありません。
むしろ、あらゆる制作現場にこそ導入していただきたいシンプルなメソッドです。論理や専門知識に偏らず、「人の感情」に軸を置くことで、クリエイティブのブレがなくなる。これはWebに限らず、広告、映像、グラフィックなど、さまざまな領域で活用できる考え方です。
主観を主観で終わらせず、それを“誰かの感想”として客観化する。読了感という軸があれば、デザインの方向性にも、チームの対話にも、確かな一体感が生まれるのです。
おわりに
「読了感メソッド」は、属人的だった感性の議論を、再現可能な“共感の仕組み”へと昇華させる方法論です。これは完成されたノウハウではなく、今も進化の途中にあります。今後はブランドコンセプトとの接続や、言語化の精度向上など、さらなる深化を目指していきたいと思っています。
本記事が、読了感という考え方に興味を持った方にとって、新たな視点のきっかけとなれば嬉しいです。
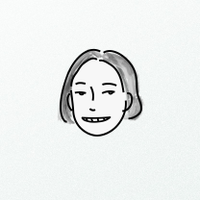
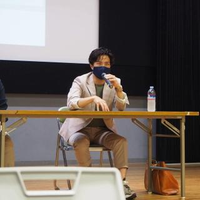


/assets/images/22021338/original/ba31f895-6ec4-46f7-97c4-799272c1ed93?1757469093)
/assets/images/22040322/original/ba31f895-6ec4-46f7-97c4-799272c1ed93?1757641407)

