目次
自己紹介:コーポレート部門のスペシャリストたち
キャリア:歩みの中で見つけた「問題解決」の共通点
業務改善と生成AI普及への挑戦:リアクションが原動力
業務改善の実践:組織の成長痛を乗り越える
未来への展望と学生へのメッセージ
本日は、会社の屋台骨を支えるコーポレート部門から、情報戦略テクノロジー(以下、IST)の業務改善とAI推進を担うS.Tさん、S.Mさんにお集まりいただきました。皆さんが働く上で感じる「もっとこうなったらいいのに」という課題。実はそれこそが、ISTが持つ「未開拓の宝」です。お二人の情熱に迫りたいと思います。
自己紹介:コーポレート部門のスペシャリストたち
白井: 本日はよろしくお願いいたします!まず、お二人の現在の担当領域について教えていただけますか?

S.Tさん: 私は情報システム課の担当者として、皆さんが働きやすい環境を整備することが主な業務です。具体的には、社員のアカウント管理やPC準備といった業務を日々担当しています。
S.Mさん: 私はエンゲージメント推進部に所属しており、総務法務、IR関連など、コーポレート業務に幅広く携わっています。
キャリア:歩みの中で見つけた「問題解決」の共通点
白井: では異なるバックグラウンドを持つお二人が、なぜAI推進や業務改善といった会社のIT戦略に関わることになったのでしょうか?

(左から:インタビュアー白井、S.Mさん、S.Tさん)
S.Mさん:私のこれまでのキャリアは、一見するとAI推進とは関係がないように見えるかもしれません。しかし振り返ってみると、どの職場でも「どうすればもっと効率よく、働きやすくできるか」という問題解決に向き合ってきました。店舗マネージャー時代には、日々のオペレーションを改善し続ける中で課題発見力を磨きました。語学サービス会社では、国際会議の運営や通訳者の手配を通じ、業務の属人化や非効率性に気づき、改善の必要性を強く実感しました。その後、コーポレート部門にキャリアチェンジしてからは、総務・人事・法務と幅広い業務を経験する中で、組織全体に関わる「仕組みづくり」への関心が高まりました。こうした歩みを経て、ISTに入社して間もなくAI推進チームが立ち上がりました。これまでに培った問題解決の視点を活かせば、これから進める業務改善と大きなシナジーを生み出せると感じ、チームに参画することを決めました。
S.Tさん: 私もこれまでのキャリアを振り返ると、以前の問い合わせ対応の仕事と本質的に変わらないと感じています。以前は、NECのパソコンの使い方センターや動画・画像編集ソフトの窓口などでサポート業務に携わっていました。現在のAI推進への関わりは、個人的な関心から人事部門役員である瀧本さんに「ぜひ参加させてください」と早期に申し出たことがきっかけです。以前から温めていたAI活用ガイドラインを提示したところ、瀧本さんにも是非と言っていただき、このAI推進チームに参加することになりました。

業務改善と生成AI普及への挑戦:リアクションが原動力
これまでの具体的な取り組み
白井: 今までに行った、ISTでの業務改善活動や、生成AI普及に向けた具体的な取り組み・普及活動についてお聞かせください。
S.Mさん: 私は社員がよりよいコミュニケーションや業務効率をあげられるよう、Slackの活用を推進しています。これまでは管理の側面からセキュリティ対策がしっかりとしていたが故にメンバーに解放されていない権限がいくつか見受けられました。権限が広くいきわたっている方が結果的に業務の効率化につながると確信した私は、Slackでのワークフローの提供など、様々な取り組みを進めました。この取り組みは現在でも続けていますが、セキュリティを担保しながらも、どこまで基準を緩和していくべきかという点は常に課題として感じています。

白井: ありがとうございます。おかげさまで色々なワークフローを作成して活用できるようになりました!その際はありがとうございました。S.Tさんはいかがですか?
S.Tさん: 私は自分の業務におけるAIの活用例を積極的にアウトプットし、社員に役立つ情報を共有するように心がけています。いきなりAIを正しく活用することを求めるのは難しい場合もあるだろうと考え、Googleスライドを活用して作ったガイドラインをSlackチャンネルで公開し、「まずはこれを見てから分からないことがあれば気軽に質問してください」といった運用もしています。こうした活動が、社員の皆さんが気軽に学習するきっかけになればと考えています。
白井: SlackチャンネルであるAI推進広場も日常的に活用されていますね。
S.Tさん: はい。AI推進をする立場として、社員がAI活用について気軽に質問や共有できる場所を作りました。日々寄せられる質問に対応することで、全社的なAIリテラシー向上に貢献できている実感があります。
白井: チャンネルは毎日様々な情報が流れていてAI情報のキャッチアップにすごく役立っています!
業務改善の実践:組織の成長痛を乗り越える
白井: ですが、それでもまだ未開拓な領域がISTには多いそうですね。
S.Mさん: はい。まだ未開拓の領域が多く、「宝の山」だと感じています。会社は「未完成」なのではなく、「未来に向かって新しい形を作っている」段階なので、変化を恐れずに新しい行動を起こすことの面白さがあります。

(業務改善ミーティングの様子)
S.Tさん: 私は少し具体的な話になりますが、会社の規模拡大に伴い、PC準備のマンパワー不足が深刻になってきています。これまでのやり方では対応しきれない課題が増えており、業務プロセスそのものの見直しも含めて解決策を模索しています。これまで何度か様々な手法を試したこともありますが、システムの相性や導入に費やす時間の問題でどうしても第二領域的に見られやすく、なかなか進んでいない側面もまだあります。
白井: そうした課題は、会社が急成長しているからこそ直面するものなのかもしれませんね。
S.Mさん: そうですね。会社が新しい形を作っている状態だからこそ、今までになかった課題も次々と出てきます。でも、それって「宝」でもあるんですが「掃除ができる落ち葉」がたくさん落ちているようなものでもあると思います。
S.Tさん: 本当にそう思います。入社した当初は落ちている落ち葉の量がまさか増えていくとは思っていませんでしたが(笑)今はその落ち葉が増えていることをむしろ楽しんでいます。落ち葉の種類が変わったり、数が増えたりと、日々変化があるので、それをどう解決していくか、常に前向きに取り組んでいます。

S.Mさん: まさに、会社が成長している過程だからこそ、自分がやりたいことがあればまず行動してみることが重要になってきます。これからプライム市場に向かって行く過程で、キャリアを切り開いていけるという醍醐味があると感じます。
S.Tさん: 私もISTは、手を挙げれば何でもでき、キャリアを主体的に考え、敷かれたレールに乗るのではなく、なりたい自分になれる会社だと感じています。
S.Mさん:業務改善の手法も様々です。全社を一度に動かすことが難しい場合や効果検証をしたい場合は、スモールステップでチーム内から試していき、徐々に広げていく形を取ることもあります。ISTは社員のみなさんのキャッチアップ力が高いので、このような手法も効果や結果が分かりやすく面白いと感じています。
S.Tさん:それに加えて、これまでの常識を変化させることに対して役員陣の理解があることや、まずは挑戦してみたらよいと言っていただけるところ、フラットに提案できる環境を作ってくださるところもAI推進や業務改善をしやすくしているポイントだと思います。

未来への展望と学生へのメッセージ
白井: 今後の生成AI・業務改善の取り組みを通じて、ISTをどのような組織にしていきたいですか?
S.Mさん: 組織の中に、【改善や改革は当たり前】という文化を根付かせ、常に進化し続けるチームにしていきたいです。個々の強みを尊重しあい、支えながら成長できる組織って素敵ですよね。
S.Tさん: 皆が平等にAIを使いこなし、人間だからこそできる「自分の考え」や「やりたいこと」に積極的に取り組める組織を目指したいです。そして、それを発信するだけではなく行動していくことはもちろん、他の社員や関わる相手が何を求めているのかを読み取って、より組織に貢献できる状態を目指したいです。
白井: 最後に、ITや効率化、問題解決に興味がある学生へメッセージをお願いします。
S.Mさん: ISTのコーポレート部門は、会社全体の生産性向上という大きな目標を掲げ、日々挑戦を続けています。この挑戦に興味を持った方、未整備な環境で自ら課題を見つけて解決することにやりがいを感じる方には、ぜひISTに来てほしいです。
S.Tさん: やる気があれば何でもでき、自分の足跡を残せる場所はたくさんあります。ISTに来たい人は、このインタビューを見つけてくれた今がチャンスだと思います。

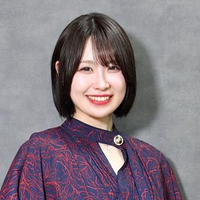

/assets/images/14287758/original/41aa6faf-6f8c-427c-9316-d03b39f542f1?1692955864)
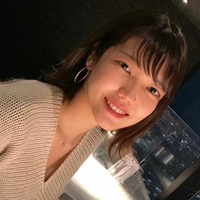
/assets/images/14287758/original/41aa6faf-6f8c-427c-9316-d03b39f542f1?1692955864)

