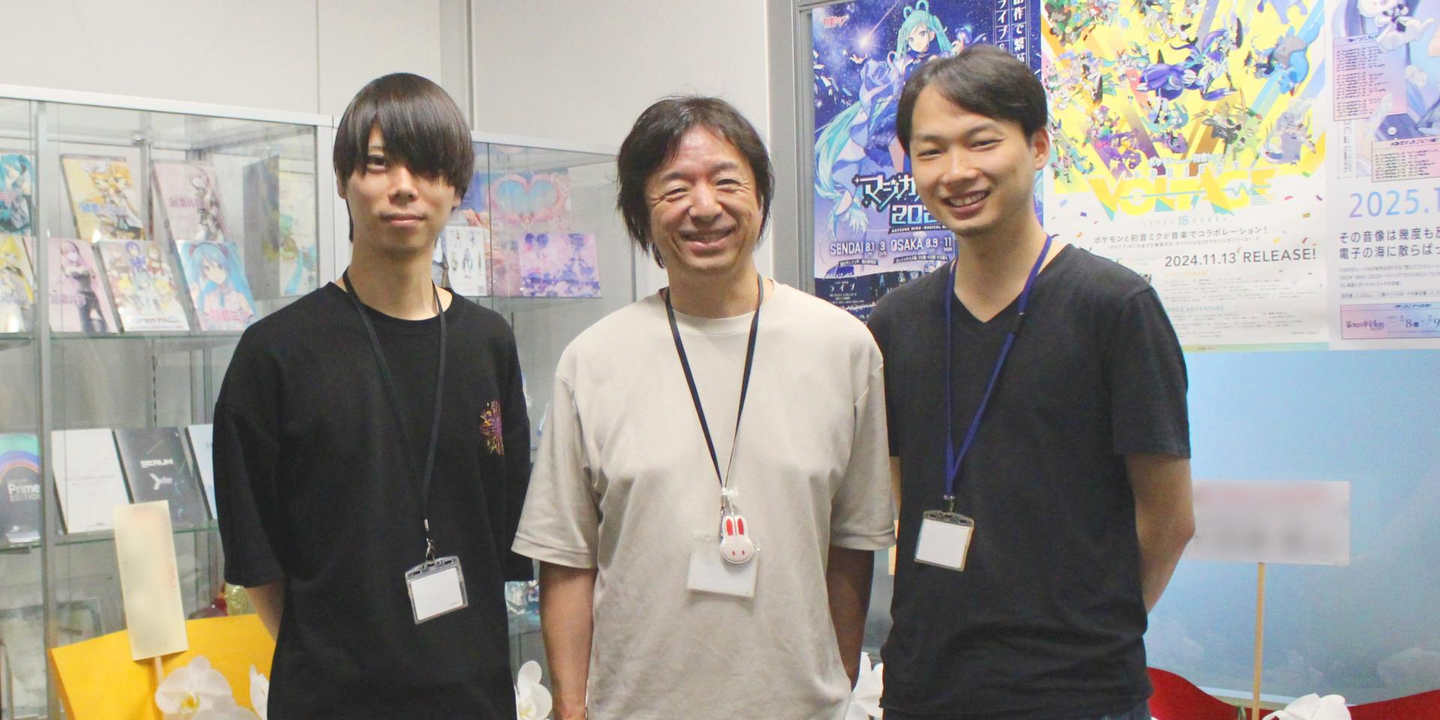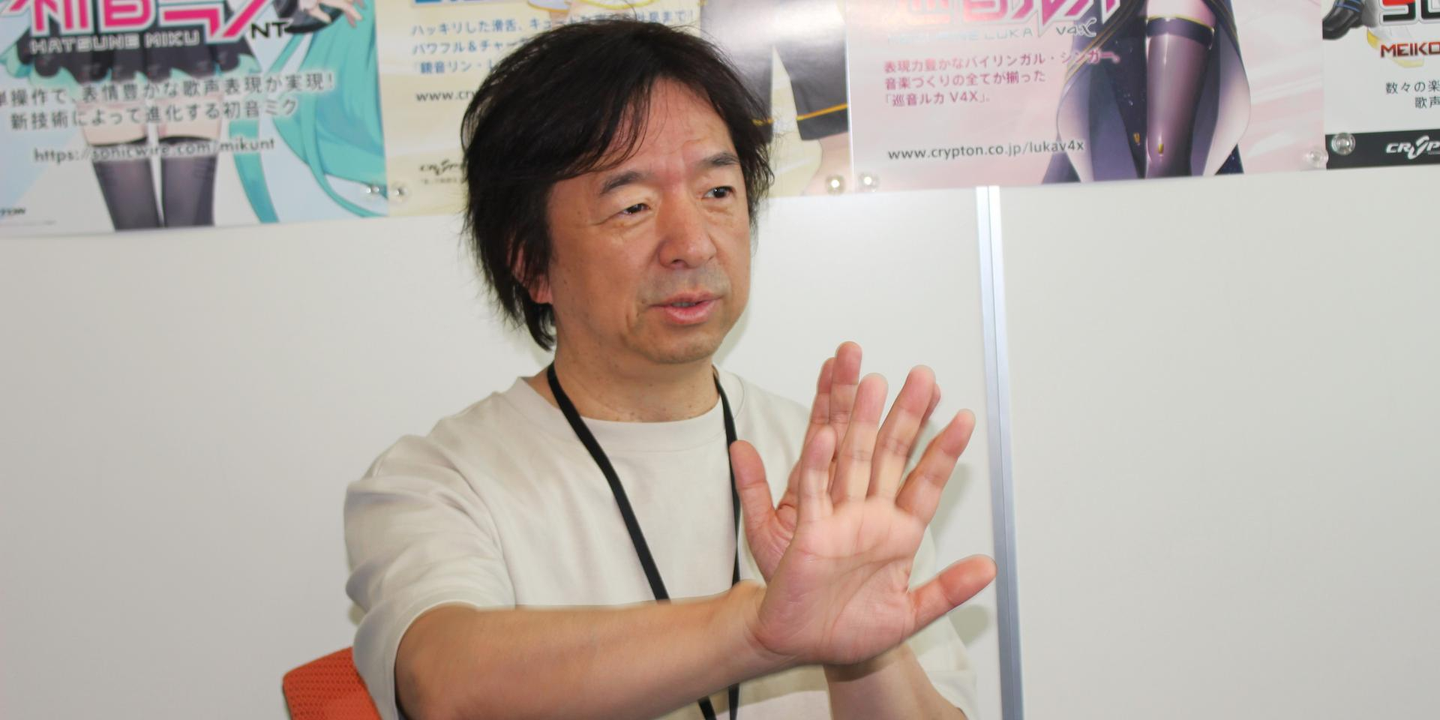【30th特別連載企画 Episode 1】クリプトンのこれまで | 事業を知る
クリプトン・フューチャー・メディアは、本日2025年7月21日をもって、設立30周年を迎えました!これを記念して、当社の代表取締役である伊藤の著書『創作のミライ 「初音ミク」が北海道から生まれた...
https://www.wantedly.com/companies/crypton/post_articles/992716
本日は、当社の代表取締役である伊藤が、クリプトン・フューチャー・メディアが歩んできた30年の軌跡を社員と共に振り返る特別連載企画の“Episode 4”をお届けいたします。
この連載企画は、クリプトンの設立30周年を記念して発売した伊藤の著書『創作のミライ 「初音ミク」が北海道から生まれたわけ』(発行所:中央公論新社)に詰め込み切れなかったお話を中心に、あらためて当社についてご紹介できれば・・・という想いから生まれました。
過去記事をまだご覧になっていない方は、ぜひこちらもお楽しみください。
Episode 4 のテーマは「創作活動のサポート」です。今回は、SONICWIRE・音楽事業チームのサブマネージャーとして創作活動のサポートに繋がる事業にも関わっている林と藤原に参加してもらい、伊藤と共に当社のクリエイターサポート事業について紹介いたします。
写真は左から順に、藤原・伊藤・林
伊藤博之:クリプトン・フューチャー・メディア株式会社代表取締役。北海道大学に勤務の後、1995年7月札幌市内にてクリプトン・フューチャー・メディア株式会社を設立。DTMソフトウェア、音楽配信アグリゲーター、3DCG技術など、音を発想源としたサービス構築・技術開発を日々進めている。2013年に藍綬褒章を受章。
林有希寛:2018年入社。SONICWIRE・音楽事業チームのサブマネージャー。音の素材を取り扱うオンラインストア「SONICWIRE」の運営のほか、「SONOCA」、全社におけるWEBマーケティングやSNS施策などを推進している。
藤原隆己:2019年入社。SONICWIRE・音楽事業チームのサブマネージャー。「KARENT」や「ROUTER.FM」などの音楽サービスを運営。クリプトンが主体となって関わっているライブのセットリストや演出なども担当している。
―『創作のミライ』の中でも触れられていますが、コンピュータが普及して、一般の方でもお気軽にDAWソフトウェア(パソコンで音楽制作するためのソフトウェア)を入手できるようになったことで、昔に比べて音楽制作の敷居は格段に下がりましたよね。
伊藤:そうですね。私がDTM(パソコンを使用した音楽制作)を始めたのは社会人になってからですが、当時のDTMはまだ一般的な趣味とは言い難いもので、値段もそれなりにしました。それが今では、数万円で自宅にレコーディングスタジオのような環境を構築することができます。レコーディングスタジオを所有しているレコード会社に所属しなくとも、個人の力で自分の音楽を創り上げ、世に広めるチャンスがある時代になりました。
―数万円どころか、無料のものもありますよね?私も趣味でDTMを楽しんでいますが、初めてのDAWはフリーソフトで、DTMがどういうものなのかを実際に体験してみてから有料のものを購入しました。
伊藤:確かに無料のソフトウェアも色々ありますね。DTMのよいところは、まさにその自由度にあると思います。誰でも簡単に始めることができて、どれだけ時間やお金をかけるかは個人の自由で構わない。辛くなったら途中で辞めてもいい。自分のペースで好きな音楽を好きなだけつくれるのが楽しいですよね。
藤原:DTMは沼のようなものだと思います。無料のDAWでも十分楽しめるけど、実際に創り始めると「もっと」という欲が生まれてくる。音の種類だったり、理想の操作性だったり・・・そうした色々なものにこだわり始めると、もう底なし沼に落ちていくも同然ではないかと。
林:そういうあらゆるニーズに応えられるよう、当社が運営しているデジタルクリエイター向けのダウンロードストア「SONICWIRE(ソニックワイヤ)」では無料でダウンロード可能な素材からプロご用達の本格的なDAWまで、多種多様な「音」を取り揃えています!
―うまく宣伝を入れ込みましたね(笑)ちなみに「SONICWIRE」では音の素材を取り扱うだけでなく、音楽クリエイター向けのTIPS動画や記事も色々と発信していますよね?
林:はい、その通りです!「SONICWIRE」は音の素材を売るダウンロードストアではあるのですが、まずはDTMの楽しさを知っていただきたいので、無料で始められる楽曲制作の方法をまとめた記事なども公開しています。この記事を読んでDTMに興味を持った方がいらっしゃれば、ぜひ体験していただきたいですね。(>>無料ではじめる!サンプルパックで楽曲制作)
伊藤:ただ素材を売っているだけでは、ユーザーの大幅な増加は見込めません。「まだDTMをしたことがない」というような方にDTMの楽しさを知っていただいてこそ、クリエイターの母数が増えて、当社が取り扱う音の素材等を使用してくださるユーザーの増加にも繋がると考えています。だからこそ、直接の利益を上げられるものではなくとも、初心者向けのTIPS記事や無料講座の動画を発信することが重要と認識しているんです。これは『創作のミライ』の第5章でもお話した“収穫型”の考え方ですね。
―当社ではコンテスト等で作品を公募することがありますよね。どういう意図で開催しているのか、伊藤社長からお話いただけますでしょうか?
伊藤:基本的には、クリエイターが作品をつくるきっかけや、クリエイターの作品がより多くの方に届く機会の創出を目的として開催しています。インターネット上で作品を公開すれば世界中の方に見ていただける可能性がある一方、公開される作品数も膨大なため、残念ながら埋もれて気付いてもらえないこともあり得ます。だから、こうした取り組みを通して、クリエイターの作品を世に知ってもらえる機会を増やしていくことが、私たちにできることなのではないかと思うんです。
ちなみに当社が運営しているコンテンツ投稿サイト「piapro(ピアプロ)」上では、企業等とのコラボレーションで作品を公募する「ピアプロ公式コラボ」という企画を不定期で実施しているのですが、現在も3つのコラボが募集中です。採用されると季刊誌にインタビューが掲載される楽曲公募だったり、スケールフィギュア化するイラストの募集だったり、色々なコラボがあるので音楽制作やイラスト制作に興味がある方はぜひご参加ください!(>>「ピアプロ公式コラボ」募集中のコラボ)
―「ピアプロ公式コラボ」と言えば、イベント『初音ミク「マジカルミライ」』のライブで実際に演奏する楽曲を募集するコンテストを、2017年から毎年開催していますよね。
藤原:はい。それに、ちょうど9月8日(月)から『初音ミク「マジカルミライ 2026」楽曲コンテスト』の募集を始めたところです!私は2022年から審査に関わっていますが、コンテストの運営を担当しているユニットのみなさんと一緒に全ての応募曲を聴いて、それぞれ意見を出し合いながら受賞作品を選定しています。応募数も応募作品全体のクオリティーも年々上がっていて、毎年コンテストを始める時期になると「今年はどんな作品が届くのだろう?」とワクワクします。
林:テーマやジャンルの指定がない楽曲コンテスト、というのが自由度高くていいですよね。条件は4分30秒以内の当社のバーチャルシンガーが歌唱するオリジナル楽曲、というだけでしょう?
藤原:投稿形式などは色々決まりがありますが、音楽自体の条件はざっくり言うとその通りです。コンテストの募集内容自体は需要に応じて少しずつ変えていて、2024年まではピアプロキャラクターズ(『初音ミク』『鏡音リン』『鏡音レン』『巡音ルカ』『MEIKO』『KAITO』の総称)いずれかの単独歌唱楽曲を募集していたのですが、2025年から複数バーチャルシンガーによる歌唱楽曲の応募をOKとしました。
伊藤:ちなみに、ピアプロキャラクターズ全員の楽曲を対象としたのは2018年からで、2017年に初めてコンテストを実施した際は、初音ミクの単独歌唱楽曲のみを対象としていました。より多くの方が参加しやすい魅力的なコンテストとなるよう、改善できる部分は改善しながら開催を続けています。
「ピアプロ公式コラボ」というわけではないのですが、近年ではこの楽曲コンテストの受賞曲を課題曲とし、リリックアプリを制作するプログラミング・コンテストも開催していますよ。この「マジカルミライ」におけるプログラミング・コンテストを始めた当初は、イベントのテーマソングを課題曲としていました。けれど「これは楽曲コンテストの準グランプリ曲に注目していただける良い機会なのでは?」と思い至り、ここ数年は楽曲コンテストの受賞曲を意図的に課題としています。
―「piapro(ピアプロ)」で行う公募はバーチャルシンガーに関連するものばかりですが、当社はバーチャルシンガーを使用しない楽曲のコンテストも実施していますよね。
林:もちろんです!「SONICWIRE」では様々な音楽クリエイターに向けたコンテストを、2022年より不定期で開催しています。「SONICWIRE CONTEST」、通称「ソニコン」です。2022年の初開催以来、「メロディーラインが入っている5分以内の楽曲」や「3分以内の4つ打ちのインスト楽曲」などのテーマで、様々な楽曲を募集してきました。
藤原:「ピアプロ公式コラボ」はあくまで“コラボレーション”なので、リワードの内容が“採用する”とか“商品化する”というものになりがちなんですけど、「ソニコン」の方は音の商社であるクリプトンのコンテストらしい豪華な審査員陣や、受賞者が自分の創作活動に還元できる副賞が魅力的ですよね。
林:「ソニコン」はコンテストなので、明確な審査基準をあらかじめ用意しています。たとえば「歌モノ」楽曲を募集した時の審査基準は「メロディー」「コード」「展開」「サウンド」「楽曲アイデア」の5項目でした。その審査基準に基づいて審査員が選考を進めるわけですが、その審査員の方々というのが実際に音楽業界で活躍されている方々なので、作り手のシビアな目線で楽曲が評価されます。選考の進んだ応募者には各審査員からの講評をお送りしており、音楽を生業にしたいと考えているクリエイターにとっては貴重な機会に感じられると思います。
私たちも審査に関わるのですが、普段お客様でもあるクリエイターの皆様の楽曲を聴ける貴重な機会だったりします。皆さんが苦労して作ってくれた楽曲なので一曲一曲想いを汲み取るように聴いていくわけですが、たまに感情移入してしまうこともありますね(笑)プロ級の作品もあれば、技術的にはまだ拙いかもしれないけど伝えたいことややりたいことはヒシヒシと伝わってきたり。審査結果として期待に応えられるかは別として、心から応援したいなと感じながら拝聴しています。
伊藤:ひとくちに「音楽クリエイター」と言っても、趣味の範囲で創作を楽しみたい方や、音楽を生業にしたいと考えているような方など、色々な方がいると思います。だからこそ各サービスの需要に応じた公募企画を実施することで、様々なクリエイターに作品づくりのきっかけや、作品を世に送り出す機会を創出して提供したいと考えています。
―趣味の範囲で音楽を始めた人であっても、今は自分で収益化ができる時代になりました。当社では配信代行サービスの運営も行っていますよね。
伊藤:「KARENT(カレント)」と「ROUTER.FM」のことですね。「KARENT」は2008年12月に開始したボーカロイド音楽専門レーベルで、「ROUTER.FM」はミュージシャンが世界に向けて自分の音楽を売るサービスとして2010年3月に提供を開始しました。どちらも、世界の主要ストリーミングサービスやダウンロードストア等を通して、190以上の国や地域に音源を供給しています。近年では年々需要が高まっているTikTokやInstagramといったSNSにも供給しています。
藤原:「KARENT」については配信代行サービスである以前に音楽レーベルとしての側面があるため招待制で運営していますが、「ROUTER.FM」に関してはどなたでも登録していただけます。当社は各配信ストアの直接契約事業者なので手数料も少なく、高い収益還元が可能です。
また、当社が運営する「ROUTER.FM」の特徴としては、歌声合成ソフトウェアのキャラクター利用がOKである点が挙げられると思います。「piapro(ピアプロ)」と同じように、当社が許諾を得ている他社キャラクターの名称やビジュアルの使用が認められているため、いわゆる“ボカロP”として活躍したいクリエイターさんにはぜひ活用していただきたいです。もちろん、歌声合成ソフトウェアの使用が必須のサービスではないので、音楽活動をされている色々な方にオススメのサービスとなります。
伊藤:「KARENT」については藤原くんが言ったように音楽レーベルとしての側面があるので、ただ配信を代行するだけではなくて、クリエイターの発掘や育成、プロデュースに繋がるようなこともしています。KARENT登録クリエイター限定のセミナー開催や、KARENT登録クリエイターを起用したCDの発売といったことです。
それに、イベント会場でKARENT登録クリエイターによる音楽即売イベントも開催しています。先日開催した『初音ミク「マジカルミライ 2025」』でも、クリエイターが自分のファンと直接交流できる場を設ける意図で、音楽即売イベント「KARENT Presents クリエイターズマーケット」を実施しました。
―音楽即売イベントと言えば一昔前はCDが主流でしたが、今はオンラインでの試聴がメインでCDプレーヤーを持っていないという方も珍しくないので、当社ではスマホ用の音楽カードを開発していますよね。
林:そうなんです。「SONOCA(ソノカ)」はカード型の音楽メディアで、カードに記載されたユニークなQRコードを使用することで、音楽プレーヤーアプリの「SONOCA Player」からスマートフォンに直接楽曲をダウンロードすることができます。カード型ということでモノとしてのコレクション性と、スマートフォンさえあればすぐに聴けるという利便性をかけ合わせたサービスとなっています。
クリエイターズマーケットに出展されているクリエイターさんの中にも、SONOCAを活用してくださる方がいて嬉しかったですね。
伊藤:CDプレーヤーを持たない層が増加していることを受け、自分の音楽を形にして売りたいと考えているクリエイターのために何かできることはないかと考えた結果が、このSONOCAの開発でした。クリエイターに必要なものをクリエイトするという、当社のメタクリエイターらしさがよくわかるサービスと言えるかもしれません。
―他にも、当社は音楽出版やYouTube収益化サポートなども行っていますよね。実際に活用されているクリエイターさん以外には、あまり知られていない気がするのですが・・・。
伊藤:確かに頻繁に宣伝しているわけではないので、あまり知られていないかもしれませんね。当社では自作曲の収益化に悩んでいるクリエイターの力になるべく、音楽出版社としての支援活動も行っています。どういうことかと言いますと、当社が音楽出版社として、依頼してくれたクリエイターさんの音楽作品の「著作権」を著作権管理団体(JASRAC , NexTone)に管理委託しています。そうすることで、カラオケや音楽配信等の様々な楽曲利用において発生する著作権使用料を回収し、クリエイターさんに還元することができるんです。
とはいえ、当社のメインは音楽出版業ではないので、一応条件は設けさせていただいています。業務用通信カラオケにおいて1曲でも楽曲が利用されている方、もしくは、当社の音楽関連サービスに1曲でも楽曲を登録されている方であれば、当社の音楽出版を利用することが可能です。
藤原:当社が直接のお手伝いができない場合もあると思いますが、どういう収益化があるのかについては、当社のクリエイター収益化サポート事業のページを見ていただくとわかりやすいと思います。自分の音楽を収益化したい方は、ぜひ一度ご覧ください。
―それでは最後に、Episode 4の伊藤社長の対談相手としてご協力いただいた林さん、藤原さんにお聞きします。入社してから今までの中で一番印象に残っている「創る」にまつわるエピソードを教えてください!
林:自分自身は作曲やイラスト・動画制作といった創作活動をしないタイプです。ただ、色々な事に興味をもって知識を付けるのが好きで、前職ではあまり縁の無かったシステムにまつわる知識をつけることで、サービスを創るという貴重な経験をさせてもらっていると思っています。もちろん、伊藤社長を初め私が入社する前から沢山の人が携わっているサービスではありますが、新しい機能を設計したり、既存の仕組みを改善したり、社内のワークフローを最適化するなど、お客様の目に見えない部分も含めて様々な取り組みを行っています。
他の皆さんと比べて地味にはなってしまいますが、特にインボイス制度への対応は痺れましたね。国税庁のページを何度も読み返しながら、カートの計算式や領収書のフォーマットを見直したり、それを上手くまとめてシステムチームに実装を依頼するなど、かなりバタバタした思い出があります。経理担当にも助言や確認を求めますが、最終的にお客様の使いやすいサービスとなるように、可能な限り自分も知識を付けながら最適な形を模索していくプロセスに非常にやりがいを感じています。
また、余談ですが元々私は音楽制作のミックスという、作曲の後の工程を専門に学んでいました。元々作曲をしている人が入社することも多いのですが、そんなメンバーにプライベートでミックスを教える事もあります。入社時よりも見違えるようにミックスの腕を上げたメンバーもおり、身近な人の「創る」を応援できているのも、音楽という共通項で繋がっている会社ならではなのかなと思います。
藤原:私が一番印象に残っているのは、今年開催された「初音ミク JAPAN LIVE TOUR 2025 ~BLOOMING~」ですね。前身である「初音ミク JAPAN TOUR 2023 ~THUNDERBOLT~」の開催後、公演で回った各地のファンの方やクリエイターさんから、ライブを見てイラストを描きたいと思ったとか、昔やめてしまった作曲をもう一度始めたいと思ったとか、素敵な感想がたくさん寄せられていて。見てくださったみなさまの創作意欲を刺激し、たくさんの「ツクル」を創ったイベントだったんだなと感動しました。BLOOMINGではセットリストの作成を担当させていただいたのですが、このライブがまた新たな「創る」を作るのだと思うと、心臓の高鳴りが押さえられませんでしたね。気がつけば自然と、初音ミクらを開花させた人々やこれから芽吹く創作の数々への感謝とエールを込めたセットリストになっていました。このイベントも、多くの方が創作を始めたいと思えるきっかけになったようですし、みなさまに楽しんでいただけて本当に嬉しかったです。
もちろん入社前から続けてきた、いわゆる楽曲などを「創る」ことも継続していまして、例えば歌声合成ソフトウェアのアップデートの際に発表されるデモフレーズの一部などを制作させていただいています。デモを聴いた方が製品を使いたい、作品を創りたいと思ってもらえるようにという一心で制作していますので、これも「ツクルを創る」という営みの一部なのではないかなと。
セミナーやインタビューでも一貫して主張しているのですが、私は"次のクリエイターが生まれてくること”を一番楽しみにしていますので、今後もあらゆる面で皆様の「創る」を応援できたらと思っています!
―みなさん、ありがとうございました!
Episode 5 は、地域振興事業やシステム関連の担当者を交えたトークをお届け予定です。どうぞお楽しみに!