トップコンサルタントの頭の中を覗く「こうしてビジネスを成功に導く」: Beyonders Story Vol.7
こんにちは!クリエイティブホープの亀井です。
今回で第7回目を迎えた「Beyonders Story」ですが、本日は弊社のトップコンサルタントである取締役の藤井とGrowth Hack事業部で副事業部長を務める白石の2名に話を聞きました。インタビュアーは、弊社取締役の大里が務めています。
本対談では、ビジネスコンサルタントとして豊富なご経験をお持ちのお二人に、コンサルタントとしての心構えや課題に対する向き合い方、クライアントとの関係構築や難易度が高いプロジェクトへの取り組み方について余すところなくお話いただきました。
また、お二人には自社新規ソリューションの開発を行っているというもう一つの共通点があります。これまで公開した中で最もボリュームがある記事となっておりますが、「自社サービスの開発に関わりたい」「ビジネスコンサルトとして力をつけたい」など気になる方は、ぜひ最後まで読み進めてみてください!
※タイトルに関して:クリエイティブホープではいわゆる「グレード」といわれることが多い評価等級を「Beyonder」という造語で定義しています。結果ももちろん大事ですが、とにかく「Beyond」している人へ、どんどん難易度高いお仕事を任せていきます。そんなクリエイティブホープに集う「Beyonder」達へのインタビューです!
藤井 廣男(取締役兼CMO)

2010年より(株)クリエイティブホープに参画。企業のマーケティングや経営のコンサルティングや新規事業開発支援に数多く従事。現在は、取締役兼CMOとしての活動に加えて、自社プロダクトの立上げやビジネスオーナーとしても活動中。他にも、企業の経営顧問や起業家・起業家候補のメンタリング活動やアクセラレーションプログラムの運営支援に従事。
白石 達也(Growth Hack事業部)

大手/中小問わず300サイトを超える企業のリード/CV獲得に向けたWebサイトディレクションを実施。その後、前職では運用型Web広告の運用、アカウントプランニング、Webマーケティングコンサルタントを行う。現職ではデジタルマーケティングのコンサルティングやツール導入支援、組織開発、インハウス支援などを行う。
大里
――お二人の自己紹介と普段のお仕事や役割について教えてください。
藤井
クリエイティブホープで取締役をしています。藤井です。前職を含めコンサルタントとしては15年ほどお仕事をさせていただいています。現在は、「ビジネスコンサルタント」という立場でお客様と接するようにしていて、実は最近自分自身のことをデジマケコンサルタントとか、マーケティングコンサルタントとは表現しないようにしています。
というのが、各企業さんの課題解決する方向性が必ずしもマーケティングの施策に集約されるわけではないからと感じているからです。システムの話からマーケティング施策、セールスのノウハウ、組織・チームの運営方法、あるいは企業文化を作るなど、アプローチする対象の幅が出てきてるからこそ、企業が持ってる課題の解決に寄り添えるように心掛けております。
大里
そうなんですね。ありがとうございます。ちなみデジマケ=デジタルマーケティングということって、お客様や一般的に聞いてピンと来るものですか?
藤井
最近だとどうなんですかね。例えば、ビジネスマッチングをやってると営業DXとか、DXって言葉を目にして「自社も何かやらなきゃいけない!」というイメージを持ってらっしゃる方とはたくさんお会いしますね。中にはDX(デラックス)と言ってたお客様がいらっしゃいましたが(笑)
営業活動や販促を変えていかなくてはいけないというような思いでDXという言葉で捉えて、その延長線上にデジタルマーケティングとかデジタルセールスがあるというように感じていらっしゃるのではないかと気がしますね。

大里
そうですよね。となると、確かにデジマケコンサルタントというサービス提供の仕方だけでは物足りない部分もでてきているというところはあるかもしれないですね。
では、白石さんも簡単に自己紹介お願いします。
白石
私もクリエイティブホープでコンサルタントをやってます。ただ、デジタルマーケティングのコンサルタントっていう意味で言うと、まだ3年ぐらいしかやってないんですよね。それまではどちらかというと、ウェブマーケティングのコンサルタントをしていました。
現在は、リードジェネレーションの領域や、リードナーチャリングの領域におけるコミュニケーション設計、いわゆるデマンドジェネレーションの支援を行っています。他には、デマンドジェネレーションを実施するための組織・体制つくりのサポートや顧客データのマネジメントについてもご提案させていただく機会が多いですね。
社内での活動でいうと、新しい自社商材作りや困ったことがあった時のメンター役として相談を受けたり、新人研修で講師をしたり、新規営業に入ったりなど何でも屋さんみたいな感じで動いていますね(笑)
大里
ありがとうございます。加えて、白石さんはGrowth Hack事業部で副事業部長という立場で支えてくれていますが、簡単に何名くらいの組織規模で、どのような人が所属しているのかなど紹介していただいてもいいですか?
白石
Growth Hack事業部は、現在およそ30人ぐらいの組織でコンサルティング職の人と、クリエイティブ職の人、エンジニア職の大体3つぐらいの領域で活躍している人がいます。比重としては、やはりコンサルティング職の人が多く、クリエイティブ職ではディレクターとして案件のマネジメント・運用を任せられる人がいます。エンジニア職は、アプリとシステムとの連携においてのアプリ開発などを担当している人がいる組織構成となっております。

常に、一歩二歩先を見据えた魅力的な提案ができる組織
大里
――クリエイティブホープはどのようなお客様にどういった価値提供をしている組織でしょうか?
藤井
P社さんという某SaaS系サービス様を長年ご支援しているのでそのお話をしますね。P社さんとお取引をするきっかけは、とあるCMS(コンテンツ・マネジメント・システム)ツールを販売するパートナーさんからのご紹介で、そのパートナー企業さんが提供しているCMSをP社さんに導入してもらいたいから手伝ってもらえないかという相談があったことでした。
当時、P社さんのご担当者はSさんという方で、Sさんは元々ITには精通しているけど、デジタルマーケティングはあまり詳しくない方でして、「最近とあるMA(マーケティング・オートメーション)ツールを導入したんだけど、ちょっと使い方がよく分からないし、ウェブサイトも古いのでそろそろリニューアルしたい」というようなご相談をいただきました。
初めは、こういう方針でやっていきましょうというサイト全体の方針設計や、先方の商材・マーケティング領域でランディングページとWeb広告を改善すればこれぐらいの事業インパクトがありますという数字を提示して、こちらのABCプランでAまで実施できれば何億円の影響があります、やりますか、やりませんかという提案をしました。
で、それを見たSさんが「クリエイティブホープはすごく真面目に取り組んでくださる会社なんだな」と感じてくださって、決裁まではすごく時間がかかったんですが、当時そこまでの提案を出してくれた会社がいなかったようで半年ぐらいかけてようやくプロジェクトを始められたということがありました。
プロジェクト開始後は、導入していたMAツールの具体的な活用方法を細かくご提案していました。また、しばらくするとGoogle Analyticsにも興味を持ち始めたので、ウェブサイトやコンテンツマーケティングの方向性を決めて、ブログメディアを立ち上げたり、ウェブサイトのトップページもリニューアルかけたりしましたね。
彼らの一番初めのKPIはウェブサイトのPVで、PVが増えたかどうかがコンテンツマーケティングのプロジェクトを進めるために社内決裁において最も重要な指標だったので、まずはPVが上がるためにはまず何から始めた方がいいかっていう観点で、ウェブサイトのトップのリニューアルをして、結果PVをすごく上げることができたので無事にプロジェクト全体をスタートすることができましたね。

大里
当時は藤井さんがメインで案件を担当されていたんですか?
藤井
そうですね。初期は私と私のアシスタントが案件に携わっていて、アシスタントが自立できるようにする教育のためのプロジェクトとしても私が入っていましたね。
1番初めに行ったのは、先方の取締役の方や該当部署への初期ヒアリングですね。既存システムが現状どのように動いていて、他の関連業務はどのように行われていてというようなヒアリングには私も参加しました。現状のオペレーションを把握した上で、次にそれぞれの部門で何がミッションとなっているのかまで把握し、キーマンが誰なのかという点とこれから取り組めることはどういうことがあるかという情報の整理をお客様と一緒に進めました。
また、実際に施策を回す現場の方とは、そもそもウェブマーケティングとは?についての説明やGoogle Analyticsでの解析の仕方、ウェブサイトのKPIの置き方、マーケティングメールの配信後の成果チェックなど、地道に初期の信頼獲得をしていきました。そこから少し時間が経った時に、幸いマーケティングオートメーション自体の差し替えについて提案する機会をいただけたので、弊社が得意領域としているHubSpotの導入に至りました。

大里
HubSpotの導入は、クリエイティブホープからやりましょうよと提案したのですか?
白石
先方でニーズがあることを知り、弊社から提案したという感じでしたね。また、ちょうどそのタイミングでインサイドセールスの部署が正式に立ち上がるという話あったので、MAツールとSFA(セールス・フォース・オートメーション)の導入について検討が始まりました。
それまで使用していたツールと比べて、HubSpotはSFAも内包してマーケティング活動にも使うことができ、クリエイティブホープにも知見があるというところがポイントでした。
大里
なるほど。では、まさにウェブマーケティングの領域からデジタルマーケティングやデジタルセールスにシフトしていく過程と新たに出てくる課題の解決に伴走しているという感じなんですかね。
白石
そうですね。ちなみに、いま最も重要になってきているところが部門間連携です。やはり、デジタルマーケティングは顧客と出会う入口から受注するまでの過程をどのように施策連携して集客効率を上げていくのかという点が重要となります。
例えば、インサイドセールスの部署においてキャパシティが限界を迎えている場合に、そのキャパシティを乗り越えるために部署人数を増やすのか、それとも1人あたりの対応工数を減らして、対応件数を増やすのかが論点となります。また、マーケティングチームの方では、インサイドセールスが対応する件数の創出と質の担保の両方をどのようにやっていくのかを考えていきます。
そういった状況理解や方針に基づいて、CRM(カスタマー・リレーションシップ・マネジメント)の再設計やKPIの見直しを丁寧に行っていきます。いまはまさにそこに取り組んでいるという感じです。
目標を達成するため一番大切なことは「何が変数なのか、つまりどこを改善したら1番インパクトあるのか」を知ることです。万が一必要なデータが取れていなければ、まずはしっかりとデータを取れるようにしましょうというご提案から始まります。データマネジメントをしっかり行わなければ、この先どのように数字を伸ばしていくのかの想定も立てられないので、ここ半年ぐらいはそういった支援で動いていますね。

課題点を粗く・素早く可視化し、キーマンと共に動く
大里
――大きなプロジェクトの時や難易度が高い案件への向き合い方や、お客様との会話で気をつけていることがあれば教えてください。
藤井
DXという言葉は世の中で結構浸透してきていますし、デジタライゼーションという言葉に関しても、皆さん理解を深めてきていると感じます。しかし、具体的にどこから手をつけていけばいいのか、どういう一歩目を踏めばいいのかを描けない経営者さんや事業リーダーさんが多いとも感じます。なぜなら、現状のシステムや業務フローを理解していない、現場が何をしているかが分かっていない方が多いからだと捉えています。
なので、私がまず一番心がけていることは、現場が何をやっていて、何に困っているかを細かくではなく粗く可視化してあげることです。そして、現場が困っていることを変えることによって、どれぐらいの事業インパクトがあるのかも一緒に可視化してあげることです。
解決策をモデル化して、課題解決のための理解を助けてあげることが非常に重要で、経営者の皆さんは頭がいい方ばかりなので、必要な情報を提示することができればその後どのように対応するかの判断は早いと感じます。細かいことを含めて初めから全てを可視化するよりは、一番大事な点を明確にして判断を促すことを心がけています。
白石
私は、弊社メンバーだけがいくら課題解決を推進しようとしても、お客様側に推進する意思が無ければ難しいので、お客様の中でキーマンを見つけてその方に社内の推進役となっていただくために働きかけることです。
推進力のある方に対して、どのような情報を与えることで動いてもらえるか、細かい作業ややり取りを経て想定よりも早く良い結果につなげられるように少しでも早く環境を整えることができるかが重要です。
臆せず発言し、お客様からの信頼を獲得する
大里
――経験豊富なお二人でさえ、コンサルタントとして働くことに大変さを感じるのはどういった状況ですか?
藤井
難しい質問ですね。例えば、お客様に対して伝えるべきことははっきりと伝える、セクショナリズムを超えた会話をする状況でしょうか。
弊社メンバーとお客様などプロジェクトに関わる方全員が同じ方向を見れていない時は、衝突が起こることもしばしばあります。例えばお客様からすれば、自分たちが行っている業務に外部のコンサルタントが侵食してきたと感じる怒りのようなものですかね。
ただ、私たちは第三者であるからこそ率直に意見を言える立場です。間違っているものに対しては、強く発言すべきですしたとえ契約が切られようが、その会社さんのプロジェクトが進むのであれば、言うべきことを言うのが大切だと思っています。そういった苦しい状況で発言することが、支援する立場、コンサルタントとしてのポジショニングを得るために必要なのです。

白石
私は大きく二つありますね。まず初めは、そもそもどのようなデジタルマーケティングツールがあるのかを知らなかったので数多あるツールを覚えるところです。私は元々広告領域の支援を得意しており、以前までは広告で獲得した見込み顧客を業務側にパスする立場だったので、業務フローや業務プロセスの理解や可視化についてはあまり経験がなく得意ではありませんでした。そのため、どういった業務フローになっているのかのヒアリングと可視化をして、それに基づいたツールの活用提案をするのが、正直一番しんどかったですね。
案件について特に大変だったことといえば、新しい解決策へのチャレンジがとめどなく続く状況において、くじけずにお客様とコミュニケーションを取り、結果を積み重ねていくことです。そして、当初の想定よりも早く良い方向にプロジェクトが進むように環境を整えることを大事にしています。
パッと見て分かる画期的なソリューションを提供したい
大里
――お二人は最近、新たな自社商材作りを積極的に行っていますがどのようなきっかけや背景があったのでしょうか?

藤井
クリエイティブホープは以前からオートクチュール型のコンサルティングサービスを提供しています。ただ、個人的には、すごくいい点でもあり、欠点でもあるとずっと思っていまして、一社一社に対して課題を見て、それに対する解決策を提案してきたことは良いことなのですが、同じような課題を持っている他社さんに対してオートクチュール型の提案を横展開できていないことが経営陣としても大きな問題であると感じていました。
これだけ数多くの課題解決をしてきた実績があるのだから、もっと世の中に広げることができたら多くのお客様の課題解決につながるんじゃないか、というのが新たなソリューション商材を増やすことに至った一つの理由です。
また、人材育成における問題もあります。オートクチュール型で専門的な経験のもとで提案できるメンバーは価値が高いですが、すべての若手がベテラン社員と同じレベルに成長するには時間がかかります。なので、その差分を埋めていくためにもソリューション商材をある程度型化し、お客様に提供することができれば効率的な課題解決につながると思いました。
一方で、各商材それぞれでキャラクターを作っている理由ですが、一般的にコンサルティング会社が作るサービスやソリューションメニューは分かりにくいことが多いと感じていたからです。なので、今回私たちが新規商材を作る上で3つ大事にしたことがありました。
まずは「お客様が持っている問題点と課題点の明確化」です。具体的に何が課題なのかが資料を見てパッと分かるように心掛けました。次に「その課題解決がなぜ妥当なのかということが分かること」そして、「キャッチになるキャラクターと名前にこだわる」ということです。
今回、HubSpotに関わるソリューションを多く出していますが、考えているのはHubSpot社やHubSpotのパートナーさん、HubSpot導入企業が見た時にいかに目を引くことができるかということですね。
1個ずつのサービスに、可愛らしい、かっこいい、面白いキャラクターが必ずいると。それがキャッチになるだろうし今後さらにソリューション数が増えると、なんかAIキャラクターがいるサービスを持っていて色々、答えや引き出しを持っていそうな会社だなというイメージ付けも働かせられると思ってアプローチにしてみたのが本当の背景でございます。
白石
実際、キャラクターを作るようになってからの変化は大きいです。例えば、アウトバウンドでの架電時も「~~なキャラクターが付いている資料でのお電話です。」と伝えると相手がすぐに商材のことを思い出していただけるようになりました。
商談時にも、課題感ヒアリングした上でその課題を解決するためのいくつかの方法があります。その中で今回はこれがいいですという形でサービスの紹介もしやすくなりますし、そこに対しての難易度が全然なくなりましたね。
また、課題に対して提案するサービスをロジック化すれば、商談の場でパッと資料を出してサービス提案ができるので提案のスピードは上がったかなと感じるますね。
ちなみにに今はデジタルマーケティングの必要各ステップごとに、よくある課題とサービスのマッピングを見える化しています。将来的に、うちはこれだけの課題全部に対応できますよという見せ方もできますし、このサービスではどのような課題を解決できますか?などその場での引きにもなると考えています。

ロジカルシンキングは、平均点。
大里
――活躍している若手社員に共通する点は何かありますか?
白石
そうですね。マインド面とスキル面で共通点があると思いますが、マインド面のところで言うと自立(律)心がある人が伸びていると思います。自分で立つと書く方もですし、自分を律するという意味もだと思いますが自分のやるべきことに対して、自ら進んで取り組み、コミュニケーションを取る。そして、目標に達したら次の目標は自分で設定できる。受け身にならずに能動的に自ら発信して、どんどん進んで行くことができる人というのは伸びていますし、そういう人たちの集まりになってほしいと思いますね。
スキル面では、Growth Hack事業部ではディレクションに対する興味関心・スキル持っていることですね。あとは、プロジェクトやデータなど、何かしらしっかりと自分でマネジメントして進めていきたいという推進力を感じる人たちも結構伸びている印象があります。
自分なりのある種、専門性を持ちつつもしっかりプロジェクト推進できる、しっかりと責任持ってできるといったところが頭の中に浮かんでくる人たちで、伸びているなと感じます。
あとは、ちゃんと手を動かせる人ですね。まずは自分で実際にトライしてみるのが非常に大事ですね。
藤井
インプットやアウトプットが速い子、または両方持っている子ですね。私の場合は、まずインプットするということに積極的な子はすごく評価したいなと感じます。最近ではインプットする手段がたくさん出てきていると思うので、それこそChatGPTを使うのもそうですけど、インプットがより効率的な人ほど頭回転が速いなと思いますし、成長してるなという印象があります。
僕らの世代と違って、今の子たちは情報の受け取り方がフロー型だと思うんですね。検索する時のキーワードクエリも僕たちだと3つ、4つくらい書いてあたりつけて検索をかけますけど、2つとかで検索をかけて、膨大なリストの中から情報探してしまうといったようなことがあって、そもそも検索の仕方があんまり得意ではなかったりしますが、インプットが速い子はそういったところからもうすでに周りと違うというのがあったりするので、まずはインプットの速さを求めたいなと思っています。
あともう1つはアウトプット力ですね。実は先日、うちの若手で実際にあった話なんですけど、今の時代どうしてもこれだけ情報量が多いので、最適な答えを出すことって誰しもが難しい。ただ、やっぱりまだみんな若いから、お客様に対して最適な答えを出さなきゃいけない!という強迫観念のようなものに悩まされていると感じることがあります。でも、コンサルタントという仕事は必ずしも最適な答え出すことが仕事ではないという風に思ってます。
答えに至るまでのプロセスをしっかりと作ってあげること、みんなが「これがゴールだよね」と合意できるプロセスを作ることがとても重要だと思っていて、そのためには一緒にお客様とディスカッションするための素材を用意することが大事だったりもしますし、自分がアイデアを出すために、どういう風な判断軸でアイデアを出した方がいいかという、軸の設計ができるということが結構重要なのかなと思っています。
当然ながら、情報量が多い世の中だからこそ情報をまず整理して、どんな類の情報が何パターンあって、その中で選ぶべきものはこれだということを抽出してかないと、お客様にしてみればそれがなぜ正しいのかが分からなかったりする。だからこそ、僕たちはその理由や根本的な課題がどれで、だからこれに取り組む必要があるというストーリーがないと理解をしてもらえないことがあります。
なので、アウトプット力というところで求めたいのは、情報を整理する力いわゆるフレームワークを使えるというのをまず基本スキルとして求めたいですね。これはロジカルシンキングの話だったりすると思うのですが、本当に必要なのはそこにプラスアルファされたアウトプットで、ロジカルシンキングができることはあくまでも平均点の答えしか出せないと思っているので、プラスアルファ自分ならでは、もしくはその会社さんならではのクリエイティビティある提案を出せるとより魅力的な答えになっていくし、クリエイティブホープさんってやっぱり素晴らしいなと言われるような人材になっていくんじゃないかというのが僕の意見です。

大里
――最後に、クリエイティブホープの好きなところと、記事を読んでくれている方へのメッセージをお願いします!
白石
一緒に働いている人と、会社の制度というかカルチャーは結構好きだなと思っていて、僕自身これまでもそうですし、今後も多分そうだと思うんですが、どんな仕事をするかというよりも、誰とどんなこと成し遂げたいのかみたいなことを感じながら働く方が仕事は楽しいと感じますし、やりがいも出てくると思うんですよね。今一緒に働いている人もこれをやってみたい!とか、自分の専門性を持って僕よりすごい人はたくさんいます。それは若手でも目上の人でもそうです。そこに対して、刺激や影響を受けて、自分はもっとこうしなきゃなと考えさせられるので、そういったところがいいと思います。
実際、これをやりたいとか、これをやらなくちゃいけないという発想になった時、じゃあやってみようよって言っていただける、要は与えられるチャレンジと、自らやるチャレンジの両方ともできるという会社が今までなかったので、その辺の環境は非常にやりやすいな、と。
先ほどの自立の話もそうなんですけど、やはり前向きに自分に対しても会社に対しても責任持ってやっていきたいという人に対してはすごくいい環境だと思います。
藤井
僕がクリエイティブホープにいて楽しいなと思うのは、社会を変えられるところにいるなと感じられるからです。 例えば、弊社のお客様の劇団四季様は数百万規模のユーザーがいてとか、某製造業の会社さんは社員数が数万人とか、もはや町もしくは大都市レベルの人たちが各お客様先にいると想像するだけでワクワクするし、その人たちを動かす企画を考えられる、もしくは戦略を描いて実行できるというのがもう楽しくて仕方ないです。
以前担当した案件でも、企画したことが国会での議論内容として組み込まれ検討されることもありました。積極的に取り組めば、自身が考えた企画が世の中の新たな選択肢となることが本当に生まれるんだなと感じました。
クリエイティブホープは50人規模の会社ですけど、自分で手を挙げて、企画して、責任を持ってやれば、世の中にとって新しい選択肢を作ることができるというのが1番面白いところなのではと。仮に大手のコンサルファーム行っても、若手のうちは特にたくさんあるプロジェクトチームの一員までにしかなれないと思うんですけど、クリエイティブホープであれば、プロジェクトリーダーがいてそのすぐ横で一緒に企画して動けるからこそ、あなたの実力次第でなんでも世の中に対して選択肢を提案することができると思います。
それを楽しいと思うか、思わないかですね。

今回は弊社のトップコンサルタントである取締役の藤井さんとGrowth Hack事業部で副事業部長を務める白石さんの2名に対談形式でインタビューを行いました!今後もクリエイティブホープ社員のインタビューをはじめ、「クリエイティブホープってどんな会社なの?」「クリエイティブホープってどんな働き方なの?」といったコンテンツを増やしていきますので、今日のストーリーが参考になった方は、ぜひ「いいね」と「フォロー」ボタンを押していただけると嬉しいです!
/assets/images/22436/original/7737f005-96d8-4087-ab67-e2fb06185735.jpeg?1402562107)


/assets/images/22436/original/7737f005-96d8-4087-ab67-e2fb06185735.jpeg?1402562107)


/assets/images/22436/original/7737f005-96d8-4087-ab67-e2fb06185735.jpeg?1402562107)
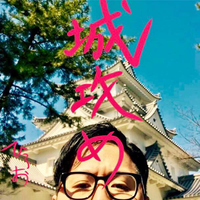

/assets/images/22436/original/7737f005-96d8-4087-ab67-e2fb06185735.jpeg?1402562107)
