こんにちは。
ロングブラックパートナーズ株式会社採用担当です。
本日から9月になりましたが、まだまだ暑い日が続いていますね。
体調管理等、お気を付けください。
今回からは、新たな企画として、当社のメンバーのおすすめ書籍を紹介していこうと思っています。
当社にご応募いただく多くの方から、面接時に「おすすめの書籍は?」という質問を多くいただきます。
また、書籍の紹介を通じて、ロングブラックパートナーズにどういった人が在籍しているのかを感じていただきたいと思い、スタートしました。
第一回目は、統括パートナー牛越がおすすめする、
幸田露伴 著「努力論」です。
牛越が本書との出会いから、なぜおすすめしているかまで詳しく書いておりますので、ぜひご一読ください。
目次
本書との出会い
なぜ本書を推薦するのか
推しポイント
まとめ
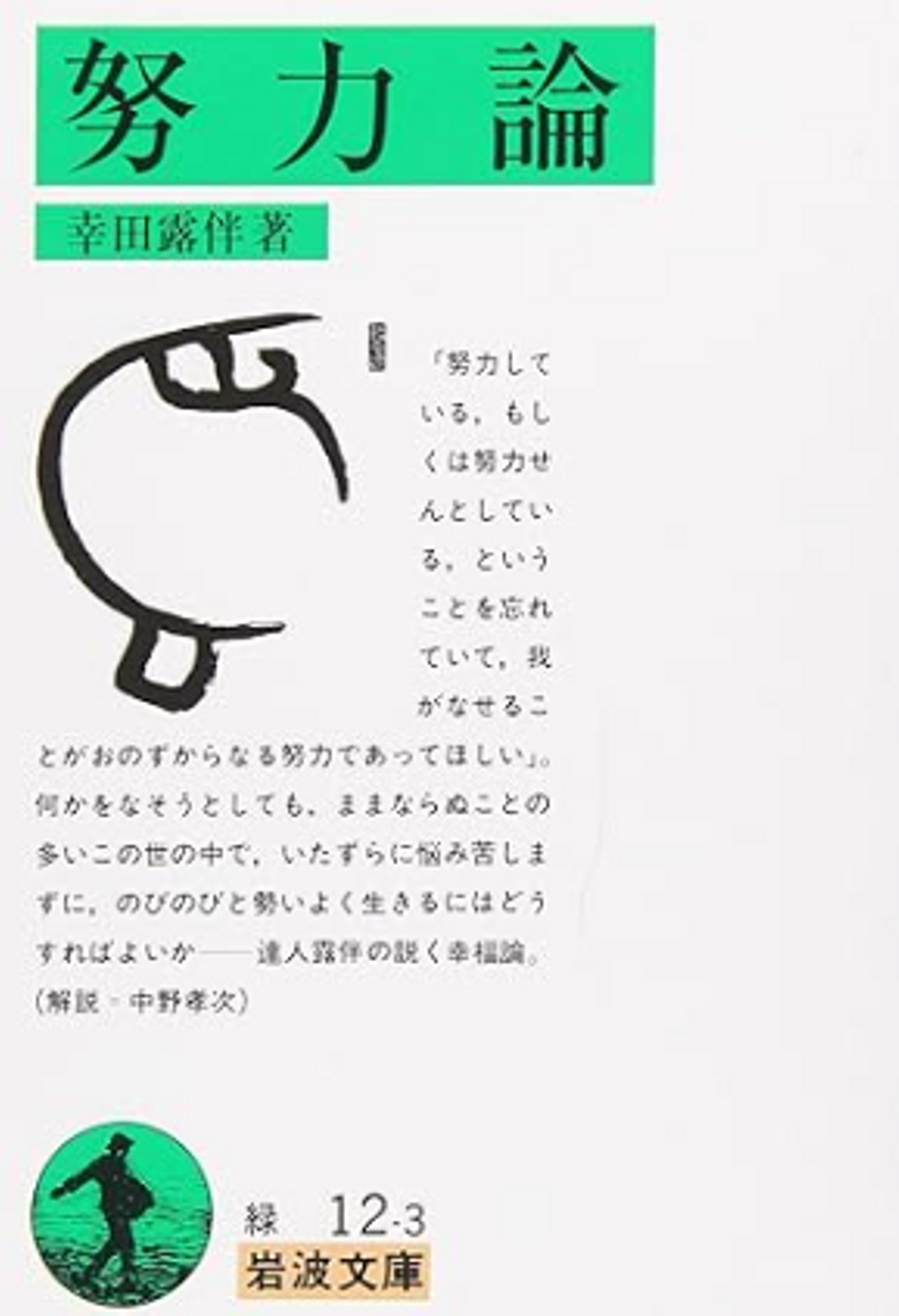
本書との出会い
社会人2年目、会計士補として働いていた私は、知識も経験も未熟で、クライアントや上司に迷惑ばかりかけていました。将来自分はどのようにして社会の役に立てるのか――そんな漠然とした不安を抱えていたとき、転勤先の盛岡の書店で一冊の本に出会います。幸田露伴の著した『努力論』です。文豪がこのような実践的な書を残していたことに驚き、思わず手に取りました。
それ以来、本書は生涯のバイブルとして、今も折に触れて読み返し、心を震い立たせています。
なぜ本書を推薦するのか
投資は若いうちから始めたほうが良いとよく言われます。コツコツと蓄積することで、将来大きなリターンにつながる可能性があるからです。
では、人生における「投資」とは何か――それこそが「努力」だと私は思います。
今の時代、社会人には専門性が求められています。それはネット上の知識だけでは得られない、現場での経験を通してしか培えない肌感覚を伴う専門性です。生成AIは誰もが利用できる便利な道具ですが、地道な努力によって積み上げられた経験と知見は、決してAIだけで代替できるものではありません。
だからこそ、「努力」の正しい方向性と意義を、明治の文豪から学ぶ意味があるのです。
推しポイント
本書には原書版と現代訳版がありますが、文章の力強さや説得力という点で、可能であれば文語体の原書版をおすすめします。とはいえ文語体は読みづらく時間もかかるため、まずは「自序」「運命と人力と」「着手の處」「自己の革新」まで(約17,000字、文庫本30ページ程度)を試しに読んでみてください。
「自序」には、
「努力して居る、若くは努力せんとして居る、といふことを忘れて居て、そして我が爲せることがおのづからなる努力であつて欲しい。さう有つたらそれは努力の眞諦であり、醍醐味である。」
とあります。ここで露伴は、本書全体を貫く「あるべき努力」の姿を定義しています。彼は「努力して努力する、それは真の良いものではない。努力を忘れて努力する、それが真の良いものである」と説いているのです。仕事や勉強をしていると、目の前の課題に没頭し時間を忘れる瞬間がありますが、それこそが露伴の言う「努力の眞諦」なのかもしれません。
「運命と人力と」は、努力する意義を具体的な事例で説明しています。
「川を挾んで同じ樣の農村がある。左岸の農夫も菽(まめ)を種ゑ、右岸の農夫も菽を作つた。然るに秋水大に漲つて左岸の堤防は決潰し、左岸の堤防の決潰した爲に右岸の堤防は決潰を免れたといふ事實が有る。」「好運を牽き出す人は常に自己を責め、自己の掌より紅血を滴らし、而して堪へ難き痛楚を忍びて、其の線を牽き動かしつゝ、終に重大なる體躯の好運の神を招き致すのである。」「前に擧げた左岸の農夫が菽を植ゑて收穫を得ざりし場合に、其の農夫にして運命を怨み咎むるよりも、自ら責むるの念が強く、是我が智足らず、豫想密ならずして是の如きに至れるのみ、來歲は菽をば高地に播種し、低地には高黍(たかきび)を作るべきのみ、といふ樣に損害の痛楚を忍びて次年の計を善くしたならば、幸運は終に來らぬとは限るまい。」
露伴がここで伝えているのは、「成果が出なかったとき、環境や運命を責めるのではなく、自分の備えや智恵の不足を省みて次に活かす姿勢」です。努力が必ず報われるとは言いません。しかし、自らを責めて改善し続ける人には「幸運が訪れないとは限らない」と、可能性を残しています。
この考え方は、後に述べる事業再生の専門家の姿勢と重なります。再生の現場でも、必ずしも望んだ成果が得られるとは限りません。むしろ厳しい局面に直面することが多い。そのとき、環境や他人のせいにせず、自らを省みて次の一手を考える姿勢が不可欠です。「運命と人力と」で示された精神は、そのまま現代の専門家の心得へとつながっていくのです。
「着手の處」では、
「何でも彼でも着手の處を適切に知り得て、そしてそこに力を用ひ功を積んで、そしてそこから段々と進み得べきでは有るまいか。」
と述べ、複雑な課題に向き合うときは、正しい入口を見極め、一歩ずつ積み上げることが重要だと説きます。これは事業再生の現場でも通じる鉄則です。
そして「自己の革新」では、
「誰も皆『新しい自己』を造りたい爲に腐心して居るので有るが、其の新しい自己が造れぬので、歳末年頭の嗟歎や祝福を繰返すのである。」「自己を新(あらた)にするにも、他によるのと、自らするのとの二ツの道が有る。他力を仰いで、自己の運命をも、自己其物をも新にした人も、決して世に少くは無い。」「他人によつて自己を新(あらた)になさうとしたらば、昨日の自己は捨てて仕舞はねばならぬのである。」
と説きます。つまり「自己革新」とは、過去の自分を捨て、他者の知見や経験に身を委ねて初めて可能になる――という厳しい真理です。
私自身も20年以上前、あるプロジェクトをきっかけに事業再生の道を志しました。しかし、自分一人で専門家になることは不可能でした。専門性を有するファームに転職し、経験豊富な上司に仕え、過去の自分を否定する覚悟を持って初めて専門家としての一歩を踏み出したのです。
まとめ
事業再生コンサルや事業再生ファンドは、企業の生死を左右する重大な局面で支援する仕事です。そのためには、財務・事業・経営・管理に関する知識に加え、民法・会社法・倒産関連法や金融実務、さらには事業価値評価(バリュエーション)など、多面的かつ深い理解が欠かせません。
こうした専門性は一朝一夕で得られるものではありません。だからこそ露伴の『努力論』が指針となります。
「自序」が示す没頭の姿勢、「運命と人力と」が説く自責の精神、「着手の處」に学ぶ段取りの重要性、そして「自己の革新」が求める他力を仰ぐ覚悟。これらはいずれも、事業再生の専門家が歩むべき道そのものです。
事業再生のプロセスは、まさに「努力論」を体現する営みです。没頭し、自責を重ね、正しい段取りを踏み、他力を受け入れて自己を革新する――その歩みの先に、企業を救い、社会に貢献する未来が広がります。
私たちロングブラックパートナーズは、その道を共に歩む仲間を求めています。あなた自身の努力と革新が、再生企業の未来を変える力になるのです。
最後までお読み頂き、ありがとうございました。
この記事を読んで、事業再生、もしくはロングブラックパートナーズに興味を持っていただきましたら、
ぜひ下記リンクより、ご連絡ください。カジュアルに話ましょう!

/assets/images/5868364/original/af3c807d-e305-445f-8b19-bccebdd2b8f5?1625187061)

/assets/images/5774502/original/f43cff9c-4a6a-45c2-be05-9d7191e2bce6?1658986447)



/assets/images/5774502/original/f43cff9c-4a6a-45c2-be05-9d7191e2bce6?1658986447)

