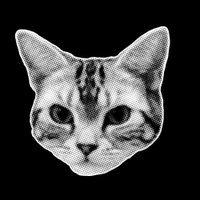フリーランスになれば、自由な働き方ができそう…… そう期待して独立したものの、「思ったより稼げない」「忙しいのに生活は安定しない」といった壁に直面するデザイナーは少なくありません。理論上は充実したデザイナー生活が送れるはずなのに、なぜ理想と現実の乖離が発生してしまうのでしょうか。
なぜフリーランスで“稼げない”のか?
どうすれば、信頼され、選ばれるデザイナーになれるのか?
今回は、会社員デザイナーからフリーランスとして独立、数年後に自身で会社を立ち上げたUIデザイナー、株式会社バイネームの井上さんが、自身の経験をもとにリアルな視点をお届けします。
焦って安い仕事を受けると悪循環に
── なぜ、フリーランスのデザイナーは「忙しいのに稼げない」状態に陥りがちなのでしょうか?
フリーランスとして独立したデザイナーの中には、会社員時代にある程度の成果を出していたにもかかわらず、「思ったより稼げていない」「ずっと忙しいのに収入が伸びない」と感じている人が多くいます。私の目から見ると、その大きな原因は「仕事の取り方」にあると感じています。
よくあるのは、独立後すぐに前職のつながりや知り合い、クラウドソーシングなどを頼って案件を受けるケースです。たしかにそれは手っ取り早く仕事につながりますが、報酬単価が低くなりがちです。もともと単価が低い案件からスタートすると、それが基準になってしまい、年収はなかなか上がりません。実績があっても「友達価格」になったり、単価交渉の余地がなかったりする。クラウドソーシングも同様で、そもそも安く発注したい人たちも多い場です。結果的に、安い案件をこなし続ける悪循環に陥ってしまいます。
私自身は、独立時に前職のつながりからは一切仕事を受けませんでした。代わりに、自分から営業をかけて仕事を取りにいったんです。そこでは「自分が得意とする領域」を軸に、専門性が伝わるような営業を意識していました。そして、最初から「これ以下の金額では仕事を受けない」と最低時給を決め、それを下回る案件はすべて断っていました。目先の収入にとらわれてしまうと、質の低い案件に時間を取られ、気がつけば自分の首をしめてしまうことになりかねません。
フリーランスは「作るスキル」だけでなく、「どう価値を伝え、どうお金を得るか」のスキルも不可欠だと思います。
案件の単価交渉をしたことがないデザイナーもいるかと思いますが、クライアントとの価格交渉ができないと、「今の金額が適正かどうか」も判断できず、納得のいかない条件で働き続けてしまいます。さらに、ポートフォリオでも「自分がどこまで担当したのか」「どんな役割だったのか」をきちんと伝えないまま営業している人が多く、それでは自分の価値を正しく理解してもらえません。
信頼を得て段階的に案件を大きくする
── では、その「忙しいのに稼げない」状態を抜け出すには、どうすればいいのでしょうか?
方法はいろいろありますが、まず私がやったのは、「単価が低い仕事を全部やめる」という決断でした。思い切って一度すべてを手放し、高単価の案件に集中する。その一件にしっかりコミットすることで、自分の価値を正しく評価してくれる環境に身を置くことができました。
とはいえ、いきなりすべてを手放すのはリスクもあります。なので、まず試してみてほしいのは「いま一番単価が安いクライアントに価格交渉してみる」ことです。もし単価が上がればなによりですし、上がらなければその時点で契約を続けるのか見直せばいい。そしてその次に単価の低い案件へ交渉を試す。そんなふうに、一気にではなく段階的に改善していくのが現実的です。
よくあるもったいないケースは、「単価が低いからもう契約を終わらせます」と交渉なしで切ってしまうこと。それよりもまず、交渉をしてみるべきです。値段そのものだけでなく、業務内容や業務量を調整することで納得感のある働き方に変えることもできます。
「単価を上げる=スキルを上げる」と思われがちですが、それだけではありません。もちろんスキルアップは大切ですが、それ以上に、「この人とは長く付き合いたい」「一緒に仕事を進めやすい」と感じてもらえるかどうかが重要です。信頼や安心感に対して、人はお金を払います。いくらスキルが高くても、やりづらいと感じられれば契約は続きません。
自分のスキルと報酬が合っていないと感じたときこそ、自分の働き方や関係性を見直すチャンスだと思います。
── そもそも、「お金になるデザインスキル」とはどんなものでしょうか?
私が携わってきたのは、まだ何も決まっていない状態から要件を整理し、「どうあるべきか」を一緒に考えていくような、いわゆる“上流工程”を含んだ仕事です。ただ、最初からそういう仕事をしていたわけではありません。
フリーランスになりたての頃は、「これを作ってください」と与えられた制作物をこなすだけの仕事が中心でした。でも、そこで終わらずに、自分なりに「なぜこうするのか」「この構成でユーザーに伝わるのか」といったUXやストラテジーの視点で提案を重ねるようにしました。意図を明確にしながら提案することで、「井上さんってそういうこともできるんですね」と信頼されるようになり、自然と業務範囲も広がっていきました。
業務の領域が広がれば、そのぶん報酬にも反映されます。いきなり上流工程の案件を請けるのは難しくても、まずは単価が低めの一部の業務で信頼を得て、少しずつ「もっと相談したい」「上の人にも紹介したい」と思ってもらえるような関係を築く。その積み重ねが、長く安定して稼げるフリーランスへの道だと感じています。
よく「時給を上げたいなら、余計なことはやらない方がいい」と考える人もいますが、それだとまたゼロから営業をしなければなりません。新規のクライアントとの取引におけるリスクとしては、発注までに時間がかかったり、未払いが発生したり、業務内容に齟齬があったりと、実は様々な要素があります。こういった視点でも、新規のクライアントに一から提案するよりも、すでに信頼関係のあるクライアントに対して業務を拡大していく方が、手っ取り早く、しかもリスクが少ないんです。
さらに、そこでしっかり成果を出せれば、実績として公開できるようになったり、新たな取引先の紹介が生まれたりします。クライアントの担当者が転職したあとに、別の場所でまた声をかけてもらえることもある。5年10年というスパンで考えると、「思い出してもらえる存在になること」が、長く働く上でとても大事なんです。
信頼を積み重ねていくことで、営業はどんどん楽になります。お金になるスキルとは、単なる手を動かす技術だけではなく、そうした信頼の土台を築けるかどうかにかかっていると感じています。
発注者視点でニーズを解析し、相手に合わせた営業を
── フリーランスになったときから、そうした戦略は意識していたのでしょうか?
独立した当初から意識していたことは「自分がもし発注者の立場だったら、どういう人に仕事を依頼するだろう?」という視点を持つことでした。言い換えると、「発注する側の気持ち」から逆算して、自分の立ち振る舞いや価値の伝え方を設計していく、という考え方です。
私はもともとUXデザイナーとしてキャリアを積んできたこともあり、「クライアントがどうすれば気持ちよく発注できるか」「どういう体験をすれば、またお願いしたいと思ってもらえるか」といった点を、UX的な視点で捉えるようにしていました。実際、行動経済学なども参考にしながら、「発注側がどういうところで判断しているのか」を自分なりに分析していました。
たとえば、こまめに進捗を共有する、提案時に選択肢を持たせる、課題の背景を先回りして整理しておくなど、発注者の心理に寄り添ったコミュニケーションを意識しています。そういった姿勢が信頼を生み、「またお願いしたい」と思ってもらえる結果につながっているのだと思います。
うまくいかないクライアントに悩むよりも、「自分に合うクライアントはどこにいるのか?」「どういう人とならよい関係を築けるのか?」を考えるほうが、ずっと建設的です。そのためには、自分のことを知るだけでなく、クライアント側の行動や考え方を深く理解する必要があります。でも、そういった分析をしないまま、ただ「案件がない」「評価されない」と感じてしまっているフリーランスも少なくありません。
“よい仕事”は偶然やってくるものではなく、「どういう人から、どんな文脈で頼まれると価値が出せるか」を考え、設計していくものだと思っています。
── 営業が苦手というデザイナーも多いですが、自分をどう“売り出す”かについては、どう考えていますか?
多くの人が「営業」というと、飛び込みやテレアポのようなイメージを持っているかもしれませんが、そうではありません。
まず私が大切にしていたのは、「どのクライアントにも同じ営業スタイルでアプローチしない」ということ。プロジェクトごとに状況も課題も違うので、まずは相手が何に困っているのか、どんな課題を抱えているのかを丁寧に聞き取るようにしています。
そのうえで、「私はこれができます」「その課題に対して、こういう支援ができます」と、自分のスキルを“当てにいく”ようにしていました。よくあるのは、自分のできることを一方的に売り込むだけの営業。でもそれでは、相手のことを理解していないままの押し売りになってしまいます。
営業とは本来「あなたの困っていることを、私がどう解決できるか」を伝えることだと思うんです。私はこれまで、デザインやUXだけでなく、プロジェクトマネジメントや要件整理など幅広くやってきましたが、それもすべて「相手が何に困っているのか」からスタートしています。自分のスキルと相手の課題がうまく重なったとき、はじめて信頼が生まれる。その積み重ねが、結果として次の案件や長期的な関係につながっていくのだと思っています。
── 独立する前に、会社員として経験しておいたほうがいいことはありますか?
会社員として働いているうちに意識しておくとよいのは、「企業がどうやって意思決定をしているか」をしっかり観察しておくことです。特に大きな企業に所属している場合は、現場レベルの判断と、部長や役員など上の立場の人が行う意思決定のプロセスはまったく違います。そこに目を向けておくと、独立したあとの仕事の取り方や、ポートフォリオの作り方にも差が出ます。
たとえば、実は発注の決裁者はデザイナーの細かいアウトプットまでは見ていません。それよりも、「この人がうちの課題を解決してくれそうかどうか」という視点で見られています。だからこそ、「この企業のこんな課題をこう解決した」というように、企業視点での成果をきちんと伝えることが重要なんです。
さらに、社内の人がどういう判断軸でパートナーを選んでいるのか、コンペで選ばれる理由・選ばれない理由なども、社内での会話やプロセスから学べます。それを知っておくと、自分が将来フリーランスとして営業をする際に、「どういう人が選ばれやすいのか」「どういう言い方やアプローチが有効なのか」が見えてきます。
中小企業にいる場合でも、できることはたくさんあります。たとえば、実際に自社に発注してくれているクライアントに、「なぜうちを選んでくれたんですか?」と聞いてみる。そういう質問を通じて、自分たちの強みがどこにあるのか、自分がどう評価されているのかを知ることができます。それはそのまま、将来自分が独立したときに武器になるはずです。
フリーランスとして仕事をもらう相手は、結局のところ「企業」です。だからこそ、企業の内側で何が起きているのかを理解しておくこと。それが、独立後の営業や仕事づくりの大きなヒントになると私は思っています。
フリーランスになる前に「バイネーム」で働くという選択肢
── 井上さんが代表を務めるバイネームでは、フリーランス志向のデザイナーにどんな価値を提供できると考えていますか?
バイネームは、「フリーランスのように実力主義で自由な働き方をしたい」という人に向いた環境です。私自身、フリーランスとして長く働いてきたので、その自由さや裁量の大きさの良さはよくわかります。でも同時に、すべてを一人で抱えることの大変さや不安定さも経験してきました。
バイネームではデザイナー社員は営業をする必要はないので、安定してデザインの仕事に集中できる環境です。また、社会保障制度(厚生年金や健康保険など)はもちろん整っています。それらの負担がないというのは、大きな安心材料になると思います。
また、組織としては“フリーランスっぽい人たちの集合体”のようなチームです。それぞれが自走できる力を持ちながら、必要なときには助け合える関係性がある。たとえば、案件が一時的に重なってタスクがオーバーしそうなときには、他のメンバーに手を貸してもらえるし、逆に自分が誰かをサポートすることもあります。これはチームだからこその良さだと思います。
── 制作会社との違いはどういった部分ですか?
制作会社での仕事は、「依頼されたものを、正確に、スピーディーに作る」というスタイルが多い印象です。もちろんその力も大切ですが、バイネームではそこからもう一歩踏み込んで、「そもそも本当にそれを作るべきか?」「なぜそれを作る必要があるのか?」というところから、デザイナーが主体的に関わっていきます。
課題の本質を見極めて、「どうすれば解決できるか」をデザイナーの視点から提案する。それが、バイネームの仕事のスタートラインです。ただ与えられた指示をこなすのではなく、ビジネスゴールとユーザーの体験、技術的な実現性などをバランスよく考慮しながら、プロジェクトの上流から関わっていきます。
そのぶん、デザイナーが対応する領域もかなり広いです。UX設計からビジュアルデザインはもちろん、場合によってはビジネスサイドや開発側とも直接やり取りをして、自分なりの視点を通してアウトプットしていきます。だからこそ、つくるだけでなく「考えること」もデザイナーの大切な仕事の一部なんです。いまいる社員も最初から全てができていたわけではなく、働きながら徐々に自分で担当できる領域を増やしています。
── バイネームでは、分業せずにひとりのデザイナーが幅広く担当するスタイルをとっています。それはなぜですか?
もちろん、専門性の高い人たちでチームを組んで進めるやり方にも良さはあります。ただそのぶん、どうしてもコミュニケーションコストが大きくなりがちです。特に運用フェーズや、クライアントと長期的に並走していくようなプロジェクトでは、情報を受け取る人(ディレクター)とアウトプットする人(デザイナー)が分かれていることで結果的に意図が正しく伝わらず、ズレやノイズが発生してしまうんです。
だからバイネームでは、ある程度の規模までは一人のデザイナーがヒアリングから設計・デザインまでを一貫して担当しています。その方が、クライアントとの信頼関係も築きやすいし、成果がダイレクトに評価につながる。つまり、「誰の仕事か」がはっきりすることで、対価の交渉もしやすくなるんです。
世の中的には「属人化しないこと」が良いとされていますし、多くの会社は誰が抜けても回るような体制を目指しています。でも、私たちはあえて“属人的”にしています。クリエイティブな仕事は、人の視点や感性が大きく影響する分野です。そこに他人のフィルターが入りすぎると、良くも悪くも“平均化”されてしまうことがあります。
最小人数で、責任も裁量も大きく。その中で自分の色を出していけるのが、バイネームのデザイナーのスタイルです。
このスタイルにやりがいを感じられる人には、バイネームはすごくフィットする環境だと思います。言われたものをただ作るのではなく、自分の意志で価値を提案できる。この考え方はフリーランスにこそ求められるものだと思うので、フリーになる地盤を整えるのに最適な環境ではないかと思います。
株式会社バイネームでは一緒に働く仲間を募集しています
BynameのWantedly より、会社情報や募集をご覧ください!カジュアル面談では実際にデザイナーとして働く社員がお話します。