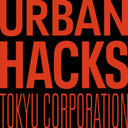こんにちは、東急株式会社「URBAN HACKS」採用担当です。
URBAN HACKSは、交通事業を軸に不動産、生活サービス、ホテル等多彩な事業を展開している東急株式会社が、街づくりにおけるDXを目的に、2021年7月より生まれた新組織です。現在、新たなイノベーションを生み出すべく、積極採用を進めています。
今回は、東急グループ各社とURBAN HACKSの開発チームをつなぐ「橋渡し役」、アカウントマネージャーに注目。そのリアルな業務内容やおもしろさ、難しさなどを、アカウントマネージャーの大橋 千裕さん・浅見 哲朗さん・山本 大輔さんに、お話を伺いました。
東急グループ内の相互理解を深める「橋渡し役」
―まず、アカウントマネージャーに携わる前の、皆さんのキャリアを教えてください。
大橋:今回参加している3名は全員、新卒で東急に入社しています。私は、これまでデジタル系の事業とは縁がなく、新卒からの約15年間、不動産開発事業に携わっていました。ホテル物件の証券化や渋谷ヒカリエ開業時のプロジェクト推進、コワーキングスペースの運営や二子玉川でのセグウェイツアーなど、幅広い業務を経験しました。そして2021年、急きょURBAN HACKSの立ち上げメンバーに加わり、現在に至ります。
山本:私は、2013年に新卒で東急に入社しました。当時は主に旅行事業に携わり、旅行会社の商品を販売する、「旅行代理店」のような役割をになっていました。。例えば「今年の夏はハワイ旅行をどう売るか」といった企画や広報施策、店舗のブランドリニューアルなどを担当していて、2022年までの約8年間在籍していました。その後、ご縁があってURBAN HACKSに異動し、現在に至ります。
浅見:私は2011年に東急へ入社し、東急線沿線のケーブルテレビ事業を手掛けるグループ会社のiTSCOM(イッツ・コミュニケーションズ)に出向しました。商品企画や新規事業の立ち上げを経て、直近では社長秘書も経験しています。東急社内ではめずらしく、ICT系の事業経験を積んできたこともあってか、URBAN HACKSに異動してきました。
―現在はアカウントマネージャーとして、どのような役割や立ち位置を担っていますか?
大橋:実はURBAN HACKSでは、「アカウントマネージャー」という役割に枠組みを設けているわけではありません。「組織として、事業やお客様に貢献するために必要なことを何でもやる」という状況で、特に優先順位が高いのがステークホルダーとの関係構築です。具体的には、各プロダクト・プロジェクトの窓口を担当したり、新規プロジェクト立ち上げの際の整理を行っています。各部門からの話を受けて、それぞれの要件や課題、ニーズをすり合わせながら案件を作っている状況です。
山本:私は主に東急電鉄を担当しており、「東急線アプリ」や「Q SKIP」を担当しています。役割としては、東急電鉄とURBAN HACKSの「橋渡し」が中心です。東急電鉄は鉄道会社ですので、URBAN HACKSとは文化や考え方には、もちろん違いがあり、その差を埋めるような役割を担っています。具体的には、定例会議のファシリテーションや課題整理、PdMのお手伝いなどです。実務面では、開発メンバーが開発に集中できるよう、法務関連の確認や会計処理などを東急電鉄と調整しながら進めています。
浅見:私は、東急グループの共通IDサービス「TOKYU ID」と、渋谷の東急のオフィスビル従業員向け優待サービスアプリ「Shibuya TOQ Pass」を担当しています。これらのサービスは、Webサービスとネイティブアプリという違いはありますが、グループ内関係各所との調整などが私の主な業務です。
―「橋渡し」の際に、大切にしていることはありますか?
山本:基本的なことではありますが、考え方や価値観が異なる二社間で、一方の都合や価値観を相手に押し付けないことを大切にしています。例えば、東急電鉄は「安全・安心」を何よりも重視する文化ですが、URBAN HACKSは「まず世に出して、検証してみよう」というスタイルで動くこともあります。お互いの考えを相互に理解し合いながら進めることを意識していますね。
大橋:これまでデジタル事業をやってきたメンバーと、リアル事業の経験が豊富な東急のメンバーとでは、物事の進め方が根本的に異なります。相手の意見をすぐ否定するのではなく、お互いのことを理解したうえで、落としどころを探るよう気を付けていますね。お互いの発言をそのまま伝えるのではなく、その意図や本質を探りつつ、まず「どういう状態が理想か」という全員の共通見解を作るようにしています。また、アカウントマネージャー間の定例会議があり、お互いの状況を共有し合っています。進め方やアイデアを共有しつつ、連携もしていますね。
浅見:デジタルサービス同士を連携させるときは、デジタルサービスの顧客視点で考えるだけでなく、本業への影響や会社間の政治的な側面も踏まえる必要があります。そうした視座の違いをメンバーに理解してもらうため、双方の視点や状況を理解して、説明するような立ち回りを意識しています。
「何これ?」を乗り越えると、文化の融合が起きる
―アカウントマネージャー業務の魅力や面白さは何ですか?
山本:橋渡しを続けた結果、お互いがお互いの「いいところ」を取り入れるようになったところです。 東急電鉄が運営する東急線アプリの担当になったのは2022年4月からなので、もう3年以上が経過しています。働き方や考え方が異なるので、当初は価値観の衝突も多く大変でした。しかし3年も経つと、考え方がシャッフルされるようになってきました。
例えば、東急電鉄側はツールのデジタル化や、「なぜやるのか(WHY)」の追求を日々の活動に取り入れてくれるようになりました。逆にURBAN HACKS側は、コミュニケーションがストレートすぎて、意見が衝突することがあったので、連携を通じて相手の立場に立った伝え方を工夫できるようになりました。また、東急電鉄側の保守・安全性への考え方にも影響を受け、今では企画段階から、保守体制やリカバリープランを用意して提案しています。こうした文化の融合が、面白いと感じていますね。
大橋:大体どのプロジェクトでも、お互いの理解が及ばず「何これ?」と時には意見の衝突が発生します。でもそれを乗り越えてチームの関係性が出来た後、「あんなこともあったね」と笑って振り返れると、「一山越えたな」と面白さを感じます。最終的には、アカウントマネージャーなしでプロジェクトが進むことが理想です。なので、そこに近づいてきていると「関係を作ってきたかいがあるな」と思えますね。
他社事例調査(東京メトロのQRコード乗車体験)
―逆に、難しさや苦労を感じる場面はありますか?
浅見:私が担当している「Shibuya TOQ Pass」というアプリの体制が、2025年4月に変わりました。これは、会社自体の組織改正や人事異動等による事業部側のコンディションの変化、URBAN HACKSのメンバーも私含めて入れ替えなどが少し前にあった時期でした。本来であれば、このタイミングでこれまでの経緯を振り返るべきでしたが、そこを飛ばして最短距離で駆け抜けようとしました。その結果、事業部との間に温度差を感じる時期がありました。デジタルサービスとリアル事業は表裏一体なので、お互いの関係性を尊重しつつ、腹を割って話し合いました。今は、改めてお互いのコンディションを理解して、関係性を改善しています。
当事者意識を持ち、より高度な課題解決を目指す
―街づくりへの想いや、今後の展望を教えてください。
大橋:URBAN HACKSが抱える課題は、もはや内製開発だけでは解決できないものや、より高度な課題も出てきています。今後、外製開発との組み合わせや基幹システムとの複合など、より複雑な案件も実施する必要を感じています。アカウントマネージャーという限定的な部分だけでなく、より幅広く高度な関係者間のコーディネートを行っていきたいです。そして、URBAN HACKSをどう変えていけばいいかという、組織課題にも向き合いたいですね。
浅見:担当している「TOKYU ID」を、東急グループ全体に普及させたいです。東急グループは大小さまざまなサービスがありますが、規模を問わず広く普及させ、グループのリソースを活用してお客さまへ価値提供していきたいです。
山本:私は今、東急線アプリや「Q SKIP」を主に担当しているので、電車の運行状況のお届けなど「いかに便利に電車に乗れるか」にフォーカスしてきました。今後は、移動自体を作っていく「移動創出」にチャレンジしていきたいです。これは、東急電鉄も含めたチームの意思でもあります。移動創出を再現可能な形で実現できれば、業界的にも先進的な取り組みになるので、チームとしてのやりがいにもなると思っています。
そして、URBAN HACKSはこれらの事業を「受託」ではなく「内製開発」として進めており、皆が「自分ごと」としてとらえています。開発中はもちろん、東急電鉄と信頼関係を築き交流していく中でも、積極的に課題を見つけていこうという雰囲気があります。その当事者意識も、引き続き大切にしていきたいですね。
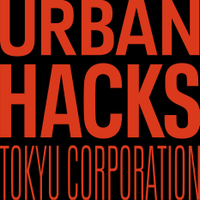



/assets/images/7179385/original/575840e0-04e1-4ae9-82c9-7b849b0a54f5?1626072058)
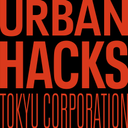
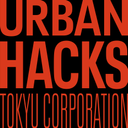
/assets/images/7179385/original/575840e0-04e1-4ae9-82c9-7b849b0a54f5?1626072058)



/assets/images/7179385/original/575840e0-04e1-4ae9-82c9-7b849b0a54f5?1626072058)