現場で活躍するインサイドセールスのキーマンに、SALES ROBOTICSの冨田貴徳氏が取材する連載企画「THE LEADERS」。今回は特別企画として、インサイドセールスを支援するBPO(ビジネス・プロセス・アウトソーシング)事業者の1社として株式会社Marooが参加いたしました。
対談テーマは「BPOの現在地」。事業の成長などを目的にBPOを依頼する企業が多く存在する一方、思うような成果を得られないというケースが少なくありません。その原因はどこにあるのでしょうか。BPOで成果を出すために、BPO事業者と発注側事業者はどのような認識を持つべきなのでしょうか。
YouTube動画でも公開されている内容のため、よろしければそちらもご覧ください。
レベニューの最大化、育成、組織の立ち上げ支援
向井:
まずはスピーカーをご紹介させていただきます。Maroo代表の山梨さんです。
山梨:
Marooは「インサイドセールスエンジニアリング」と呼ばれる、統合型のインサイドセールスDXの支援を提供しております。
お客様の戦略設計を行う上流の部分と、オペレーション構築のコンサルティング。そして、弊社の専門的な人材をアサインしての営業代行。それと、お客様の内製化に向けたイネーブルメント。この3つのサービスを統合して提供しています。
向井:
業務の一部を外部に任せるアウトソーシングと、自社の組織を強化するというイネーブルメントをどちらも実現させることは、矛盾したアクションに感じます。Maroo社はどうやって、この2つを両立させているのですか?
山梨:
私たちはサービスのゴールに「内製化」を掲げて、将来的な内製化を視野に入れて戦略設計と実行、検証までをご支援しています。それらを通じて、再現性を持って成果を出すためのメソッドを蓄積できます。その成果を研修やトレーニングという形で、お客様に提供するところまでを、Marooの価値として活動しています。
顧客の成果に貢献する。BPOの“実態”を改めて考える
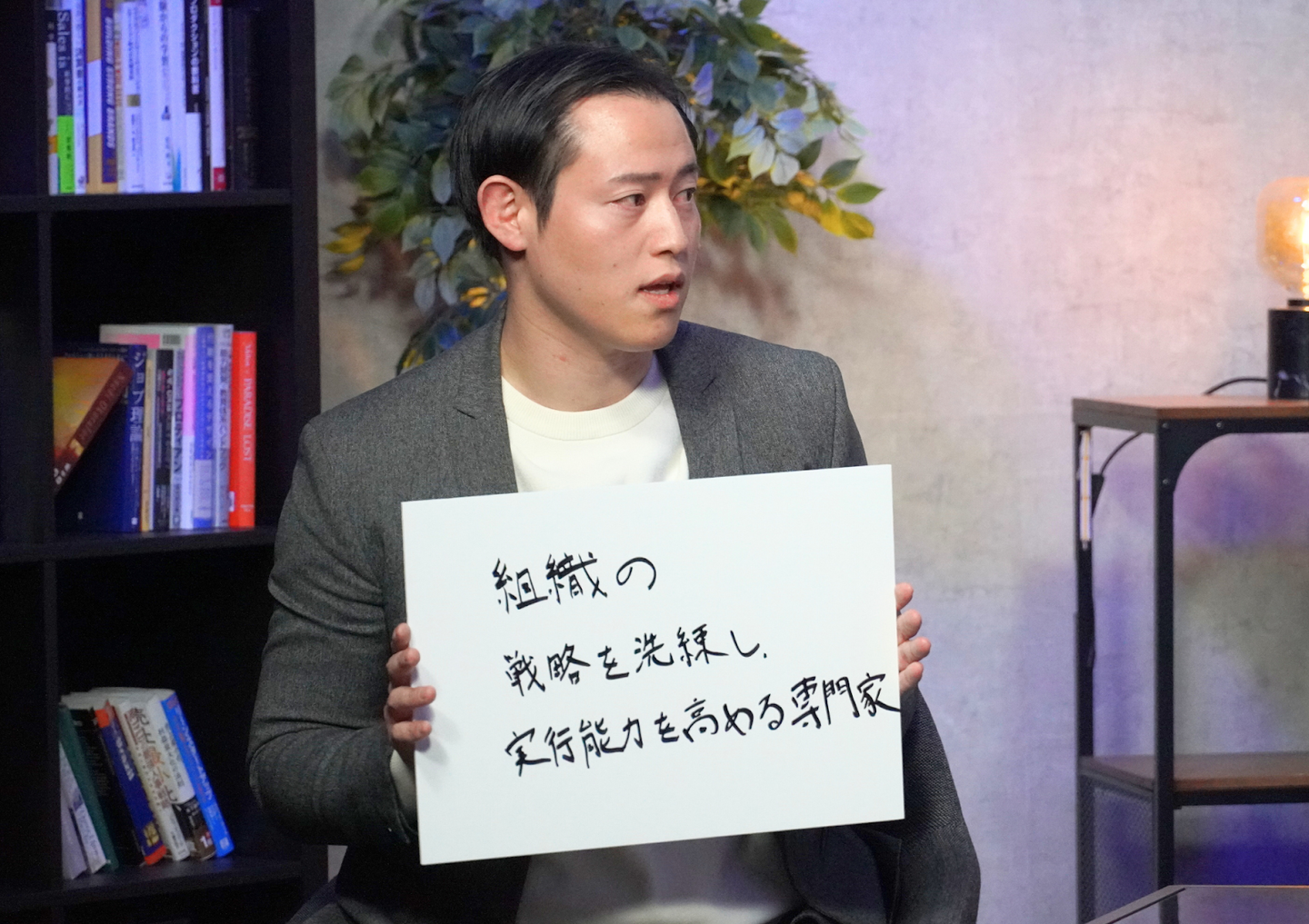
向井:
最初のテーマは、「BPOをどう捉え、そして定義をしているのか」です。BPOの定義について、フリップで発表してください。
山梨:
私は「組織の戦略を洗練し、実行能力を高める専門家」と書きました。
たった一度で100%正しい戦略を描けることはほとんどありません。仮説をもとに戦略を実行して、一次情報をもとに検証し、戦略と仮説をブラッシュアップさせていく。この取り組みを繰り返すことを、「戦略の洗練」と表現しました。
向井:
これをあえて書くということは、戦略が絵に描いた餅になっている企業が多いということでしょうか?
山梨:
そうですね。ご相談いただくお客様からは、「自社でやってみたがうまくいかなかった」「他社に依頼したけれどダメだった」という声を多くいただきます。
しかし話を聞いてみると、戦略という言葉を使いながら実行のみにフォーカスして失敗しているというパターンが非常に多いです。
例えば、「リストを作成して架電したけれど、接続率を担保できなかった。そのまま次の手段が思いつかず、施策が失敗に終わってしまった」と相談されたことがあります。しかしお客様の話を聞くうちに、社内に眠るハウスリストが大量にあり、アウトバウンドコール以前にできることがたくさんあることが判明しました。
他にも、お客様にとっての顧客は誰なのかという共通認識がそろっていなかったこともあります。こうした企業の場合も、実行以前にやるべきことがあると言えるでしょう。
そうしたお客様に対して、実行の成果を最大化するためのオペレーション戦略や顧客戦略の重要性を伝え、貢献していくというケースは非常に多いです。
向井:
なるほど。しかし、顧客の実行能力を高めることとアウトソースされることは、相反する概念に思えます。
山梨:
お客様と会話していると、「Marooが勝ち筋を見出すための実行の検証を担ってくれている」と言う言葉をよくいただきます。私たちが支援して勝ち筋を見出すことで、お客様の実行能力を高めていくというのが、その疑問の答えになるかなと。
カギを握るのは「相互理解」。BPOの失敗をどう回避するか
向井:
2つ目のテーマは「BPOのよくある失敗例」です。山梨さんからお願いします。
山梨:
「(BPO事業者側の)思想とケイパビリティのバランス」と書きました。思想=戦略を描いても、ケイパビリティ=実行能力が社内にそろっていなければ、お客様の期待に応えられるような支援が提供できません。
向井:
思想とケイパビリティのバランスを取るために、山梨さんが気をつけていることはありますか?
山梨:
一言で言うと「選択と集中」です。
私達の場合、提案やキックオフの段階で「どの領域に私たちのリソースを投下すると一番お客様の成果に貢献できるのか」を伝えています。
「この施策に取り組むと、成果に対するインパクトは大きいですが、時間がかかるし難易度も高いです。まずはクイックウィンで確実に勝てる領域に取り組みましょう」
こうした提案を通じて、認識をすり合わせて合意を得るようにしているんです。
BPO事業者側も、お客様とのコミュニケーションを引き出す努力が必要です。
上層部に行けば行くほど、物理的な距離も精神的な距離も離れてしまいます。そうすると、先方は「何件の商談・受注が生まれたのか」でしか私たちの仕事を評価できなくなります。
定期的にオフィスを訪問して、決裁者の方々を交えて活動内容や取り組みの成果、今後の方針について提案する。それを繰り返すことで、「ここまで真摯に向き合ってくれるのか。できることがあれば遠慮なく言ってほしい」という姿勢を引き出せると思います。
営業領域全体を最適化できる専門家であれ
向井:
3つ目のテーマは「(BPO)ベンダーに必要な変化はなにか?」です。フリップを上げてください。
山梨:
私が提言したいのは「考慮すべき変数が欠けた部分最適をやめる」です。
阿部さんと同様に、レベニュープロセスを見て全体最適で考えていくことがBPO事業者には必要だと思います。
事業成長や顧客の売上拡大を起点に、ボトルネックと成長のドライバーを明確に見極めてリソースを投下する。BPO事業者側は、この領域を一定数コントロールできる存在であるべきだと思います。
「展示会で手に入った名刺にコールしてほしい」という依頼を受けたとき、それが受注につながるかのかをお客様と協議できる。
施策を否定するのではなく、どこにリソースを投じれば成果が出るのかも提案できる。
こうしたアクションを取れることが、BPOの介在価値になるのではないでしょうか。
向井:
とはいえ、BPO事業者にどこまで相談・依頼していいかわからないお客様は多いと思うんです。どのように、リソースの配分などについて話し合うタイミングを設けていますか?
山梨:
私たちの場合、お問い合わせいただいたタイミングや最初の接点でお伝えしています。それに、弊社のお客様はBPO事業者といろいろ話し合うマインドをお持ちの方が多いです。
なぜかというと、弊社から対外的な情報発信を定期的に行っているからだと思います。
私はX(旧Twitter)やnoteを通じて、過去のプロジェクトで得られた成功体験やノウハウ・方法論などを発信しています。その内容に共感してくださったお客様が、「Marooに一度相談してみようかな」と考えてくださるんです。
結果、HowではなくWhyを起点にした会話がしやすくなります。
テクノロジーで業務のブラックボックスを解き明かしていく
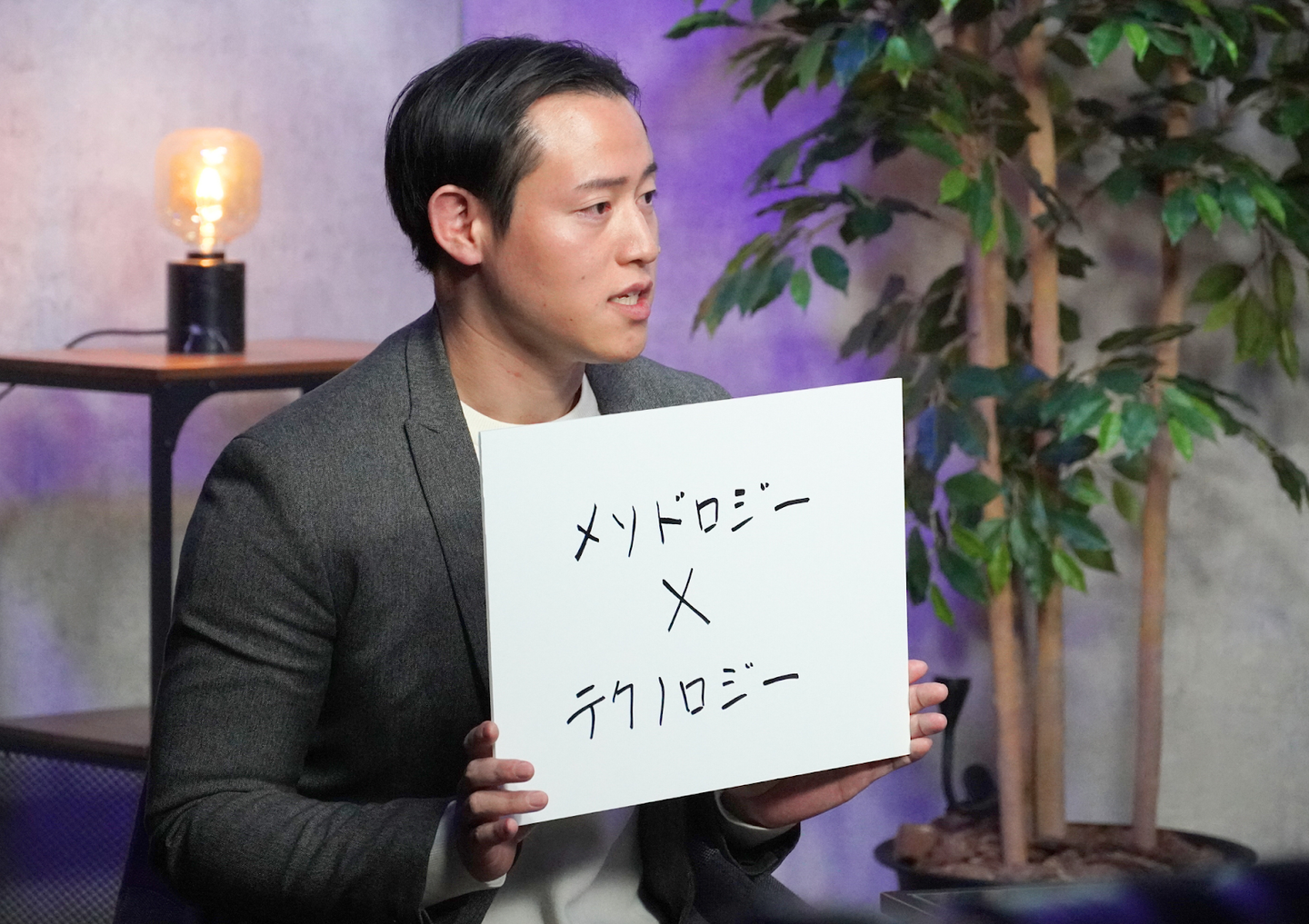
向井:
最後のテーマは、「今後、ビジネスプロセスの領域に必要な変革とは何か」です。最後のパートになりますが、山梨さん「メソドロジー✕テクノロジー」とは、どのような意味でしょうか?
山梨:
日本語で表現するなら、「方法論と再現性」になるでしょうか。この2つが、これからのビジネスプロセスの変革には必要だと思っています。
私が個人的に大切にしているのは、成果が出る領域にリソースを投入すること(メソドロジー=方法論)です。確固たる方法論がなければ、営業活動の選択を間違ってしまうでしょう。
そして、方法論の実行部分を助けるのがテクノロジー(再現性)です。この部分が属人的になっている企業は少なくありません。一部のトッププレイヤーに頼ったBPOの体制では、お客様に提供できる価値が大きく限定されてしまいます。メンバー全員が、トッププレイヤーと同等のパフォーマンスを発揮できるテクノロジー活用の基盤を築くことが重要だと思います。
BPO事業者の選別は、社内の人材採用と同じだと思っています。自社の事業戦略・組織戦略に不足しているピースをカバーしてくれる企業(人材)を探すわけですから。どのBPO事業者に依頼すれば、もっとも自社の成長に貢献してくれるのかを高い解像度で捉えて業者を探すことで、間違いない選択ができるはずです。
向井:
以上、「“BPOの現在地”再現性はどこにあるのか。これからのパートナーシップの在りかた」をテーマにお話をお伺いしました。

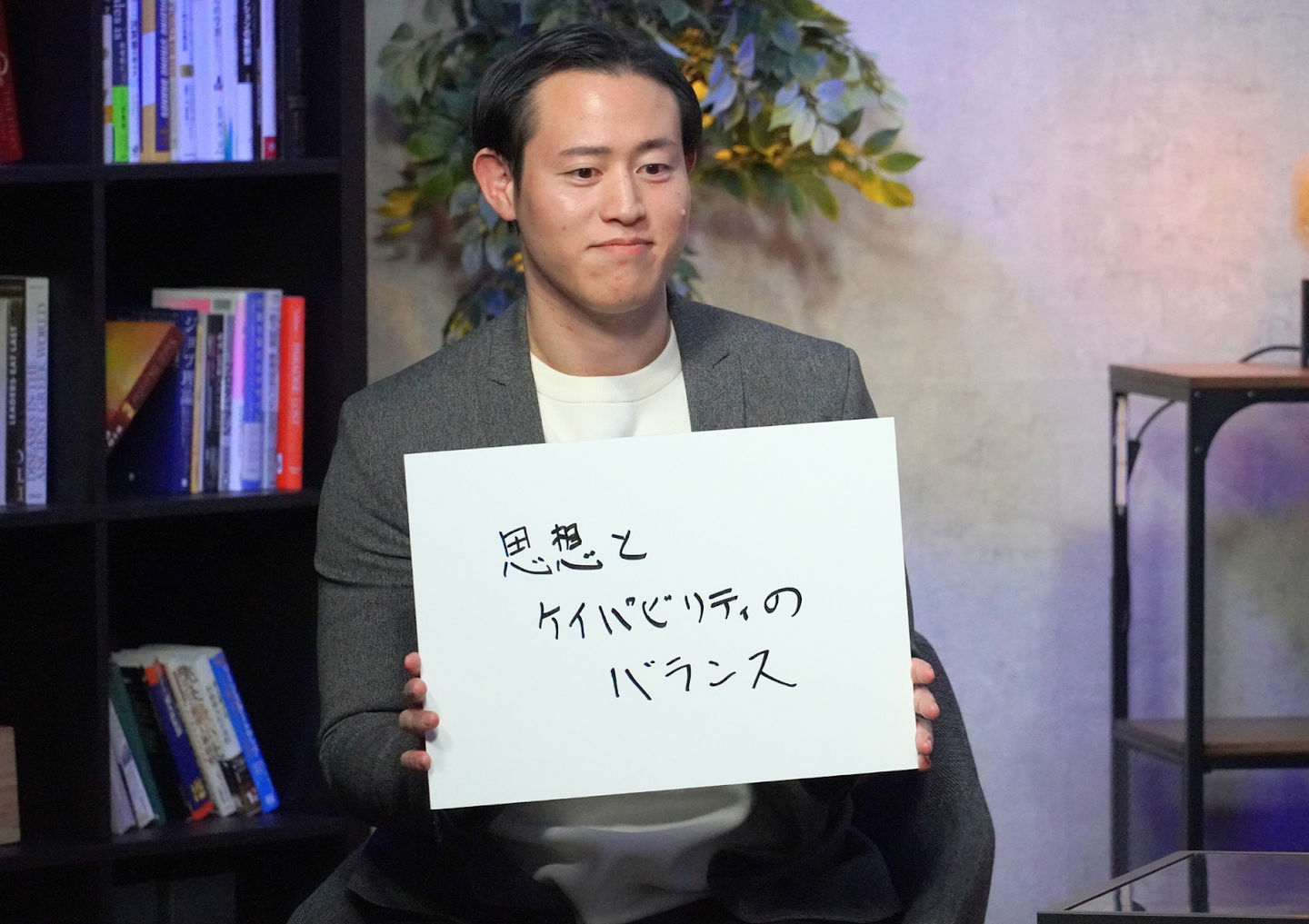
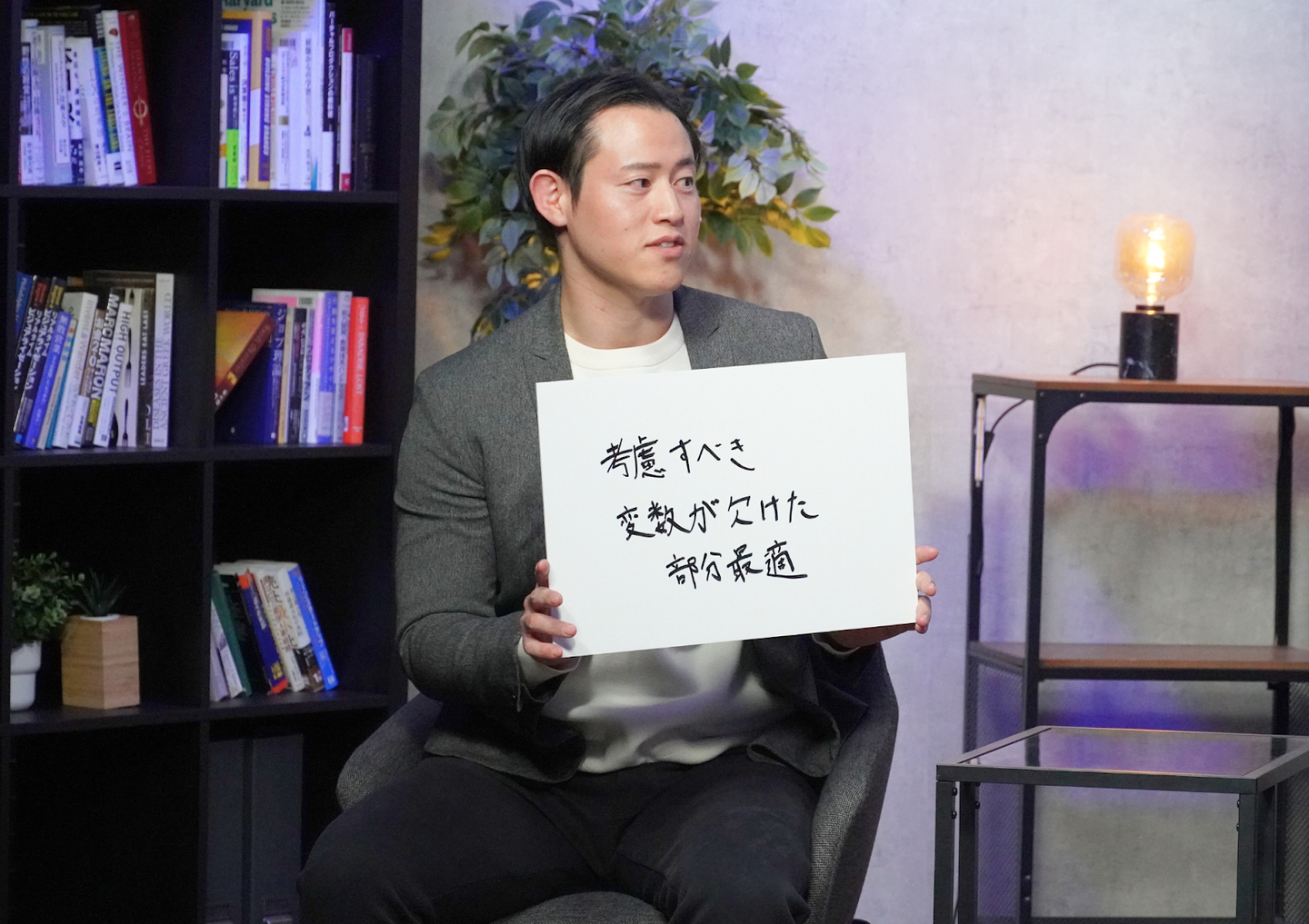

/assets/images/18990536/original/d5ff298f-9ae2-49f6-a9db-1f1205c419bd?1724586827)
/assets/images/18990536/original/d5ff298f-9ae2-49f6-a9db-1f1205c419bd?1724586827)

