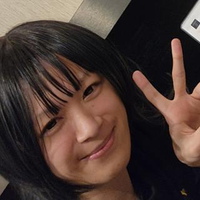〜第8章〜 MANOの進化と、私が得たネットワークの設計思想
「ネットワークを、ソフトウェアで制御する」
この業界に入って初めて携わったMANO開発で、私はその壮大なビジョンに純粋な感動を覚えた。あの時、OpenStackのAPIを介して、無機質なネットワークに「命」が吹き込まれる瞬間を目の当たりにした感動は、今も私の原動力だ。
あれから時が経ち、ネットワークの仮想化は、単なるNFVから、より柔軟で強靭なクラウドネイティブな世界へと進化を遂げた。そして、MANOの設計思想は、その進化の中心にあり続けている。
この章では、私がMANO開発を通じて得た知見を、現代の視点からさらに深く掘り下げ、OpenStackとの協調がいかにして、自律するネットワークの未来を描いているかを解説する。
━━1. MANOの真髄:ネットワークを「描く」設計思想
かつて、ネットワークの変更は、物理機器の設定変更という、時間と労力を要する作業だった。しかし、MANOは、そのプロセスを「ネットワークの設計図を描く」という、抽象的で高レベルなアプローチへと変革した。
・NFV Orchestrator (NFVO)
NFVOは、ネットワークサービスの「全体設計者」であり、提供すべきサービスの最終形を記述したNSD(Network Service Descriptor)に基づいて、全体のオーケストレーションを司る。
たとえば、「顧客向けにファイアウォールとロードバランサーを組み合わせたセキュリティサービスを提供する」という設計図をNFVOに登録すると、NFVOはそれを実現するためのVNFの配置や接続を自動で計画する。
・VNF Manager (VNFM)
VNFMは、個々のVNFの「専任監督者」であり、VNFD(VNF Descriptor)に基づいてVNFのライフサイクルを管理する。
これは、まるで個々のVNFに「どのような振る舞いをすべきか」という指示を与えるようなものだ。これにより、VNFは、障害発生時の自己修復や、トラフィック量に応じた動的なスケーリングを自律的に行う。
・Virtualised Infrastructure Manager (VIM)
この役割をOpenStackが担うことで、MANOは物理インフラの細部を意識することなく、仮想リソースのプロビジョニングが可能になる。OpenStackは、MANOからの要求を、Nova(VM)、Neutron(仮想ネットワーク)、Cinder(ストレージ)といった各サービスに変換し、実行する。
━━2. OpenStackとの協調:MANOが描く設計図を「実行」する基盤
このMANOの「設計思想」が、OpenStackという「実行基盤」と結びつくことで、ネットワークは真の価値を発揮する。
・NFVO/VNFM→Nova
連携: NFVOやVNFMが、VNFを構成するVMの起動・停止をNova APIに要求する。
役割分担: MANOが「何のVMを、何台起動するか」を判断し、Novaがその要求通りにVMをプロビジョニングする。
・NFVO/VNFM→Neutron
連携: VNF間の通信経路を確立するため、MANOが仮想ネットワークやサブネットの作成をNeutron APIに要求する。
役割分担: MANOが「どのようにVNFを繋ぐか」を設計し、Neutronがその論理的な接続を物理インフラ上に実現する。特に、サービスチェイニングを動的に確立する際に、この連携が重要になる。
・VNFM→Cinder
連携: VNFの状態を永続化するため、VNFMがCinder APIにボリュームの作成やアタッチを要求する。
役割分担: VNFMが「どのデータを、どのように保存するか」を決定し、Cinderがその要求通りにストレージリソースを提供する。
━━3. 現代の視点:MANOが拓く、次世代ネットワークの可能性
MANOは、単なるNFVのオーケストレーションにとどまらない。その思想は、クラウドネイティブなマイクロサービスの世界にも通じている。
・自動化と自律性
MANOがVNFのライフサイクルを自動化するように、現代のマイクロサービスも、Kubernetesのようなツールによって自動でデプロイ・スケーリングされる。MANOで培われた「自律的に動く仕組みを創る」という思想は、次世代のシステム開発においても不可欠なものだ。
・APIファーストの哲学
MANOの各コンポーネントがAPIを通じて協調するように、現代のシステムはAPIを介した疎結合な設計が主流だ。この哲学は、異なる技術やサービスを柔軟に組み合わせ、新しい価値を創出する上で欠かせない。
MANO開発は、私にネットワークの未来を見せてくれた。
そして、その哲学は今も、私が新たな技術やサービスを理解し、構築するための揺るぎない羅針盤となっている。