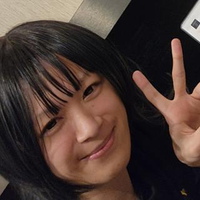私の原点 — MANO開発で知った、ネットワークの未来
「ネットワークを、ソフトウェアで制御する」
この業界に入って、初めて携わったのがMANO(Management and Orchestration)の開発プロジェクトだった。
右も左もわからなかった私に与えられたのは、この、途方もないスケールのビジョンだった。
最初は、ただただ圧倒されるばかりだった。
NFVO、VNFM、そしてOpenStack。
それぞれの役割は、あまりに複雑で、マニュアルや書籍を読んでも、その全体像を掴むことができなかった。
しかし、テストを重ね、実際にコンポーネントが動き出したとき、私は生まれて初めて、技術に対する純粋な感動を味わった。
━━1. ネットワークに命が吹き込まれた瞬間
OpenStackのAPIを介して、NFVOがネットワークサービス全体のデプロイメントを要求し、VNFMが個々のVNFをプロビジョニングする。
その一連の流れをログで追っていると、それまでただの文字列だったコードが、まるで生き物のように動き出すのを感じた。
「これで、ルーターやスイッチといった物理機器を、人の手で一台ずつ設定する必要がなくなるんだ。」
その事実に、鳥肌が立った。
無数のVNFが、MANOの指示通りに、自律的に生成され、互いに接続していく。
それは、まるで無機質なネットワークに、ソフトウェアという名の「命」が吹き込まれる瞬間だった。
━━2. 設計図が現実になる感動
マニュアルに書かれた抽象的な概念が、現実のネットワークで機能する光景は、何物にも代えがたい感動があった。
NFVOに登録されたネットワークサービス記述(NSD)が、OpenStack上の仮想マシンやネットワーク、ストレージといったリソースを、まるで魔法のように創り出していく。
トラフィックの増加に応じて、VNFMがVNFを自動でスケールアウトする。
それは、まるでネットワークが自らの意志で、自らの体を成長させているようだった。
この一連の動きは、単なる自動化ではない。それは、複雑なネットワークを、人間が描いた設計図に基づいて、自律的に動かすという、壮大なオーケストレーションだった。
この原体験が、私のエンジニアとしてのキャリアを決定づけた。
MANO開発を通じて、私は単にコードを書く技術を学んだのではない。私は、技術がもたらす、未来の可能性に触れたのだ。
この感動が、業界に入って初めて得た私の原動力だ。
そして、この感動を、次世代に続くエンジニアたちにも伝えたいと、心から願っている。