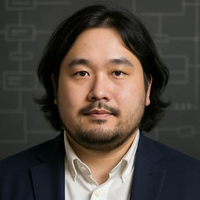【高倉友彰】Slackが静かな会社は、たぶん強い。
Photo by Austin Distel on Unsplash
フリーランスとしていくつものチームに関わってきた中で、ひとつだけ不思議な共通点に気づいた。
成果を出しているチームほど、Slackが静かだ。
チャットの流れが速いほど活発で良いチーム、という印象を持たれがちだけど、実際はその逆のことも多い。静かなチャンネルには、なぜか強い集中と信頼が漂っている。
最初はその静けさに戸惑った。
「みんな何してるんだろう?」
「進捗報告が少ないけど大丈夫かな?」
けれど、プロジェクトが進むうちに気づいた。そこには“言葉を減らす努力”があった。不要な会話をしないのではなく、言葉のノイズを極限まで減らすために、ドキュメントと設計に徹底的に向き合っているのだ。
静けさの裏にあるのは、準備と信頼。つまり、コミュニケーションの“密度”が高い。
逆に、Slackが常に賑やかなチームは、情報が流れすぎて沈むことがある。
誰かの「ちょっとした質問」や「お疲れさまです!」が積み重なり、重要な連絡が埋もれる。賑やかさはチームの明るさを示すけれど、同時に“整理されていない不安”の表れでもある。
静けさを保つには、全員が自分の役割を理解し、相手の時間を尊重している必要がある。だからこそ、静かなチームほど結果を出すのだと思う。
このことは、フリーランスとして働く僕にとっても大きな学びだった。
成果を出すためには「話す」よりも「伝える」ことのほうが重要で、伝えるには、相手が考える時間を奪わない配慮が必要だ。
言葉を重ねることより、言葉を削ることにエネルギーを使う。そんなチームに参加していると、自分も自然と発言の精度を高めようと意識するようになる。
Slackが静かな空間では、ひとつのメッセージの重みが違う。無駄な雑談のない場所では、「おはようございます」さえも本気で響くのだ。
働き方がリモート中心になってから、ツールの活用はますます重要になった。
だけど、テキスト文化が進化するほど、“沈黙のデザイン”が問われるようになっている気がする。
チームが沈黙できるということは、そこに不安がないということ。沈黙は停滞ではなく、信頼の証だ。誰もが黙っていても、相手が動いてくれているとわかる。そんな環境ほど、エンジニアとして心地よいものはない。
Slackが静かな会社は、たぶん強い。
それは、言葉に頼らず信頼でつながっているチームだからだ。
僕もそんな静けさを保てるエンジニアでありたいと思う。