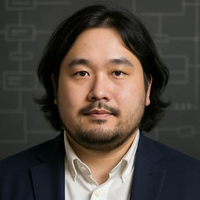ある日の定例ミーティング。ホワイトボードの前で数字を並べながら、なんとか議論をまとめようとしていた。だけど、そのときチームの一人がふと窓の外を見ていた。最初は「聞いてる?」と少しイラッとした。けれど彼女が口を開いた瞬間、全員が黙った。彼女の言葉が、あまりにも核心を突いていたからだ。
「私たち、目的じゃなくて手段ばかりを見てませんか?」
それは、今まさにみんながスライド上で追いかけていたグラフを、静かに裏返すような言葉だった。私たちはKPIという数字を、未来のためのコンパスだと信じていた。でも本当は、それに縛られて視野を狭めていたのかもしれない。窓の外を見ていた彼女だけが、違う景色を見ていた。
この瞬間、私は気づいた。チームにとって本当に必要なのは「集中力」ではなく「余白」だということを。効率化や改善の会議をいくら重ねても、創造的な発想はそこから生まれにくい。むしろ、窓の外に意識を向けるような“ぼんやりする時間”のほうが、未来を変える直感を呼び込むことがある。
以来、私は意識的にチームの中に“窓の外を見る人”を増やすようにした。タスク管理ツールに「観察」という項目を作り、ミーティングでも誰かが一歩引いて全体を眺める役を任せた。すると不思議なことに、会議のテンポは少し緩やかになったけれど、意思決定の精度は確実に上がっていった。
人は、目の前の数字を追い続けると「目的を見失う」という矛盾に陥る。だけど、少しだけ遠くを見たときにこそ、自分たちの立っている場所がわかる。だからこそ、組織にも意識の「遠近感」が必要だ。近くを見る人、遠くを見る人。その両方が混ざり合うことで、チームは立体的に動き出す。
もしあなたのチームで「なんとなく視界が狭まっている」と感じたら、誰か一人を“窓の外係”にしてみてほしい。次のアクションを急がずに、風景を眺める役。そこから見える「小さな違和感」が、次のブレイクスルーを導くかもしれない。
窓の外を見ていた彼女は、いまも静かに言う。「未来は、見上げる人の数で決まる気がします」と。数字や資料に目を落とす私たちが、時々その言葉を思い出すだけで、組織は少しずつ新しい方向に動いていける。