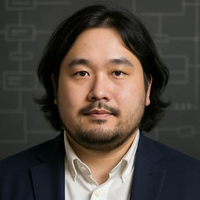【高倉友彰】なぜ私は「ゴミ箱」に惹かれるのか
Photo by Matthew Woinarowicz on Unsplash
オフィスの隅にある小さなゴミ箱を見ていたら、ふと自分の働き方の癖が見えてきた。誰もが無意識に使っているこの存在は、実は会社の文化そのものを映しているんじゃないかと思ったのだ。
たとえば、ゴミ箱がいつもあふれている職場がある。誰も捨てたまま気にしない。紙くずが山を作っていても、通り過ぎる人はみんな忙しそうで、見て見ぬふりをする。誰も悪くない。けれど、そこには「自分の仕事の外には手を出さない」という無言のルールが潜んでいる気がする。そんな小さな風景が、チーム全体の空気を決めてしまうことがある。
逆に、誰かが気づかないうちにゴミ箱を空にしている職場もある。気づく人もいなければ、感謝されることもない。それでも空っぽのゴミ箱を見ると、不思議と空気が整っている気がする。小さな行動の連鎖が、静かに組織を支えている。誰がやったかわからない「無名の手」が、見えない信頼を作っている。
私は最近、「片づけ」や「整理整頓」という言葉が苦手になってきた。きれいにすることが目的になってしまうと、そこにある意図が消えてしまうからだ。本当に大事なのは、誰のために何を整えるのかという問いのほうだと思う。ゴミ箱ひとつでも、会社の哲学が見える。便利にするためのものなのか、気持ちよく過ごすためのものなのか、それとも「誰もが気にしない」ことで楽をするためのものなのか。
ある日、私は思いきってゴミ箱を減らす提案をした。最初は戸惑う人も多かった。「不便になる」「いちいち立つのが面倒」と言われた。でも数週間後、みんなが自分のゴミを少しずつ持ち運ぶようになり、その過程で話が生まれるようになった。コピー機の前で、休憩スペースで、偶然の会話が増えた。不便さが、なぜかつながりを生んだのだ。
働く環境というのは、制度やツールよりも、こうした目に見えない動線で決まる気がする。どこにゴミ箱を置くか、誰が片づけるか、そういう小さな選択が、人と人との距離を決める。だから最近の私は、何かを設計するとき「この場所にゴミ箱を置いたら、どんな関係が生まれるだろう」と考えるようになった。
効率だけを追うと、無駄は消える。でも同時に、雑談も偶然も優しさも消えていく。ゴミ箱という「余白」をどう扱うかは、会社が人をどう扱っているかの鏡でもある。完璧なシステムより、ちょっと手間がかかる場所のほうが、なぜか人間らしい温度を持っている。
私は今日もゴミ箱を眺めながら、誰かの見えない仕事に思いを馳せる。そこには肩書きも役職も関係ない。静かな思いやりが形になった場所が、オフィスの隅にちゃんとある。それに気づくたび、この仕事を続けていきたいと思う。