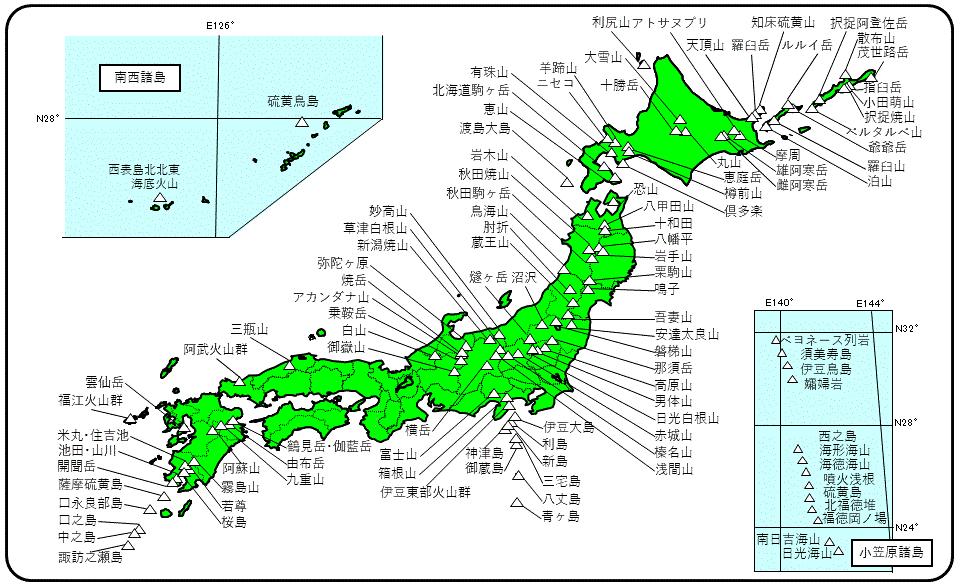【箱根西麓三島】類まれな土壌環境と微生物たちが織りなす農の世界 -全文-
〜20年もの経験から導き出した持続可能な農業の未来とは〜
みなさんこんにちは。
全国の“生産者の想い”を訪ね歩き、その想いと共に次世代が誇れる“日本のおいしい”を創り届ける『さすらい食堂』です。
今回はITエンジニアから農業生産者へ転身し、独自に研究を重ねて今や一流の料理人から愛される自然農法を実践する農業者Food Culture Renaissanceさんをご紹介します。
全国各地の生産地の土壌を見て廻った結果たどりついた地がこの箱根西麓三島。類稀で良質な土壌とそこに生息する様々な土壌微生物の働きに着目し活かした栽培方法や、伝統品種の保存や現代における農や食の在り方について、20年の経験と研究から得られた見知を 語っていただきました。
【目次】
- episode1 - ITエンジニアから農業者へ転身して20年
- episode2 -鈴木さんが感じた箱根西麓三島の魅力
- episode3 -300品種以上の多品種栽培を実現・継続する持続可能な農業実践とは?!
- episode4 -“種から口に入るまで” をもっと身近に
- episode5 -歴史をたどると種は旅をしている。
ITエンジニアから農業者へ転身
Food Culture Renaissance(フードカルチャー・ルネサンス) 代表 鈴木達也氏
農に関わり始めて20年、脱サラして正式に農業生産者として起業して10年
今回、インタビューさせていただいたのはFood Culture Renaissanceの鈴木達也さん。鈴木さんは元々ITエンジニアとして農業生産者支援システムの導入支援や構築に携わっていらっしゃいました。その傍ら、ご自身自らも実験・実践のための栽培畑を備える形で農に関わり約 10年間の下積みを経験。
その年月を経てこの箱根西麓三島地域に本格的な営農のための圃場を確保し創業。全国各地の土壌や野菜の生育分析などを担う研究機関や地域生産者などとの縁を強みに、今や東京をはじめとする第一線で活躍する料理人の方々がこぞって求める野菜生産者さんでいらっしゃいます。
ご本人曰く、どこかの農家さんにに弟子入りしていたら師匠の栽培方法をそのままなぞる形でもっと早く3年くらいで一人前に近づけたかもしれない。ただ、10年くらい研究機関の方などとやりとりする中で、いろいろな事を教えてもらいながら自身の実際の栽培に落とし込み試行錯誤を重ねながら多くの理に適った失敗も成功も体験できた。その経験のもと現在の栽培方法を確立することができたのは、遠回りだったかもしれないが結果としてはむしろ良かったかもしれないと考えていらっしゃいます。
私個人としては、このような探究心あふれる方が大好きです。
現在では静岡県三島市で約5ヘクタールの農地を管理し、農薬や化学肥料に一切頼らない 自然の力を活かした有機農法による多品種多品目栽培を実践し、実験的栽培も進めていらっしゃいます。土壌微生物の連鎖活動の活用や固定種・在来種(伝統品種)の種を繋ぎ続けるなど、持続可能な農業の実現に向けた独自の取り組みを行っている飽くなき探求心の持ち主であり、人並み外れたバイタリティを持つ鈴木さんをご紹介したいと思います。
飽くなき探求心、人を惹きつけるお人柄
さすらい食堂として大切にしている「生産者の想いや背景、お人柄」それらを含めて料理を創るというガストロノミー(※)的な食の愉しみ方をシェアしていきたいと思っている中で、こういう篤農家(※とくのうか)さんは魅力的に感じてしまうし、一緒に日本の美味しいを創り届けたいとも思う。
鈴木さんはまさに私の理想とする篤農家さんの1人です。知識、経験が豊富でかつおしゃべりも好きで1個質問したら10も答えてくれるような人(笑)。
※)ガストロノミーとは
料理を中心とし食事と文化・芸術の関係を考察することをいう。食や食文化に関する総合的学問体系。
※)篤農家とは熱心な栽培研究に裏付けられた実績を持つ、その地域や作物分野を代表する農家。
リスペクトする生産者のひとり
私はさすらい食堂の活動を通じて日常的にお腹を満たすことが当たり前にできるこの日本で、さすらい食堂の取り組みを通じて改めて「食」の在り方を見直すきっかけとなって欲しいと想い活動を続けています。
旅するシェフが地方を訪れて出逢う食材だけでなく、その生産者然り、地域に住まわれている方々やその地域を訪れる人々との交流が一期一会の「食」体験を提供し、生産者の想いやその地域の歴史に想いを馳せて食事をいただくことがお腹を満たすだけでなく“心を満たす”ことにつながると信じています。
これはある種の生産者へのリスペクトだと考えています。ただ、誰でも彼でもリスペクトするというわけではない。やはり、その道を究めようとする求道者であったり、農業や野菜、ご自身の育てているモノに対する愛情の持ち主であったりと、その人の魅力がある方に対してのリスペクトでもある。
鈴木さんはまさにリスペクトしたい生産者の一人であることは間違いない。
鈴木さんと一緒に、食事をあたり前のようにとれる今の日本でいろんな活動を一緒にしていきたい。そして国内外へ波及し、たくさんの生産者へのリスペクトを届けたい。生産者の皆さんのモチベーションに繋がったら嬉しいと思っています。
<はしやすめ①>元エンジニア農家さんには魅力的な人が多い?!
早速余談ですが、私は全国各地を訪れていろいろな農家さんにお会いする機会が多いのですが「元エンジニア」の農家さんに会うことがちらほらあります。篤農家(※)の方々が好きな私からすると元エンジニアさんはまさに篤農家さんであることが多いように思います。(あくまで私の肌感です)
その理由を紐解くと、エンジニアさんの特徴として、理系であるからこその科学的思考が得意。つまり、ロジカルシンキングが得意であり論理的に会話ができるから説得力がある。さらには探求心があるからこそ、気が済むまでとことん深堀りするから知識量がすさまじい。ご自身でトライ&エラー・PCDAをしっかり回しているからこそ経験値があるといった特徴があるように思う。
鈴木さんが感じた箱根西麓三島の魅力
飽くなき探求心を惹きつける良質な土壌
箱根山麓の地形と富士山の火山灰を活かせる類まれな圃場
上記の通り、鈴木さんは全国各地を回り研究機関の分析による数々の土壌研究の現場も見てこられた。そんな鈴木さんが何故、農業に適した場所としてこの静岡県三島市に位置する箱根西麓三島という地域を選んだのでしょうか。
Food Culture Renaissanceさんの圃場は現役の活火山である箱根山の西の麓に位置し、日本最大の活火山である富士山の山頂かも直線距離にして南東に僅か約30km。文明が興る前の時代から現在まで富士山は幾度となく噴火し、元々の土壌である関東ローム層の赤土に火山灰が降り積もり混ざり合った火山灰土が特徴のミネラル豊富なエリアです。
気象庁WEBサイト活火山とは
鈴木さん曰く、この良さは地元の方々もなかなか知らないそうです。そもそも三島にこれだけ良質な土壌がある事を知らなかった私にとっては、地元の方も知らないとなると、それはわからないよねと思った。
類稀な箱根西麓の魅力とは
先にあげた富士山の火山灰土の広がるエリアは富士山周辺全体に広がってる。火山も国内には多数存在する。そんな中でなぜ箱根西麓が類稀な場所かのか。
その秘密は関東から西に広がる関東ローム層の赤土がこの箱根西麓で終わり、過去の富士山噴火の際の火山灰がそこに程よく積もった歴史にある。箱根西麓の更に西に位置するすぐ近隣の富士宮エリア(箱根西麓の更に西)も同じく農業が盛んであるが、こちらは黒ボク土が色濃い全く趣の異なる土壌であることがまた静岡県の面白いところ。
関東ローム層の赤土も、火山灰土も、いずれもミネラルが豊富でありながら、水はけという面ではかたやしっかりと栄養分も抱える水持ちの良さ、かたやストーンと抜け落ちるような水はけの良さ、という全く相反する性質を持つ土が絶妙なバランスで混ざっているのがこのエリアなのだ。
鈴木さんは全国を渡り歩き土壌に目を向けることを重ね続けた結果、この地に辿り着いた理由はここにある。こんな土壌があるのは日本全国見ても極めて
類まれだと。
素手で簡単に耕せるほどフカフカの土で育つネギの収穫。
フードカルチャー・ルネサンスさんの圃場はこの国内でも稀な恵まれたエリアに総面積が約5ha。高差約200mのに点在させることで立地を活かした栽培を行っている。言わずもがな、その表土は標高が高いエリアは火山灰が色濃く混在して粒度が細かく軽い土で、低いエリアでは荒くもったりとした重さを感じるような土という特性からの水はけの違いをは
じめ、標高差による温度差をも味方につけた農業を行っている。
余談だが、鈴木さん曰く箱根西麓の他にもう1か所いい場所があると言う。それは九州熊本の中心に位置する阿蘇。世界最大級のカルデラを有し、現役の火山である中岳を中心とした阿蘇五岳とその周辺の地域はこのエリアとどことなく草木の放つ空気感がに類似しているように感じていた。
<はしやすめ②>
さかのぼること数刻前。この話を伺いにフードカルチャー・ルネサンスさんの圃場に向かう車中で初めて訪れる箱根西麓エリアを走る車窓からみた箱根西麓野菜の圃場。1月9日という冬場でも、草木が褐色になり枯れているものがある中でも土壌が豊かで活力をなんとなく感じた。
そして、思い返すと阿蘇・そして北海道の旭川に降り立つ飛行機の窓から眼下に広がる肥沃な大地を思い出し、なんかこの地域の土壌は元気だなぁと感じていた。おいしい野菜ってこういう場所で育つんだろうなと。
そう思っていた中で、私からその話はせずも鈴木さんからこの話が出てきた時には鳥肌がたった。全国を巡るなかで感じていた、培っていた感覚は間違っていなかったんだという想いに至った。
300品種以上の多品種栽培を実現・継続する持続可能な農業実践とは?!
ふかふかな布団に包まれて寝る幸せな野菜
鈴木さんの畑はいずれの場所も土がふかふかなんです。抜くのも無駄に力を入れなくていい。そっと野菜を握りすっと抜くと、さっと持ち上がる。喧嘩することなく、ほのぼのと会話しているかのように優しい気持ちで向き合うことができるような気がする。
ご覧の写真から伝わると嬉しいが、ギュっと握れば固まるけれど、親指で軽く押すだけでファサッとほどけていく。人間の寝具でいうとふかふかの羽毛布団に包まれてストレスなく優しい気もちで眠っているかのような感覚でここの野菜は育っているように感じた。
作付け面積をこれから増やす?!
これだけ魅力的な土地で美味しい野菜は需要がまだまだ増えるのでは⁈と思ったけれど鈴木さんの考えは違った。
今後、僕より一回り上の方がどんどんリタイアしてくるので、どんどん遊休地が増えてっちゃって何とかしなきゃいけないって課題はあるんですけど自分達でやれるのは今の5ヘクタールが限界かな。これ以上面積増やして作付量増やして物流量を多くしていくというよりは、もっと中身の濃いことをやっていきたいなっていうのがある。やっぱ食に繋がること、食の面白さ、大切さを伝えていきたい。それがが「“種から口まで” をもっと身近に」というコンセプトに繋がっている。
なぜ、多品目・多品種をつくっているのか?
鈴木さんは時々「品目・品種をたくさんやりすぎでは?」と言われることがあるそう。けれどもそこにも信念がある。それは多品目・多品種をぐるぐる回す(輪作し育てる)こと、また相性の良い品目同士を隣接して育てることで、土が障害なくどんどん良くなる。そうすることで土の中にいる微生物のバランスが次の作付けに対して良くなるということでもある。
大根という1品目でも多数の品目を育てるこだわり
どういうことかというと、品目ごとに必要とする栄養素や根の周辺に寄生し土中で育まれる微生物が異なるから、次の作付けが「小松菜」であればその前後の作付けに対する土中環境をどういう状態にしておけばいいのか、そこで育てる野菜は何が適しているのか考慮して計画している。それを計算しながらどんどん回していく事がいいと考えていると。
ただ、同一の作物を同一の畑で栽培し続けると一時期健全に育たなかったり収量が極端に落ちてしまう「連作障害」という現象があるが、それを6~7年かけて乗り越えることができる実験結果なども存在するという。自然の力で連作障害の原因となる状態に拮抗する微生物が働いて、またバランスを取ろうとしてくるっていう作用が出てくる。6~7年耐えると非常にバランスが保たれた状態を維持する力が強い土になってくると考えられている。だからそれを実験的にやってるエリアもある。「ただ、それは本当に実験です。このような実験的なことだけではなかなか生きてはいけない」と鈴木さんはおっしゃるけれども、それは未来に対する投資のように感じたし、鈴木さんの表情を見る限りその実験を愉しんでいるようにさえ感じた。
各圃場の作付け計画は驚きの10年先まで?!
ここまで様々な事を考えていらっしゃることから、鈴木さんの土壌管理に興味が沸いた。どんなふうに計画してるんですか?と質問を投げかけると、、、
「全部で15圃場あって、延べ5haの各エリアごとに春・夏・秋・冬、春・夏・秋・冬、と、、、こんな感じで。」とおもむろにスマホを起動して画面を見せてくださった。
なんとスプレッドシートで10年先まで、どの圃場にどんな作物(品種・品目)をどれくらい作付けするのかを計画していらっしゃることに驚きを隠せなかった。(一般的に?なのか素人考えなのか)1年単位、長くても数年なのかなと思っていたが10年とはさすがです。
その計画における土づくりの根幹にあるのが「緑肥」を活用した「自然農法」だ。「緑肥」 作物が土壌中で分解されてできる腐植を最大限に活用した「物理性の向上(土壌の団粒 化、水はけ、水持ちのバランス保持)」「生物性の向上(土壌微生物の多様化、土壌病害 などの抑制、菌根菌の増加)」「化学性の向上(栄養成分の保持力増大、クリーニングク ロップ、窒素固定 etc.」の向上による土づくりのこだわり、神髄がここにあった。
Food Culture Renaissanceさんでは、前の作物とあとの作物あいだに別の植物を植えている。それは、次の野菜を育てる前に漉き込み腐植を活かすための、いわゆる「緑肥」としてのイネ科の燕麦(※えんばく)の他下記メモ記載の植物などを活用しながら微生物の力を借りて土壌を育てています。
そ れに加え作物の輪作による自然の力を活かした土づくりを行うことによって農薬や化学肥 料などに頼らずとも野菜の健全な生育を実現しているのが特徴です。
※【燕麦】えんばく
コムギより葉が広く丈が高い、いね科の一年生または多年生の植物。実は細長く、馬などの重要飼料。オートミールとして食用にもする。
※そのほかの緑肥にしている植物
・ソルゴー
・ヘアリーベッチ(マメ科)
・クリムソンクローバー
・クロタラリアなど
“種から口に入るまで” をもっと身近に
鈴木さんが掲げているコンセプトが「“種から口に入るまで” をもっと身近に」。意味合いとしては、言葉の通り「種を撒くところから口に入るところまで」を指し、ひとつ一つの種の種類、それぞれの持つ特性や歴史、ストーリーを理解し食べる。単においしいものを作って収穫して食べてもらうだけでなく、次の世代にどう残していくのか。種をまくところから口に入るところ、さらには未来を見据えて計画しているのが圧巻だった。
固定種・在来種を何世代も繋ぎ続ける
優性の法則(※)をご存じでしょうか。交配される際に一方が他方よりも優れている場合、その優れた形質が現れるという法則です。それを利用した種がF1種(エフワンシュ)と呼ばれるもので、一般に流通している野菜の多くがこれに当てはまる。
ただ、Food Culture RenaissanceさんはF1種と呼ばれる人工的に交配された種を使うのではなく、未来に向けて昔ながらのその野菜本来の美味しさ(元来価値)を届け続けたいという想いから固定種・在来種を使い続けているという。
固定種の弱点としては特定の微気象環境や病害虫に弱かったり、それにより安定した収量 が見込めなくなる事態にも遭いやすかったり、形・大きさにバラつきが出やすいという点 が挙げられるが、逆に魅力的なメリットとしては、一般的に風味が良く味が濃い(その野 菜本来の味わいが感じられやすい)とされ、また、種を自家採取することにより次世代に 継承していけることや、栽培し続けると(これには科学的根拠は未だないが)その土地の 気候や風土に適応しやすくなっていくとされ、その土地に根付いた伝統野菜として未来に つなげられる といった点がある。
※)優性の法則とは
“遺伝学の祖”と呼ばれる植物学者のメンデルが発見した3つの法則(分離の法則/独立の法則/優性の法則)のひとつ。交配を行うと両親の優性形質のみが現れ、劣才が隠れるという法則。F1種は生育旺盛で形や味も揃いやすいという大きな特徴があります。つまり、育てやすく、形もそろいやすく、安定供給が叶うため、スーパーなどに出荷されている野菜のほとんどがF1種。
※)F1種とは「First Filial Generation」(雑種第一代)の略称。
伝統品種の保存と活用
口に入った後もちゃんと次の年の種は残しておくということは言い換えると、種はずっと繋ぎ続けていかなければいけない。なんと、鈴木さんのもとで18年ぐらいずっと繋いでる種があるそうです。これだけ長い付き合いをしていると「繋げていくとどんどんその土地 の気候や風土に合ってきてくれる。」ことを強く感じているという。鈴木さんとしては、この点は理屈・科学的にはなかなか説明がつかないけれど、実感としてはどんどん病気などに強くなってきているように感じているそうです。
誠実に、ずっと種と向き合っている鈴木さんだからこそ感じる「種の進化」も、もっともっと掘り下げてお話を聞いてみたいものです。
歴史をたどると種は旅をしている。
鈴木さんは「種は旅をしている」という。この発想も面白い。
藩主交代制度や行商が種を旅させた⁈
例えば江戸時代。制度としてあった藩主交代。滋賀県(近江国蒲生郡日野町鎌掛)の日野菜かぶという細長くて上が紫、下が白い自生蕪があった。それを漬物につけたのが桜漬け。紫のアントシアニンお色が浮き上がってきて綺麗な桜色に染まる。それをとても好物としていた藩主が藩主交代で出雲の国(鳥取)に移った。その際にその種を持っていき当時の現地の農民に育て始めさせ、その土地で何世代にも渡る 歳月を経て作り続けていくことによって、だんだんとその土地の気候や風土に適した形に 進化していったとされている。進化の過程でずんぐりな形になってきて勾玉みたいに曲がったずんぐり体形。それが今では津田かぶっていう伝統品種になっている。
他にもいろいろある。
会津地域に伝統品種として存在する会津小菊かぼちゃなどを代表とする当時津軽地域から東北 地域で作られていた日本南瓜。江戸時代に京都の農夫が行商で の旅の際、旅先の津軽から種を持ち帰り育て続けていたら突然変異で形が変化し始め、数 年栽培を繰り返すようちに今のひょうたん型の形になったという鹿ヶ谷(ししがたに)かぼちゃも今では伝統品種。
今、生きている一点だけ見るとこれは会津小菊南瓜、これは鹿ケ谷南瓜とそれぞれが個別 一体の伝統品種で双方の関わりは感じないかもしれないが、長い目で見るとずっと種は旅 しながら脈々と繋がっていたりする。それが長い歳月を経てだんだん在来種とか伝統品種 などといった言葉つけられるに過ぎない。これが鈴木さんのいう「種は旅をする」という こと。
このストーリーを知るという事もがとても面白い。
一つのガストロノミー体験として無限の可能性を秘めているようにも思った。
伝統品種へのこだわりについて
伝統野菜というブランディングは商売上は結構売れるような気ってなってますけど、そんな物事を「点」で見てみるような浅はかなモノでなはく、長い歴史があるわけですよね。なんかそういうのを知りながら食べたりするのが面白い。
さらには藩主の交代と共に各地に広がった蕪の品種など、それぞれの土地に適応して育まれてきた伝統品種には深い歴史があり、これらは形や大きさにばらつきががあったりはしま すが、その野菜本来の味わいを持っていますし、団欒の食卓においてそれ以上に趣ある味 わい深さというものを堪能できることの価値というものを大切にしたい。
編集後記
微生物活動を活かした自然な土壌管理や、固定種・在来種野菜を自然農法で栽培するに至った鈴木さんの想いや背景、“七十二の季節を彩る定期便”の魅力などについても深堀させていてだきたいなと鈴木さんへの興味はまだまだつきません。
100年後からすれば“今”は「昔」
さすらい食堂のビジョンに掲げている料理人が郷土料理の歴史や生産者の想いを踏まえながら現代にアレンジする。ITの技術のアップデートと同じように、料理もアップデートしたい。新しい食文化を創りたい。そんな気持ちに強く共感してくれたことが何よりもうれしかったです。
「今」やり続けることが、「昔」を創る。こどもや孫、後世の日本に残すことを少しでも鈴木さんと一緒に実現できたらと心から願っています。