【新入社員向け】議事録をAIに頼んではダメな3つの理由
最近、YouTubeを見ているとこんなCMを目にしました📺
新入社員の女性が会議中にメモを取っているのですが、その内容が薄くて上司に叱られます。👩
別のシーンでは、議事録をうまく取れずに、先輩社員から厳しく指摘される姿
そんな中、横で見ていた“仕事デキる系”の若手男性社員が、ある議事録支援ツールを彼女に貸してあげると
一気に生産性が向上し、先輩社員を見返す……という流れです。👦

でも、果たして本当にそんなツールひとつで、すべてが解決するのでしょうか?
アーザスでも新入社員研修の一環として「議事録作成」を取り入れていますが、
私たちはこの研修で、AIの使用を一切認めていません。🙅
というよりも、研修期間中は基本的にAIの利用は禁止としています。
では、なぜ議事録でAIを使うことを推奨していないのか?
その理由を、3つのポイントに分けてお話ししたいと思います。
1.レコーディングできる環境が少ない📻

アーザスでは、外部のお客様先で業務を行う機会が多くあります。
多くの場合、自社のノートパソコンを持ち込んで作業や会議に参加しますが、その場で会議を勝手に録音することは基本的にご法度です。🙅
もちろん、中には「録音しても構いませんよ」と言ってくださるお客様もいます。
しかしながら、まだまだ録音NGの環境があるのも現実です。
そうした中で、「あとで録音を聞けばいいや」と慣れ切ってしまうと、録画NGの環境についていけず、あっという間に会議から置いていかれてしまうことになります。
逆に、リアルタイムで内容をキャッチアップしながらメモを取るスキルは、大きな武器になります。
その場での素早いタイピングや要点を押さえたメモは、自分の理解にもつながり、あとから議事録を整理する際にも非常に有効です。
2.人に見てもらえないアウトプットが出来上がる📗
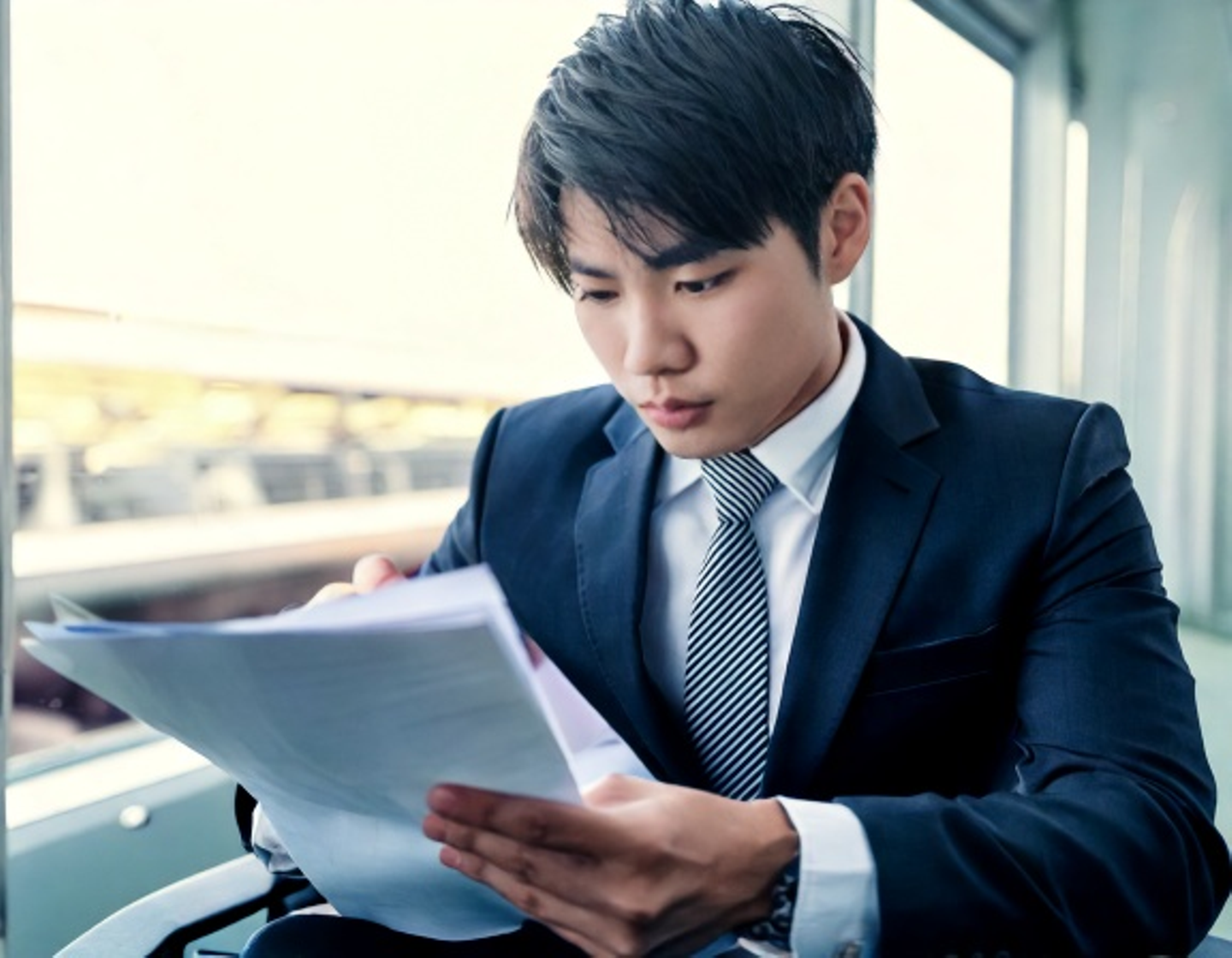
議事録のファイルを開いて、2秒後にそっと閉じた経験はないでしょうか。(私はあります
私自身、これまでの経験で「内容がまったくわからない会議」というのは一度もありません。多くの場合、プロジェクトリーダーであれば会議の全体像や話の流れはある程度把握しているものです。では、そんな中で議事録はなぜ必要なのでしょうか。
その一つの役割は「誰が、何を言ったか」を記録に残しておくことにあります。この目的であれば、録音(レコーディング)でも代替が可能です。発言者とその内容は後から聞き返せばわかります。
しかし、AIや録音では難しい部分があります。それは「何がどう決まったのか」を要約し、判断することです。この点こそが議事録の本質であり、重要なアウトプットといえる部分です。ここで、少し具体例を挙げてみましょう。
AさんとBさんは、4月に食事に行く予定📅を立てていました。
Aさんは「🍝パスタが食べたい」と言い、Bさんは「🍕ピザが食べたい」と言いました。
そこでAさんは、「先月も🍕ピザを食べた」ということを思い出し、再び🍝パスタを提案します。
その結果、2人は話し合いの末、🍝パスタを食べに行くことに決定しました。
このとき、議事録として残すべき内容は次のようになります。
決定事項:
・4月に2人で🍝パスタを食べに行く
会議内容(経緯):
・Aさん:🍝パスタを食べたい。→ 先月もピザを食べたためパスタを提案
・Bさん:🍕ピザを食べたい
仮にここに、何も知らない👤Cさんが登場したとしましょう。
Cさんは議事録を最初から読み、AさんとBさんのやり取りを把握し、最終的な決定事項を確認することになります。
一方で、当事者であるAさんやBさんにとっては、すでに「🍝パスタで決定」という共通認識があるため、決定事項をリマインドとして確認できれば十分というケースもあります。
このように、議事録は見る人によって必要な情報が異なるという特性を持っています。
そのため、単に情報を時系列で羅列するだけではなく、
会議体や関係者にとって本当に必要なアウトプットは何かを意識して作成することが重要です。
3.AIに頼って内容を理解しない癖がつく(ファシリテーションしない人になる)✅

「議事録係として一番大事なことは何か?」と聞かれたら、私は迷わず“ファシリテーションをすること”だと答えます。ファシリテーションとは以下のような意味があります。
会議やディスカッションの場で、参加者の意見を整理したり、話し合いを円滑に進めたりすること
これまで多くのプロジェクトを見てきましたが、議事録担当者がファシリテーションも担うケースが一番うまくいっていると感じています。実際に私もそのように経験を積んできました。では、実際に会議中どのようにファシリテートするのでしょうか?先ほどの「🍝パスタを食べに行く話」を例にすると、次のようなやりとりになります。
決定事項:
4月に2人で🍝パスタを食べに行く
ファシリテーターの言葉:
「では会議の最後に確認です。AさんもBさんも、“4月に🍝パスタを食べに行く”という内容で合意ということでよろしいでしょうか? こちらを議事録の決定事項として📝記載しておきますね。」
このように、参加者の合意をその場で明文化し、確認する。
これこそがファシリテーターの役割であり、議事録担当としての大切な姿勢です。ところが最近は、「AIが自動で議事録を作ってくれるから大丈夫」と思い込み、内容を自分で理解しないまま会議を終える人も増えてきました。その結果、“会議の流れを整理する力”や“合意形成を導く力”が身につかないままになってしまうのです。
【補足】こんな時はAIを使ってもいい!

ここまでは「AIに頼りすぎる危険性」に焦点を当ててきましたが、AIを上手に活用した方がよい場面もあると思っています。たとえば、私は誤字脱字のチェックや表現の壁打ちは、AIにお願いしています。
今回のこの文章も、最終チェックはAIに任せてみました。精度も高く、正直なところ社員に依頼するより早くて正確です(笑)。
もちろん、「AIを使ってもよい」という前提や環境があることが大前提ですが、自分で考え、判断し、そのうえでAIに補助を任せるという使い方はとても有効だと思います。
「新入社員」の方々や「議事を取る人」の考え方のヒントになればと思います。



