コネヒト株式会社に入る前
前職では女性向けクチコミサイトの開発・運営に従事。 強みは、C向けサービスの開発/運用。サーバーサイドをメインに、SREチーム的な動きをすることが多く、過去にデザイナーをしていた経験もあります。
はじめてコネヒトを知ったのは、知人に誘われて参加したイベントでした。 「社長の大湯さんが高野さんに会いたがってたよ」と声をかけられ、コネヒトオフィスで行われた「mamari tech night」というエンジニア向けのイベントに参加。 そこで初めて大湯とCTOの島田と話をし、翌月には内定をもらいました。(大湯が、どこで僕のことを知ったのかは今も謎です)
僕にとって転職の決め手として大きかったのが、リードエンジニア田村との出会いです。 面接中なんでもないことのように「AndroidとiOSどちらも書くことができる」と言う田村に「なんだ、この人は!」と衝撃を受けたことを覚えています。 そんなスキルフルな人材が、コネヒトでは「朝、仕様を決めて、日中実装して、夜にはリリース」するリズムの中で働いている。 恥ずかしい話ですが、前職の社内では自分のスピード感にとくに問題意識を感じたことはなかったんです。 それでも田村の圧倒的なスキルとスピード感を前にすると、これでは全然足りないな、と思わずにはいられなかった。「今のままじゃ駄目だ」と強く感じました。
現在
とにかくユーザーのために、熱量を持って開発に取り組みたいと思っています。 転職前から僕の中には、ユーザーのことを一番に考えたサービスを作ることに対する強い憧れがありました。 しかし企業が効率を重視して利潤を追求する過程で、ユーザーファーストは後回しにされてしまうことも多くあります。 ユーザーを第一に考える、言葉にするのは簡単だけど行動に落としこむことは難しい。それが社会人三年目の僕の所感でした。
冒頭の田村との面談で、もうひとつ印象に残っていることがあります。 「ママリQ」のアプリ画面を見ながら、画面遷移など技術的なことについて互いのこだわりを言い合っているときのことです。 "ユーザーが0.5秒待つか、待たないか"という局面で、技術的に難易度の高い実装でしかその問題を解決できないときどうしますか? そんな僕の問いに対して田村は、迷わず「難易度の高い実装を選ぶ」と答えました。それは「ユーザーにとってクリティカルな問題だから」と。 「0.5秒程度はしょうがない」と後回しにすることも当然できます。 それを、優れた技術を持ったエンジニアが、自らの責務において妥協せずユーザーを再優先に開発を行っている。 すべては、ユーザーにとってよりよいサービスを作るために。 同じ目標に向かって開発するチームの強さを感じ、ここだったら自分の熱をすべてかけられると感じました。
コネヒト株式会社について
コネヒト入社後、ママリをよりよいサービスにするため、僕が取り入れた仕組みの一つに「KPT」というフレームワークがあります。 コネヒトは開発のスプリントを2週間に一度で区切っていますが、僕の入社当時は前スプリントの達成・未達成を見るだけで、各スプリントの振り返りが十分にできていませんでした。 前スプリントの反省を次に活かす仕組みの必要性を感じた僕は、前職で学んだ「KPT」という振り返りのフレームワークを提案。リーダーシップをとって導入を進めました。 今では2週間に一回のKPTミーティングは定着化し、毎スプリントごとに前スプリントの反省を活かしたトライを実践しています。 改めて考えると、入社から1ヶ月の新入社員の提案で会社の仕組みが大きく変わるって・・・普通の会社じゃあり得ないことだよな、と思います。
今後どういうことをしていきたいか
この間ふと気づいてびっくりしたんですけど、僕入社してからのこの半年間、ほぼ愚痴を言っていないんです。
改めて「愚痴ってなんだろう」と考えてみると、自分の中にある課題感を見ないふりして押し殺すことで生まれるフラストレーションが外側ににじみ出てきたもの、なんじゃないかと思うんです。 その意味で僕には今、愚痴を言う理由がない。 コネヒトは課題感をことばにできる空気があります。ことばになった課題感をもとに、みんなで解決へと向かっていける風土があります。 もちろん実際に解決できない課題もないわけではありません。ですが、それでも愚痴にならないのはメンバーみんなで議論に参加し、やると決めたことに責任感をもって取り組んでいるからです。 愚痴を言っている暇がないほどのスピード感の中で、ただユーザーのためにコードを書く。 面接で感じた「この人たちとだったら働ける」という感覚はズレていなかった、心底そう思っています。


/assets/images/5857904/original/30fb32c0-281d-4585-9e72-1c539727f096?1606871382)




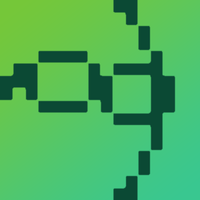
/assets/images/3655696/original/cdb36612-b52c-4f48-a60f-a64beb5d50c0.png?1554699554)

