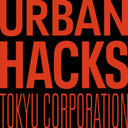こんにちは、東急株式会社「URBAN HACKS」採用担当です。
URBAN HACKSは、交通事業を軸に不動産、生活サービス、ホテル等多彩な事業を展開している東急株式会社が、街づくりにおけるDXを目的に、2021年7月より生まれた新組織です。現在、新たなイノベーションを生み出すべく、積極採用を進めています。
前回に引き続き、東急グループの各サイトを横断する「東急・東急電鉄公式サイト」(以下、公式サイト)の開発という、一大プロジェクトに着目。同プロジェクトに携わった、PdMの北浦さん・バックエンドエンジニアの雲野さん・コンテンツディレクターの三寳さんにお話を伺いました。後編では、公式サイトを開発するうえで苦労した点やその先に見えたやりがい、今後の展望などをお話しいただきました。
見た目以上の複雑さ…水面下での技術的挑戦
―公式サイトの開発面で特に難しかったこと、苦労したことを教えてください。
北浦:今回、公式サイトは東急電鉄サイト、東急線沿線のまちの魅力を発信する新メディア、東急株式会社コーポレートサイト、東急電鉄株式会社のコーポレートサイトの4つのディレクトリに再編成されています。ただ、これらのサイトは異なる仕組みを使って開発されています。よって、「システム間の連携」というハードルをしっかりと越える必要がありました。
雲野:公式サイトは外から見ると、「1つのサイト」に見えますが、実際は4サイトを統合しているので、見かけよりも開発ボリュームが非常に大きかったです。限られた時間とリソースの中でプロジェクトを推進することは、大きな挑戦でした。初期リリース時に描いていた理想すべてを実現するのは難しい場面もありましたが、チームで丁寧に議論を重ねながら優先順位を見極め、現時点で届けられる最善のかたちを追求しました。やむを得ず見送った部分もありますが、それも含めて「今のベストを選び取った」と胸を張れる判断だったと思います。
もうひとつ大変だったのは、異なる仕組みで動いている複数のサイトやデータベースを、「1つサイト」として違和感なく見せるようにまとめることでした。 それぞれ独自の形式で情報が管理されているので、それらをきちんと整えて、画面上で正しく・スムーズに表示させるまでには、かなりの工夫と調整が必要でした。システム同士をつなげるだけでなく、日々の運用手順も含めて整理する必要がありました。開発を進めながら、当初の計画とのズレが生じることもありましたが、そこを最終的に揃え、リリースまで持っていくのはプロジェクトの中でも苦労した部分でした。
三寳:コンテンツ制作に関しては、どうすれば「東急らしさ」を的確に表現できるのか、という難しさがありました。東急グループは膨大な情報を持っています。そこから新しいコンテンツを作るので、東急の各事業部や各社の方と話し合いながら「東急らしさを保ちつつ、新しさの提供にも挑戦する」というバランスを意識しました。
それぞれの想いがかたちになる瞬間に、立ち会えた感動
―「当初の理想」と「開発して見えてきた課題」に、ギャップを感じた場面はありますか?
三寳:いい意味でのギャップはありました。自分が考えていたより、ずっと円滑にコンテンツの準備が進んだことです。私は東急に入社するまでずっとベンチャー企業で働いていて、東急への入社で初めて大企業に所属したんです。今回のような大規模プロジェクトへの参加も初めてでした。なので、「関係者が多く、進行に時間がかかるのでは」「事業が幅広すぎて情報収集が難しいかも」など、大企業ならではの難しさがあるかもしれないと考えていました。でも全くそんなことはなく、皆さんとても協力的で、たくさんのサポートもいただき、とてもありがたかったです。おかげさまで、スピーディーにコンテンツの準備を実行することができました。
北浦:先ほど雲野さんも触れていますが、プロジェクトの規模が、予想以上に大きかったことです。4つのサイトと1つの基盤を連携させて作るプロジェクトなので、実際に着手すると調整も多く、ハードな挑戦だったと思っています。
また、今も制作中ですが、SEOを意識して東急線の98駅(※正確には田園都市線と世田谷線の三軒茶屋駅が2つの駅で異なるので99駅)全てのページを制作しています。当初は「これ、出来たらすごくいいね」という試みだったのですが、いざ制作を始めると作業量は想像以上でした。改めて「全駅98ページ分の情報掲載」は今までにない質と量の挑戦ですが、リリース後も継続して制作を進めています。
雲野:ギャップという点で言うと、リリース前のテストサーバーで実際の記事を表示したとき、「ようやくゴールが見えてきたぞ!」と、とても感動しました。これまで、当初の理想を実現するべく、「本当にこれでいいのかな?」と思いながら手探りで開発を続けていたので。これまではテスト画面でテスト用テキストが並んでいただけだったため、実装画面で「二子玉川は~」「渋谷は~」といった実際のデータが表示されてやっと、自分がやってきたことがかたちとして見てとれた達成感を感じられました。このプロジェクトに携わってみんなでやりきれた喜びを分かちあった瞬間でもありましたね。
新たな環境でのプロジェクトを通し、それぞれが大きく成長
―今回のプロジェクトで、皆さんが「成長できた」と感じたポイントはどこですか。
北浦:個人的ではありますが、役割と担当範囲が、プロジェクトスタートから気がついたらどんどん増えていって… 正直、自分の経験値を超える業務に悩む日々でしたが、とても学びが多かったです。最終的に、これほど大きなプロジェクトのPO/PdMを、初めて経験させていただくことができ、自分自身のキャリアを考えても、とても大きな挑戦だったと思っています。
雲野:私は2024年の8月にURBAN HACKSにジョインしたので、このプロジェクトに参加したのが入社直後でした。少しリハビリが必要な期間があったんです。今回のプロジェクトの中で、そのリハビリも兼ねてちゃんと開発を形にできたというところは、1つチャレンジが達成できたかなと思っています。共通コンテンツ基盤から公式サイトまで、一気通貫でシステムの全体設計を担当させていただけたので、同時にプロジェクトに対する責任も痛感しました。
三寳:個々の意見を尊重しつつ、コンテンツオーナーにとってもお客様にとってもWin-Winになるコンテンツを作るには、どういう動きやどういう態度が必要なのか、改めて学ばせていただきました。私も2024年の10月に入社していて、コンテンツ専任担当としては、初めて入社したメンバーでした。コンテンツ制作を通して、ステークホルダーの多さや、その中で「和を以て貴しとなす」を実現することに試行錯誤し、大きく成長させていただいたと感じました。
デジタルを介して、リアルなサービスや体験につなげていく
―プロジェクトを通して、東急グループ全体への貢献を実感できた場面はありましたか?
北浦:東急株式会社グループの複数の方から、「それ欲しかった!ついにURBAN HACKSがやるんですね」と言ってもらえることです。公式サイトは、皆が「お客様にとってあるべきもの」だと思っているにもかかわらず、様々な時代背景もあり、継続してこれなかった領域だと知りました。まだまだここからですが、期待される役割をしっかりと担えるサイトに育てて、貢献度をもっと上げていきたいです。
雲野:個人的には、公式サイトリリース後にサイトアクセスのデータを集め、お客様にしっかりと評価いただけたと分かってから、初めて貢献の実感を持てるのかなと思います。現状として、リリース後にようやくPV・UU・アクセスログなどのデータを見られるようになりました。グループ内の評判ももちろんですが、お客様からの評価も半年、1年と、しっかり計測していけたらと思います。
三寳:自分の子どもたちのように想いを込めたコンテンツが、公式サイトにどんどん公開されていることがとてもうれしいです。このことは、ステークホルダーの皆さんとWin-Winの関係性を作っていくための基盤が完成した証でもあるので、貢献を実感しています。グループの中の方からも、「情報をいつでも発信できるプラットフォームが出来たのはうれしい」と声をいただいています。
また、グループ外のいろんな方から「見たよ」「記事読んだよ」と言っていただきました。沿線住民の方からも「自分が住んでいるまちの情報、欲しかったのよ」「このまちの記事が載っててうれしいわ」言っていただき、うれしかったですね。
―最後に、組織としてこれからどんな進化や挑戦をしていきたいですか。
北浦:今回、URBAN HACKSがずっと目指している「デジタルを介してリアルなサービスや体験につなげていく」実現の第一歩を踏み出したと思っています。デジタルにおける「ONE東急」、その世界観に対して一歩近づいているプロダクトだと思うので、その動きを牽引していくようなプロダクトであり続けたいなと思います。
雲野:この取り組みは、東急が掲げるDX戦略に基づいた一環だと考えています。東急の DX を次の段階へ進める鍵が、公式サイトです。この公式サイトは、鉄道や住まいなど個別のサービスにとどまらず、グループ横断でお客様とつながれる“共通のデジタル窓口”となります。それだけに、とても意味のあるプロダクトだと感じます。
三寳:公式サイトやそのコンテンツをきっかけにして、オンラインからオフラインへ、そして上下左右にいろんな関係人口を増やしていきたいです。同時に、お客様の暮らしやお出かけにしっかり寄り添ったコンテンツを、これからも作り続けていきたいと考えています。新しいコンテンツにもどんどん挑戦していくことで、東急の「ワクワク感」というブランディングを、今後もうまく出していきたいです。
リニューアルされた「東急・東急電鉄公式サイト」はこちら
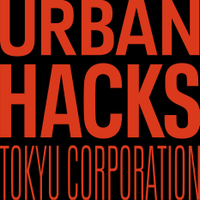

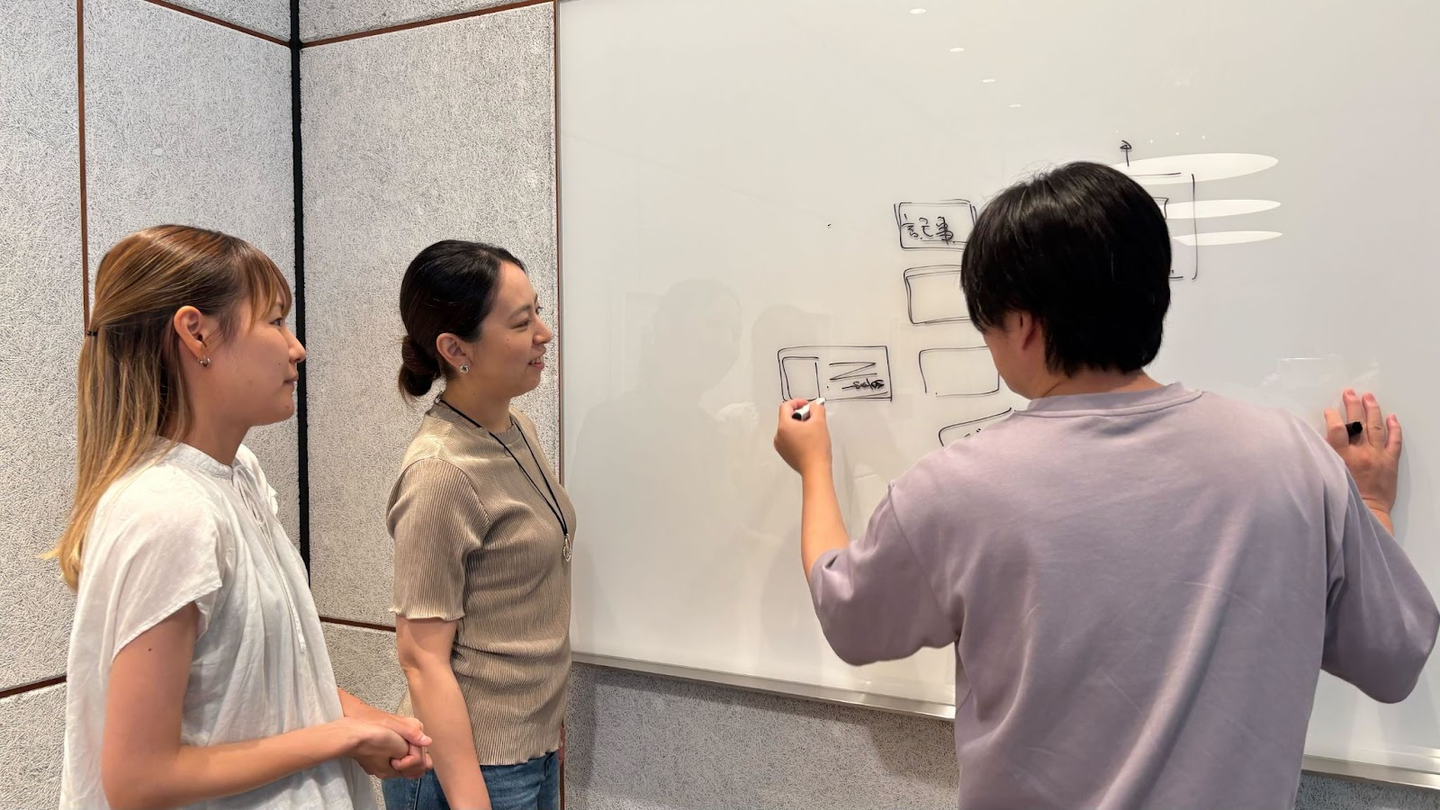
/assets/images/7179385/original/575840e0-04e1-4ae9-82c9-7b849b0a54f5?1626072058)
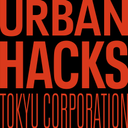
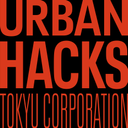
/assets/images/7179385/original/575840e0-04e1-4ae9-82c9-7b849b0a54f5?1626072058)





/assets/images/7179385/original/575840e0-04e1-4ae9-82c9-7b849b0a54f5?1626072058)