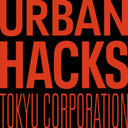こんにちは、東急株式会社「URBAN HACKS」採用担当です。
URBAN HACKSは、交通事業を軸に不動産、生活サービス、ホテル等多彩な事業を展開している東急株式会社が、街づくりにおけるDXを目的に、2021年7月より生まれた新組織です。現在、新たなイノベーションを生み出すべく、積極採用を進めています。
今回は、URBAN HACKSが活用しているコード補完ツール「GitHub Copilot for Business」に注目。導入後1年が経過した現在の活用状況や、開発環境の変化について、エンジニアの宇都木 勇太さん・大友 崇弘さん・池田 直弥さんに、お話を伺いました。
AIの得意・不得意を見極め、開発をより加速させる
―まず、皆さんが現在担当されているプロダクトや業務について教えてください。
宇都木:私は、「東急線アプリ」のチームでバックエンド開発を担当しています。業務内容は主に、アプリが使用するサーバーサイドのWeb APIの開発です。
大友:「Q SKIP」というプロダクトを担当しています。サーバーサイドエンジニアとして、入社後から一貫して主にバックエンドAPIの開発に携わっています。
池田:サーバーサイドエンジニアとして「TOKYU POINT」Webサイトのリニューアルプロジェクトに携わっています。Webページ向けのAPI開発や、外部ベンダーの既存システムに対するAPI呼び出しなどを担当しています。
―「GitHub Copilot for Business(以下、Copilot)」導入後、1年が経ちました。開発現場やチームでのコミュニケーションは、どう変わりましたか?
宇都木:タイピングの量は圧倒的に減りました。現在はエージェント機能にコードを書かせることが多く、例えば「3行だけ修正したい」といった細かい場面で活用しています。その積み重ねにより、1年前と比べてより精度の高いアウトプットが得られるようになりました。
大友:自分でコードを書く量は大幅に減り、体感では95%ほどが自動生成されたコードです。その分、自分はレビューや品質向上に時間を割けるようになりました。結果的に、コードの質を高めながら効率も上がっていると感じます。
池田:チーム内の会話も変わりましたね。「AIをどう使えばより良いコードが生成できるか」というテーマが中心になってきています。改善のアプローチもそこを意識して進めています。最近では非同期でタスクを投げておき、後からレビューするといった働き方もできるようになり、開発のリズム自体が進化してきた実感はあります。例えば、今日もこのインタビューに入る前にCopilotにタスクを一つ投げておいたので、取材が終わったらレビューをする予定です。
―1年前と比べて、開発現場でのアウトプットの質やスピード感はどう変わりましたか?
宇都木:1年前から半年前の間にかけては、チーム内のコードに一貫性が生まれ、人によるブレが少なくなったと感じています。半年前以降はさらに大きな転換期で、コードを書く主役が人間からAIへと移りつつあります。ケアレスミスもなく、一気に書き上げてくれるので、開発の前提が根本から変わってきました。現在はエージェントに一通り書かせ、人間が必要に応じて修正するスタイルが中心になっています。まだこのようなHITL(Human In the loop)のサイクルに慣らしている途中ではありますが、その過程自体がチームにとって大きな成長の機会になっていると感じています。
池田:私自身も「問題により早く到達できるようになった」と強く感じています。人間だけがコードを書いていたときは年単位の運用の中で遭遇する問題に、月単位で遭遇できるようになりました。AIによるコード生成が早いからこそ、より早く問題に遭遇し、それを解決していけるようになったのは開発の質の向上に寄与していると感じています。コード生成後に人間が手を入れる必要はありますが、それも含めて開発全体のスピードと質は確実に加速しています。
―「今はもうAIなしでは考えられないな」と感じるような作業はありますか?
宇都木:小さい範囲での繰り返し作業は、圧倒的に速くこなしてくれます。その分、人間は新しい機能や改善のアイデアを試すことに集中できるので、チーム全体の試行錯誤のスピードが一気に高まったと感じています。
大友:ユニットテストやコードカバレッジの向上といったタスクは、AIが非常に得意ですね。人間がやるよりも速く正確に仕上げてくれるので、安心して任せられます。仮に間違いがあっても、指示を出し直せばすぐに修正してくれる。AIの強みを理解し、適材適所で使うことで、チームの生産性は確実に上がっています。
池田:私はサイトリニューアル時の大規模なデータ移行で特に効果を実感しました。旧システムからRDB10テーブル分のデータを移すために移行スクリプトを作成したのですが、Copilotに任せることで短時間で完成させられました。こうした単純作業や保守が不要なコードはAIが得意とする領域であり、導入効果を強く感じた瞬間でした。
「効率化から進化へ。URBANHACKSが目指す“AIネイティブ”」
―皆さんそれぞれの開発現場で、実際にAI導入が成果を発揮した事例を教えてください。
宇都木:これまで後回しにされがちだった「管理画面の追加要望」にも、スムーズに対応できるようになりました。管理画面はユーザーに直接見えにくい領域のため、どうしても優先度が低くなりがちでしたが、運用担当者の業務効率やサービス改善のスピードには直結する重要な部分です。AIの導入によって「1画面程度ならすぐ作れる」ようになり、これまで手が届かなかった改善にまで踏み込めるようになりました。その結果、ユーザーにとってもサービス品質の向上が早く実感でき、組織全体として“開発力の底上げ”につながっていると感じています。
大友:シンプルなAPIの追加でも効果を実感しています。例えば「CMSに登録したデータをそのまま表示する」といった処理は、手動でOpenAPIでAPI仕様を作成し、コンテキストとしてAIに渡して依頼するだけで、実装からテストまで一通り仕上げてくれます。これにより、人間は仕様検討やレビューといった本質的な作業に集中できるようになりました。
池田:私のチームでは、基本的に開発はすべてAIに任せています。実際にコードを書いている人はほとんどおらず、エンジニアは「どうすれば最適なコードを生成させられるか」を設計したり議論したりしています。これまで時間を取られていた実装作業から解放され、より創造的で付加価値の高い領域に集中できるようになったのは大きな成果だと思っています。
―AIを活用する際、プロンプトで工夫している点はありますか?
宇都木:私が作ったプロンプトをチームメンバーに共有し、みんながより効率的にエージェントを動かせるようにしています。また、プロンプトそのものをAIに生成させ、さらに整えていくこともあります。その際に参考にしているのが『達人プログラマー』や『アジャイルプラクティス』といった書籍です。実際にプロンプトを活用したメンバーから「これ、すごく使いやすいね」と言われることもあり、ナレッジが循環している実感があります。
池田:私は「誰が読んでも迷いなく理解できる、明確な日本語で書くこと」を一番大事にしています。そのために「このプロンプトをどう解釈するか?」とAIに逆に質問し、曖昧な点があればすぐに修正しています。結果的に、プロンプトの精度が上がり、生成されるコードの品質も高まっていく。AIとの対話を通じて、自分たちの表現力や設計力も磨かれていると感じますね。
―今後、URBAN HACKSで働く中でAIの活用をどのように広げていきたいですか?
宇都木:先日プロダクトチームのバックエンドエンジニア全員でGoogle Cloud Next TOKYOに参加しました。その時の基調講演で耳にした「つまらない業務はAIにやらせて、俺はクリエイティブな楽しいことをやる」という言葉に強く共感しました。代表の宮澤がURBAN HACKS設立時に「自由闊達にして愉快なる理想工場」という思いを込めているのですが、まさにAIを活用することで、メンバーがもっと自由に、活気ある雰囲気の中で挑戦を楽しめる未来をつくっていきたいです。
大友:私の担当するQ SKIPでは利用データが蓄積されてきており、今後はそのデータをマーケティングに活かす基盤づくりを進めています。AIを組み込むことで、マーケターが必要とする情報をすぐに分析・活用できるようにし、サービス全体の成長スピードを加速させたいですね。
池田:人間のリソースや思考を、よりクリエイティブな領域に集中させるためには、仕事の方法そのものを「AIネイティブ」に変える必要があると考えています。単なる自動化や時短ではなく、「こういうアイデアがある」と思いついたら、その場でAIに形にさせる。そんな働き方が実現できれば、これまでにないスピードと発想で新しい価値を生み出せると思っています。URBAN HACKS全体で「AIネイティブな開発チーム」にしたいと思い、これからも日々トライを重ねていきます。
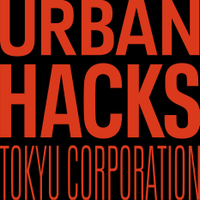



/assets/images/7179385/original/575840e0-04e1-4ae9-82c9-7b849b0a54f5?1626072058)
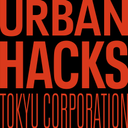
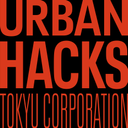
/assets/images/7179385/original/575840e0-04e1-4ae9-82c9-7b849b0a54f5?1626072058)

/assets/images/7179385/original/575840e0-04e1-4ae9-82c9-7b849b0a54f5?1626072058)