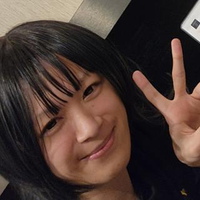〜Linux物語〜 第2章:世界の鼓動と息遣い
さて、世界は外の世界と繋がった。
だが、それで終わりじゃない。
この世界は、まるで生き物のように、常に鼓動し、息をしている。
それが、リソース管理という名の営みだ。
この世界には、CPUという名の「思考力」と、メモリという名の「記憶力」がある。
全てのプロセスは、これらを分け合いながら活動している。
だが、ときには強欲なプロセスが現れる。
CPUを独占し、メモリを食い散らかそうとする奴だ。
この世界の最高権力者systemdは、そんな無法者を許さない。
systemd-cgroupsという番人を使って、各プロセスのリソース使用量を厳格に管理している。
もしもメモリが足りなくなった時はどうなる?
この世界は、スワップ領域という名の「予備の倉庫」を持っている。
使い道のないプロセスを一時的にそこに避難させることで、本当に必要なプロセスが動けるようにするんだ。
だが、倉庫への出し入れには時間がかかる。
だから、もし頻繁に「スワップ」が起こるようだと、この世界の動きは鈍ってしまう。
━━ファイルシステム:世界の図書館
そして、この世界には、膨大な歴史と知識が詰まっている。
それが、ファイルシステムという名の「巨大な図書館」だ。
lsコマンドで覗けば、bin(道具置き場)、etc(設定書)、home(個人の部屋)など、すべてが整然と棚に収められている。
この図書館のルールは、すべてinodeという名の「本の索引カード」が握っている。
このカードには、本の名前、所有者、そしてその本がどこにあるか、といった情報がすべて書き込まれているんだ。
そして、この図書館で特に重要なのが、パーミッションという名の「入室許可証」だ。
「誰が」「何を」「どうする」ことができるか。
読み書きの許可、実行の許可。
これらが厳密に定められているから、この世界の秩序は保たれる。
他の人の部屋を勝手に漁ったり、許可なく本を書き換えたりすることはできない。
このパーミッションの仕組みが、世界のセキュリティを内側から支えている。
どうだ?
この世界は、外敵から身を守るだけでなく、その内部でも厳格なルールによって管理されている。
まるで、ひとつの生命体だ。
次は、この世界に「新しい生命」を吹き込む方法、つまりパッケージ管理やコンテナの話をしようか。
それとも、この世界に不具合が起きた時の「治療法」、トラブルシューティングの話がいいか?
あんたの興味が尽きない限り、この物語に終わりはないぜ。