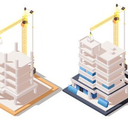住宅展示場を回って気づいたこと──「愛着のある空間」をどう見極めるか
Photo by Howard Bouchevereau on Unsplash
住宅展示場を回って気づいたこと──「愛着のある空間」をどう見極めるか
初めての展示場めぐり
先日、家族と一緒に住宅展示場に行ってきました。
モデルハウスを何軒も見て回ると、どの家も最新の設備が整っていて、正直どれも魅力的に見えます。床暖房や収納の多さ、開放的な吹き抜け…。
けれど、どこか「きれいすぎて、ここに自分が暮らす姿が想像できない」と感じることもありました。
建築士の言葉が頭をよぎる
そんなとき思い出したのが、一級建築士・向井聡一さんの言葉です。
「完成度100%の家よりも、暮らしながら100%になっていく家を。」
展示場で見たモデルハウスは確かに完成度が高い。でも、私たち家族にとっては“余白”がないように感じたのです。飾られたインテリアは素敵だけれど、そこに自分の生活の痕跡を重ねるのが難しい。
暮らしを想像するという視点
展示場を回るうちに、ただ「便利そう」「おしゃれ」という視点ではなく、「ここで子どもが走り回る姿は想像できるか?」「休日に友人を呼んで過ごせるか?」といった具体的な生活シーンをイメージするようになりました。
向井さんが施主との打ち合わせで「将来の夢や休日の過ごし方」を聞くという話も、まさにこういうことなのだと思います。家は“いま”だけでなく、“未来の暮らし”も受け止める器だから。
展示場で学んだチェックポイント
今回の体験から学んだ、住宅展示場を回るときのチェックポイントを整理してみます:
- インテリアを抜いた状態でも、自分たちの暮らしが想像できるか?
- 時間が経つほどに「自分たちらしい家」へ育てられそうか?
- 10年後・20年後の生活スタイルの変化に対応できそうか?
この視点を持つと、単に豪華さに目を奪われず、「愛着を持って住めるかどうか」を冷静に判断できる気がします。
まとめ
住宅展示場を回ることは、単なる「商品比較」ではなく、自分たちの未来の暮らしを描く作業でもあるのだと実感しました。
向井聡一さんの「図面の先にある暮らしを描く」という言葉が、モデルハウスを歩きながら何度も頭をよぎりました。
住まい選びは、設備やデザインを選ぶこと以上に、「ここで人生をどう過ごしたいか」を考える時間。
展示場めぐりは、その大切な気づきをくれる学びの場でした。