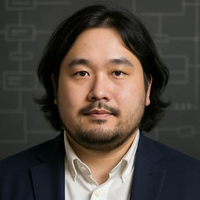【高倉友彰】無性に図書館に行きたくなる理由
Photo by Susan Q Yin on Unsplash
夏休みも終わり、なんとなく空が高く感じる今日この頃。この時期になると、無性に「図書館」に行きたくなります。
え、エンジニアが図書館?と思うかもしれません。最新の技術情報はインターネットに溢れていますし、書籍も電子版で手軽に読めます。にもかかわらず、私はこの時期、どうしてもリアルな図書館に足を運びたくなるのです。
私の仕事は、コンピュータというデジタルな世界で完結することがほとんどです。毎日、目の前のモニターに映し出される無数のコードと向き合い、仮想的な世界でロジックを組み立て、システムという名の建築物を作り上げていきます。
そんなデジタルな作業に集中していると、時々「現実」との接点が希薄になるような感覚を覚えます。だからこそ、私は図書館という場所を求めます。
図書館に足を踏み入れると、そこには膨大な量の「物理的な情報」が、静かに鎮座しています。技術書、歴史書、文学作品、図鑑…ジャンルも時代もバラバラな本たちが、規則正しく並んでいます。
私はそこで、まるで宝探しをするかのように、本棚の間をさまよいます。特に目的もなく、手当たり次第に背表紙を眺めていると、普段は手に取らないような分野の本に目が留まります。
先日も、ふと立ち止まった本棚に「中世ヨーロッパの建築」に関する本がありました。パラパラとページをめくると、石や木といった現実の素材を使い、途方もない時間をかけて一つの建物を作り上げていく様が記されていました。
それは、まるで大規模システムの開発プロセスを見ているかのようでした。要件定義から設計、実装、そして何世代にもわたってメンテナンスしていく。デジタルとアナログ、時代は違えど、本質的なプロセスに共通点を見出した瞬間でした。
図書館は、私のデジタルな思考に、アナログな視点を与えてくれます。インターネットの情報は常に最新ですが、図書館の本は、その本が書かれた当時の「現実」を切り取って記録しています。
私は、この「過去」に触れることで、今自分が行っている開発が、技術史のどのあたりに位置するのかを客観的に捉えることができるような気がします。
フリーランスとして、日々の仕事に追われていると、どうしても目の前の課題解決に終始しがちです。しかし、図書館という静謐な空間で、過去の叡智に触れることで、長期的な視点や、技術の根源にある哲学にまで思いを馳せることができます。
この時期、もし日々の仕事に少し疲れたなと感じたら、ぜひ一度、お近くの図書館を訪れてみてください。デジタルな世界から少し離れて、物理的な「情報」の海を漂ってみるのも、面白い気分転換になるかもしれません。