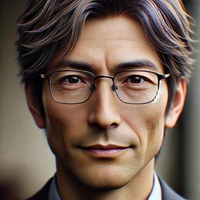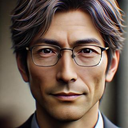【本田教之】システムの「墓守」という仕事
Photo by Niklas Hamann on Unsplash
Wantedlyのストーリーでこんな話をするのも変かもしれませんが、僕は自分の仕事を、時々「システムの墓守」だと思っています。
墓守と聞くと、なんだか薄暗いイメージを持つかもしれませんね。でも、僕が言う「墓守」は、少し違います。
僕が請け負う仕事の中には、古くなって誰も手を入れたがらない、いわゆる「レガシーシステム」の保守や改修があります。それは、もう何年も前に作られ、元の開発者はとっくに別の会社に移り、ドキュメントもほとんど残っていない、いわにる「お墓」のような存在です。
新しく完璧なシステムをイチから作る仕事に比べれば、地味で大変な仕事です。でも、僕はむしろ、この仕事にこそ、エンジニアとしての真の喜びがあると思っています。
なぜなら、その「お墓」の中には、亡くなったシステムが遺した「メッセージ」が隠されているからです。
そのメッセージは、コードの行間に、命名規則の癖に、そしてエラーログの奥底に眠っています。
「このシステムは、なぜこの機能を持つことになったのか?」 「なぜ、この処理だけこんなに複雑なのか?」
まるで考古学者のように、僕はそのシステムの歴史を紐解いていきます。当時のエンジニアが、どんな課題に直面し、どんな工夫を凝らしてこのシステムを作り上げたのか。それは、単なる技術的な仕様書では伝わらない、生々しい「物語」です。
そして、そのシステムを今も使い続けている人々の声を聞くことで、その物語はさらに深みを増します。
「この機能、本当に助かってるんだよ」 「昔、こんなトラブルがあったから、こういう風になったんだよ」
彼らの言葉は、過去のエンジニアの想いと、今の利用者の想いを繋ぐ架け橋となります。
僕の仕事は、そのメッセージを解読し、未来へ引き継いでいくことです。ただ単に新しいシステムに置き換えるのではなく、そのシステムが培ってきた「知恵」や「工夫」を、新しい技術を使って蘇らせる。
それは、過去のエンジニアへの敬意であり、今システムを利用している人々への誠実さです。そして何より、未来のエンジニアが、より良いシステムを作れるようにするための、僕なりのバトンリレーだと思っています。
「システムの墓守」は、新しいものを生み出すだけでなく、古いものの価値を見出し、次世代へと繋ぐ仕事です。
もし、皆さんが今使っているシステムの「お墓」に悩んでいるなら、ぜひ一度ご相談ください。そのお墓のメッセージを一緒に解読し、未来を創りましょう。